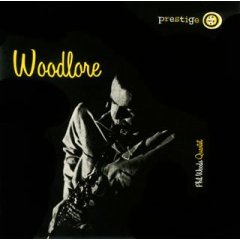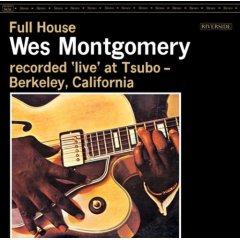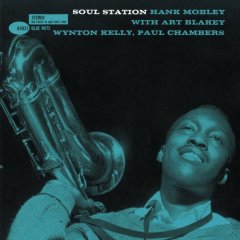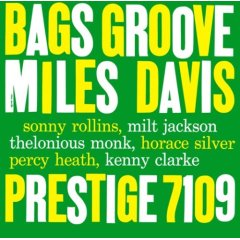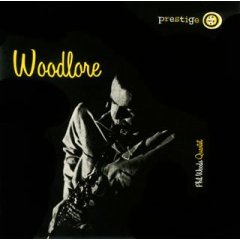
フィル・ウッズはヨーロッパ・リズム・マシーン時代のギラギラとしてメタリックというかメカニカルな吹き過ぎ感が強烈に印象に残っていて、一時期敬して遠ざけていました。その後、『ビッグ・コミック・オリジナル』というマンガ誌に連載されていた「風の大地」というゴルフマンガを読むでもなく眺めていたら、なんだかフィル・ウッズっぽい白人アルティストが取り上げられていて(バド・シャンクっぽくもあるんですが)一回腰をすえて聴いてみようという気になりました。初期から中期、そして近作まで聴いてみましたが、自分にとってツボだったのはやはり、若い頃の作品、とりわけ、『ウォーム・ウッズ』や『ウッドロア』、『スガン』などでした。アート・ペッパーほど情感を絡ませず、かといってリー・コニッツのように高踏的で超俗的でもないアルトです。程よい情感と、程よい哀愁、程よいブルース・フィーリングと優れた楽器のコントロールといった印象で、そつがないというのか駄作がない印象です。
今日取り上げる『ウッドロア』は1955年11月25日のセッション、ウッズ24歳の時です。メンバーはウッズ(as)の他、ジョン・ウィリアムス(p)、テディー・コティック(b)、ニック・スタビュラス(ds)という編成で、若きウッズがワンホーンでのびのびと吹いたアルバム。
1曲目でタイトル・チューンの "Woodlore"。ウッズのオリジナル曲で、軽快なミディアム・テンポ。流れるようなテーマ演奏から、ブレイクを経てアドリブに突入すると「パーカー・フレーズ」を分かりやすく溶け込ませながらのプレイ。続いてジョン・ウィリアムスによるピアノ・ソロは左手が活躍するブギウギスタイルで面白くなっています。そのあとはアルト対ドラムの4バースになりエンディング。
2曲目のバラード、"Falling in Love All Over Again" では、蕩けるようなウッズのアルト・サウンドが聴けます。冒頭からグリッサンドをかけたオフ・ピッチの音色で惹きつけ、華麗なキーワークでしっとりと歌い上げる。ピアノが手数の多いタイプですが、ここではアルトを鼓舞するように上手くマッチしています。エンディング処理は「上手い!」の一言。
3曲目は "Be My Love"。ルー・ドナルドソンも取り組んだスタンダードで、聴き比べてみるのも面白いかも。この曲はアップテンポで賑やかにやっても哀愁が含まれている曲。ルーには確かに哀愁がありますが、ウッズの哀愁はただ事ではない。パーカーのフレージングを混ぜ込みながら、翳りのあるフレージングが光っています。ピアノもバップ語法から少しずれた独自性のあるソロを取っています。再び4バースを経てテーマに戻って終わり。
4曲目 "On a Slow Boat to China" はロリンズの名作が光りますが、結構古い曲。ロリンズが悠然とリズムに後ろから乗っていくのに対して、ウッズは突っかけ気味に吹きます。アドリブに突入してもそのまま疾走。それでいて構成はしっかり考えられているところがさすがです。
5曲目は "Get Happy"。チョッパヤです。リフの畳みかけが多いもののバップの醍醐味を感じさせ、レコーディング時間の限界までといった感じでコーラスを重ねます。バリバリ吹くパーカー直系の面目躍如です。
ラストはオリジナル、といってもブルースの "Strolling with Pam"。ウッズのブルース・プレイの典型的な演奏となっています。
CDになって別テイクが追加されましたが、別テイクなのでここでは触れません。
ウッズ青春の輝きを捉えた名アルバムです。
Tags: alto sax · Woods, Phil

先日授業で観たルイ・アームストロングの伝記DVD『サッチモ』についての感想を集めると、多くの人がネットで調べたらしく「もう一人の天才ビックス・バイダーベックと並び称された」なんて書いてあるんですね。「もう一人も二人もビックスなんて知らないでしょうに」と思いながらも、「こうやって写しづらい名前を写すことで覚えてしまい、いつかビックスに出会う縁ができたかもしれないな」と期待もするわけです 😛 ビックス・バイダーベックという人はルイと同じ時代を生きたコルネット奏者で、ルイとは全く違ったスタイルと音色を持っていました。ヴィブラートをかけない奏法で、ルイがラッパを「吹いて(blow)」いるのに対して、ビックスの場合は「鳴らして(ring)」いるような印象の実に輝かしい音色です。彼のコルネットはたとえビッグ・バンドの中でも埋もれなかったと言われ、彼の入ったアンサンブルはそうでないアンサンブルよりもいっそう輝きをもった音色だったそうです。多くのミュージシャンから敬愛されていた彼ですが、1931年8月6日28歳でこの世を去りました。死後伝説化され、50年代にはカーク・ダグラス主演の伝記映画『情熱の狂想曲 (原題 Young Man with a Horn)』が作られ、近年でも『ジャズ・ミー・ブルース
(原題 Young Man with a Horn)』が作られ、近年でも『ジャズ・ミー・ブルース (原題 Bix)』というイタリア映画が撮られました。夭折であることと残っている写真がハンサムなため伝説化もされやすく、私は中原中也に似た印象を持っています。多くの白人ミュージシャンに影響を与えましたが、特筆すべきはマイルスに対する影響です。トランペットの主流派といえばルイ-ロイ・エルドリッジ-ディジー・ガレスピー-ファッツ・ナヴァロ-クリフォード・ブラウンというホットな系譜ですが、マイルスのラッパはそれとは異質でクールな音色を持っています。そしてそのルーツは実にビックスにあるといわれています。
(原題 Bix)』というイタリア映画が撮られました。夭折であることと残っている写真がハンサムなため伝説化もされやすく、私は中原中也に似た印象を持っています。多くの白人ミュージシャンに影響を与えましたが、特筆すべきはマイルスに対する影響です。トランペットの主流派といえばルイ-ロイ・エルドリッジ-ディジー・ガレスピー-ファッツ・ナヴァロ-クリフォード・ブラウンというホットな系譜ですが、マイルスのラッパはそれとは異質でクールな音色を持っています。そしてそのルーツは実にビックスにあるといわれています。
このアルバムはLP時代にコロムビア系の音源から油井先生が編集したもので、A面B面で計16曲が収められています。ヴィクター系の音源が上で述べたようなビッグ・バンド中心のもので、ソロは数小節であるのに対して、コロムビア系の音源には畢生の名作 "Singin' the Blues", "I'm Coming Virginia" を含むコンボ演奏が多数あり、その中から選りすぐったのがこの選集といえるでしょう。また、このアルバムには盟友フランキー・トランバウアーとのセッションも数多く収められています。このフランキー・トランバウアーという人はCメロディー・サックスといって楽器のキーがC(アルトとバリトンはE♭、ソプラノとテナーはB♭)のサックスを吹いていました。そして重要なことはこの二人が全く同じコンセプトで演奏していること、そしてレスター・ヤングはテナーでフランキー・トランバウアーのフィーリングを出そうとしたことです。つまり、ビックス-トランバウアーのコンビは、レスターやマイルスを経由して、現代に繋がっているというわけです。
A面
1. Singin' the Blues
2. I'm Coming Virginia
1927年の吹き込み。ビックスの吹き込みの中で、最高傑作といわれている2曲です。「シンギン・ザ・ブルース」のソロは同時代のミュージシャンが皆こぞって暗記したといわれる無駄のない名ソロ。また「私はヴァージニアへ」のほうは、ベニー・グッドマンのお気に入りで、伝説的な『カーネギー・ホール・ジャズ・コンサート』でもこの曲を取り上げ、ビックスのソロを一音一句再現しているほどです。
3. For No Reason at All in C
タイトルからも分かるように、フランキー・トランバウアーのCメロディー・サックスを全面的にフィーチャーした演奏。エディー・ラングがギター、ピアノはビックスです。最後にコルネットに持ち替えて吹いています。
4. In a Mist
別名 "Bixology" と呼ばれるビックスによるソロ・ピアノ。印象派のような演奏です。
5. Wringin' and Twistin'
3曲目の"For No Reason at All in C"と同じトリオによる演奏。やはりクールなトランバウアーの演奏が中心。
6. At the Jazz Band Ball
7. The Jazz Me Blues
8. Goose Pimples
Bix and His Gangというレコーディング・コンボの演奏。トランバウアーはいません。先頭に立ってアンサンブルを引っ張っていくビックスの高らかな音色が響き渡る "At the Jazz Band Ball"。 選集や伝記映画のタイトルともなった名演 "The Jazz Me Blues"。 "Goose Pimples"(鳥肌)という滑稽なタイトルにもかかわらず、力いっぱい吹いて、ソロの飛び出しまでやる8曲目など名演ぞろいです。
B面
1. Since My Best Gal Turn Me Down
2. Somebody Stole My Gal
メンバーは上記3曲と同じBix and His Gang。1.はテンポを動かしながら、自在にソロを取っていくビックスが素晴らしい。2.は吉本新喜劇のテーマでも有名な曲で、この曲から1928年の吹き込みに移っています。
3. 'Taint So Honey, 'Taint So
4. That's My Weakness Now
ポール・ホワイトマン楽団の演奏。3曲目では若いビング・クロスビーがこれまたクールに歌っています。4曲目もビングを含む「リズム・ボーイズ」というコーラスの歌入り。トランバウアーが加わってソロを取っていますが、3.で吹いているのはバスーンだそうです。
5. Ol' Man River
6. Wa-Da-Da
7. Margie
再びBix and His Gangによる演奏。どれも名演でビックスの素晴らしいコルネットが聴けます。
8. Baby, Won't You Please Come Home
ビックス研究家を悩ませるといわれるこのトラックでは、ビックスの模倣者であったアンディー・セクレストが加わっていて、ちょっと聴きではビックスのソロがどの部分か見分けがつかないそうです。アンディー・セクレストのほうが腕前が落ちるのに見分けがつかなくなっているのは、この録音の1929年、ビックスはすでに体調を壊してプレイの上でも下降線になっていたことが原因だといわれています。
今ではCDの利点を生かして、ほとんど全集といっていい量のトラックが同じような値段で手に入ります。そんな中の一つを下にリンクしておきます。
Tags: Beiderbecke, Bix · trumpet
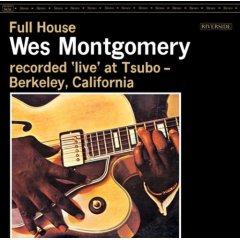
クリード・テイラー路線のウェス・モンゴメリーには批判も多いですが、私は嫌いではありません。しかし、しょせん「嫌いではない」といった程度の好みであって、『夢のカリフォルニア』を聴くときのテンションというのはあまり高くない。というか、聴くというより流してる感じです。それでは本当に気合を入れて聴くべきウェスといえば何かと言うと、答えは簡単で、彼には前人未到の3大名盤があるわけです。それは『インクレディブル・ジャズ・ギター』、『ハーフ・ノートのウェスとケリー』、『フル・ハウス』。今回はその中からホーンも入っている『フル・ハウス』を取り上げてみようと思います。
このアルバムは1962年6月25日、カリフォルニア州バークレイのコーヒー・ハウス「ツボ」でのライブ録音です。メンバーはジョニー・グリフィン(ts)、ウェス(g)、ウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、ジミー・コブ(ds)。
1曲目でタイトル・チューンの "Full House" はウェスのオリジナル。タイトルの由来はポーカーの「フル・ハウス」、つまりウェスとグリフィンがペアでリズムがスリー・カードにひっかけられたという説と、店が満員という説の2つがあります。事実、地元新聞の報道と口コミがきっかけで、通りの曲がり角まで行列ができていたという話が残っているほどです。シンプルな構造をもったリフ曲でセッションの口開けにもよく演奏される曲。イントロからテーマまでギターとテナーのユニゾンで演奏されています。ソロの先発はウェス。ホーン・ライクなアドリブから徐々にギター的なソロへと盛り上げていき、短いリフを畳みかけながら、オクターブ奏法を繰り出します。続くソロは「リトル・ジャイアント」ジョニー・グリフィン。情熱的で力強いソロを取っています。ケリーのピアノはしみじみしていますが、彼にしてはずいぶん地味なソロ。
2曲目の "I've Grown Accustomed to Her Face" は『マイ・フェア・レディー』の挿入歌。この歌詞の和訳については以前の記事でも書きましたが「ブスは三日で慣れる」という意味ではありません 😛 グリフィンとケリーが休んでウェス+ベース&ドラムスという構成で味わい深いバラード演奏に取り組んでいます。
3曲目はディジー・ガレスピーのリフ曲 "Blue 'n' Boogie"。ソロはウェスから。シングル・トーン→リフのたたみかけ→オクターブ奏法と盛り上げていくウェスいつもの構成です。次はケリー。このアドリブは盛り上がっています。グリフィンもまたおなじみの上のほうで「キュー」となる音を駆使しながら熱のこもったソロ、周りの掛け声まで入っています。ここでさらに素晴らしいのが、ドラムのジミー・コブ。ほとんど連打状態でグリフィンのソロをさらに鼓舞しています。そのままテナー対ドラム、ギター対ドラムの4バースに入り、続いてピアノ対ドラムで再び4バース交換をしていますが、これはおそらくケリーが即興的に割り込んでその場でやったのでしょう。ドラムソロをちょっとやってテーマに戻ります。
4曲目の "Cariba" はウェスのオリジナル。カリブということでしょう、ラテン・ビートです。珍しくベースが先発ソロに挑み、続いてピアノとなります。ケリーはカリブ海からの移民で、こういう曲には抜群の相性を示し転がるようなタッチと楽しげな曲想で素晴らしいソロ。続くグリフィンは速吹きでシーツ・オブ・サウンドみたいなことをしたりファナティックに畳み掛けたりやりたい放題。続いてでてくるウェスはコード・プレイまで繰り広げています。凄い!
5曲目。スタンダードの "Come Rain or Come Shine"は「降っても晴れても」の邦題がつけられた名曲です。比較的アップテンポで演奏されていますが、ここでのグリフィンは、本当に「らしい」演奏です。グリフィンの特色を掴みたかったらこのアドリブを聴けば一発です。これを超えると、やり過ぎですってんコロリンになるんですがね 8) ウェスのソロはこの曲をギターで弾くときのお手本みたいなもんです。シングル・トーン、オクターブ奏法、コード・プレイ、コンパクトに全部揃ってますよ。続くケリーは、本人名義でヴィー・ジェイに吹き込んだ『枯葉』というアルバムで、この曲の決定的解釈を披露していますが、そちらはミディアム・バウンスだったのに対して、こちらはアップテンポ。しかし転がるような音と跳ねるタッチでスイングしています。
LP時代のラスト曲が、ウェス・オリジナルの "S.O.S"。印象的な合奏を挟んだ急速調の曲です。後半、合いの手に聴こえるグリフィンのテナーが「ニャー」と猫みたいに聴こえる。例の「キューッ」って音なんですけれどね。
CDにはあと3テイク入っています。7曲目は "Come Rain"のテイク1。グリフィンに関してはこちらのほうが落ち着きがあっていい。ウェスはやはりテイク2(オリジナル)のほうがいいですかね。探り探りやっている感じですが、あからさまな三段論法になっていない分新鮮な感じもします。ケリーもオリジナル・テイクのほうがいい。S.O.Sはテイク2。こちらではグリフィンの合いの手が下を吹いているので「ニャー」とならずに盛り上がりに欠けます。最後にニャーとふた鳴きしてくれますが。9曲目はまったく別の曲で、 "Born to Be Blue"。スタンダードで、グリフィン抜きでやってます。途中でダブルタイム・フィーリングを挟みながら終始シングルトーンでホーン・ライクに進めていきます。ケリーの抑えたソロを挟んで、今度はオクターブ奏法に移行しますが決してこれ見よがしではない。実に味わいのある名演。LPの収録時間の関係で省かれたのでしょう。
上記3作はどれも名盤です。ハズレはありません。ギター一本でウェスの特色を掴みやすくコンパクトなのが『インクレディブル』、ウィントン・ケリーとの絶妙なインタープレイも聴けてスリリングなのが『ハーフ・ノート』、そしてホーンも入ってエキサイティングなのが『フル・ハウス』という感じでしょう。
Tags: Griffin, Johnny · guitar · Kelly, Wynton · Montgomery, Wes

日記ブログのほうにも書いたことですが、授業で観たサッチモの伝記映画の中で、ウィントン・マルサリスが印象的なことを述べていました。「晩年のルイはテクニックが無くなったから買わないという人がいるが、そういう連中は何も分かっていない。テクニックと速さを混同しているんだ。最高のテクニックはニュアンスである。それは人生と共に洗練されていったものだから、誰にも出せない」という彼の発言は、本人が一番学ばなければいけないような気がしないでもないですが、正しいと思います。そしてその直後に流れる歳をとったサッチモの「明るい表通りで」の演奏がナミダモノ。「ウェストエンド・ブルース」のように精緻なフレージングではなく著しく簡素化されたフレーズであるにもかかわらず、一音一音が持つ表情が豊かで深い。マイルスの場合も晩年、たとえば『ワールドツアー』のようなアルバムで聞こえてくる音は、実に深い陰翳があります。谷崎ではないですが陰翳がなければ面白くないわけです。そういえば、一時期調子に乗って「モーツアルトは陰翳がなく一本調子だからつまらない」などと放言したら、クラシックに詳しい人に呼ばれて、いろいろな演奏を聴かされて、自分が間違っていることに気づきました。演奏する人によって深い陰翳やニュアンスが生まれてくるということを知ったからです。
レスター・ヤングも全盛時代は凄かったが、軍隊生活以降はめっきりやる気を失ってダメになったというのが通説として言われていますが、これは疑問です。確かにあまりに無名で能力も怪しい連中と組まされた時や、本人の資質とまったく合わないJATP・ジャム・セッションなどではすっかりやる気を失っているような演奏もありますが、メンバーによっては実に深いニュアンスを持った演奏を行っています。全盛時代ほどの目くるめくフレーズ展開はないものの、一音にこもった音楽的な力はいささかも衰えていないのです。ここで紹介する『レスター・ヤング・ウィズ・オスカー・ピーターソン・トリオ』もそんなアルバムの一枚です。タイトルに「トリオ」と銘打っているくせに、レスター(ts)、オスカー・ピーターソン(p)、バーニー・ケッセル(g)、レイ・ブラウン(b)、J.C.ハード(ds)というクインテット、リズムが4人もいたりなんかして、ヴァーヴらしいといえばヴァーヴらしいタイトルです。演奏は1952年11月28日。曲目は下のリンク先のAmazonに全部載っていますし、便利なことに試聴までできますからそちらに譲ります。
特筆すべきは2. "I Can't Get Started"、そして、6から12にかけてのバラード銀座というか、名バラードの目白押しの部分です。とりわけ8. "On the Sunnyside of the Street" にはサッチモのバージョンと同じレベルの感情の深みがあり、「明るいのに暗い」「楽しいのに寂しい」というあい矛盾した情緒が同時に押し寄せるような域に達しています。まあ、この頃のレスターには、どの演奏にもそうした特色があるのですけれどね。わりとフェイクを強く施したAメロの演奏に続いて、サビはアドリブしています。そして再びでてくるAメロ部分でのたたみ掛けるようなフレーズの寂しさ。何かを思い出すようなフレーズです。2コーラス目のサビはこれまた深いニュアンスが込められ、その後のAメロでは一部音が出なくなっていますが、それが少しもこの演奏の価値を下げていない。非常に優れた演奏です。
私はテクにばかり耳が行ってしまったり、ジャズの原点を忘れそうになったりしたときに、耳をリセットするような意味でこのアルバムを聴きます。こっそり思っていることですが、有名な『プレズ・アンド・テディー』よりも一段深い演奏のような気がしています。
下のアルバムは輸入盤でジャケ違いです。いずれ国内盤が再発されるので、そちらを求めたほうがいいと思いますが、試聴ができるのでリンクを貼っておきます。(2009年8月現在、リンクのジャケがオリジナルになっているようです)
Tags: Brown, Ray · Kessel, Barney · Peterson, Oscar · tenor sax · Young, Lester

ケニー・ドーハムの「ブルー・ボッサ」はいろいろなアルバムで取り上げられていることからも分かるとおり、実に名曲ですね。16小節でCマイナーの構造を持ったこの曲には私も挑んだことがありますが、3番目の4小節の転調を上手く利用すると、私のようなヘタッピでも、そこそこムードのある演奏になるところが魅力です。オリジナルのライナー・ノーツでも、作曲者自信が「本物のメランコリーと快活さを持ち合わせた曲」といっていますが、Cマイナーの部分が「メランコリック」、3番目の4小節のD♭メジャーの部分が「快活」と分類されるでしょうか。
この曲の原型の一つが収められているのが、今日紹介するジョー・ヘンダーソンのファースト・リーダー作『ページ・ワン』です。録音は1963年6月3日。メンバーはケニー・ドーハム(tp)、ジョー・ヘンダーソン(ts)、マッコイ・タイナー(p)、ブッチ・ウォーレン(b)、ピート・ラロカ(ds)。ラテン物やアラビア物をやらせたらぴったりのサウンドが聴こえてきそうなメンツです。
1曲目が "Blue Bossa"。テーマが終わって、まずは作曲者のケニーがグロール・トーンを交えながら原曲のムードを生かしたソロを取ります。続くジョー・ヘンダーソンのテナー・ソロが実に味わい深い。最初の1枚、最初の1曲にして名声を確立してしまったかの感がある名ソロです。マッコイも畳み掛けるような独特のスタイルで曲のとりわけメランコリックな気分を強調しながらソロを進めます。ブッチのベースソロを経てテーマに戻ります。
2曲目は "La Mesha"。同じくケニー・ドーハムの曲で16小節のブルージーなムードを持ったバラード。出だしはマッコイがテンポを設定せずに自由なイントロを引き始め、その後合奏に入ります。DVD『ブルーノート物語』では、この曲をBGMにしてビート詩人の詩を朗読していて、詩とBGMのムードがぴったりで感動した記憶があります。ジョーのソロも絶品。呑んでいて背景にこの曲が流れていたりすると思わず耳をそばだてます。
3曲目の "Homestretch" はB♭のブルース。作曲はジョー・ヘンダーソン。印象的なマッコイのピアノ・ソロから合奏になりますが、そこは「コルトレーン経験」を経た世代のマッコイやジョーのこと、ビ・バップの場合のブルースとは響きが違ってきています。ケニー・ドーハムだけがバップ丸出しでソロを取っているところも微笑ましい。
4曲目 "Recorda-Me (Remember Me)"もポルトガル語を使っていることから分かるとおり、ボッサのリズムです。ジョーが高校を卒業してすぐに書いた曲であるとライナーに書かれていますが、洗練された曲想に驚かされます。ピート・ラロカも印象的なラテン風のドラミングを叩き出しています。
5曲目の "Jinrikisha" は「人力車」のこと。ただライナーでケニーは「中国の荷車」などと書いていますから、この辺の区別は余りつかないのでしょう。ちなみに英語には "rickshaw"という単語がありますが、これが「人力車」のこと。もちろん由来は「リキシャ」からです。作曲はこれもジョー・ヘンダーソン。曲はマイナーで東洋的というよりも中近東のムードを狙ったような曲想ですが日本のジャズ喫茶などにもぴったりな感じです。2種類のビートが交互に出てきて曲のムードに彩りをつけています。マッコイのソロにはまさしく日本的なものを感じさせるフレーズが多用されていますが、彼は曲名の由来をよく知っていたのかもしれません。
最後の "Out of the Night" は12小節のマイナー・ブルースでジョーの作曲。マイナスワンの練習曲に出てきそうな曲です。ソロはケニーのファンキーなソロから始まり、ジョーの抑えた感じのソロ、マッコイの華麗なソロが繰り広げられます。
ジョー・ヘンダーソン初期の最高傑作です。
Tags: Dorham, Kenny · Henderson, Joe · tenor sax · Tyner, McCoy

比類なき解釈という言葉があります。音楽の文脈で使う場合、クラシックにせよジャズにせよ、ある素材となる曲をこれ以上ない位、聞き手に「ああ、この曲はこうやって演奏する、歌うためにつくられたんだな」と思わせるような演奏を指す言葉です。クラシックには疎いのですが、例えば『第九交響曲』のフルトベングラーなど、いろいろ聴いていてもやっぱり感動が違い、他の演奏を聴く場合には、むしろフルトベングラーの演奏をメートル原器として比較して聴くようなところが、私の場合あります。ジャズもクラシックと同様に「持ち歌」というような概念がないため「何某の演奏がその曲の極めつけである」といった言い方がされ、例えば「バイ・バイ・ブラックバード」はマイルスであるとか、「サマータイム」はパーカーの『ストリングス』である、「ワルツ・フォー・デビー」はエバンスの演奏であるなどと言われています。もっとも、中には百花繚乱、様々な演奏が施され、そのどれもが素晴らしいといったスタンダードもあるわけで、例えば「スターダスト」や「朝日のようにさわやかに」などは十人十色、"Everyman's in his humor"な状態で、どれを1位とするか決められない、決められないからこそ、「スターダスト特集」「ソフトリー特集」などが組まれるわけです。
"Lullaby of Birdland" (「バードランドの子守唄」)の極めつけの名唱といわれるのが、今回紹介する Sarah Vaughan (邦題『サラ・ヴォーン・ウィズ・クリフォード・ブラウン』)です。メンバーは、アルバム・タイトルにもある通り、サラ・ヴォーン(vo)、クリフォード・ブラウン(tp)のほか、ハービー・マン(fl)、ポール・クィニシェット(ts)、ジミー・ジョーンズ(p)、ジョー・ベンジャミン(b)、そしてロイ・へインズ(ds)です。吹き込みは1954年12月18日。
1曲目にして永遠の名作 "Lullaby of Birdland" は、"Love Me, or Leave Me" のコード進行を使ってジョージ・シアリングが作曲した名曲。クリス・コナーが歌って、これが比類なき解釈と思われていたところに、サラの歌が出てきて「こっちが上だ」と思われたと、時系列的な聴き方ができた人は書いています。確かにクリスの歌も悪くないのですが、サラの解釈を聴くと、クリスは表面のキレイゴトに流れている感じが否めない。編成の違いなどもあるのですが、それに留まらないような部分で「勝負がついた」といえるわけです。冒頭のスキャットからして、ただならぬ気配を感じさせます。そして微妙な食い気味で歌に入ります。さびの部分では逆にタメを効かせ、そのままAメロに戻って楽器のソロにつなぎます。先発はピアノ。続いてベースが太い音でソロを聴かせたあと、ロイ・ヘインズのブラシによるソロを経て、ボーカルものとしては信じられないほど素晴らしい、4バースに繋がります。ここでもサラは技巧を極め、徐々にフレージングを複雑に音域を広げて行き、クリフォードとの4バース交換にクライマックスをもって行きます。そしてスキャットの最後の音をつなげつつ、自然な感じでサビからテーマに戻るわけです。わずか4分の芸術ですが非常に濃く、詰まっているものが多い演奏です。
2曲目 "April in Paris" はピアノを伴って1コーラスを歌い上げ。そのままピアノソロ、そしてクィニシェット、クリフォードとソロが続きます。クリフォードの活躍が素晴らしく、ソロといいボーカルへの絡み方といい、もう一人天才歌手が現れたような印象を与える名演に仕上がっています。
3曲目 "He's My Guy" は小唄色も濃厚な曲。サラがさらりと歌ったあと、レスターにクリソツのテナーに続いて登場するクリフォードのソロが素晴らしい。今生きていればもうすぐ喜寿を迎える歳でしょう。そして彼の生き方からすれば、交通事故にさえ遭わなければ、まだまだ元気に活躍していたかもしれません。マイルスだって彼が健在なら、あんなデカイ顔はできなかったはずです。そんなことさえ考えさせる名ソロです。
4曲目の "Jim" は、節をこねくり回すようになる前のサラによる、典型的なバラード歌唱が聴かれます。ここでも、歌が終わって合奏を合図に入ってくるクリフォードのソロが素晴らしく、涙すら誘うような心のこもったソロを取ります。
5曲目は "You Are Not the Kind"。これまた小唄調のさらっとした曲ですが、冒頭のクリフォードが素晴らしいので聴かされます。テナー、フルートについで再びクリフォードの吹くソロがこれまた凄い。そのムード引き継いでサラも歌詞を乗せつつも自由なフレージングでジャズの醍醐味を感じさせます。
6曲目はビリー・ホリデイによる不滅の歌が残っている "Embraceable You"。私が秘かに思っていることですが、サラがビリーの曲に挑むと、どうしても対抗意識のせいかテクに走るような所がある。この歌も、そこまで低く下げて節を捏ねなくてもいいのに、かなり節を捏ねています。ライナーノーツによると、この曲がこの日のラスト・レコーディングで、ホーン奏者に帰ってもらったあとリズム隊だけをバックにじっくり取り組んだということです。
7曲目 "I'm Glad There Is You" は冒頭のカデンツァのようなサラの歌が素晴らしい。曲はジミー・ドーシーがスイート・スタイルでやっていた頃の曲ですが、サラはこの辺のマージナルな曲を一気にジャズの中心に引っ張って歌いきる能力がありますね。ジ・イン・クラウドにしてもブラジル物にしても、晩年までサラが持っていた資質です。
8曲目はドイツのクルト・ワイルが作曲した "September Song"。実にしっとりと歌うサラの後に、クリフォードがダブル・テンポ・フィーリングで優れたソロを取ります。妙なフルート・ソロを挟んで、ジャズ・フィーリング全開で吹くクリフォードのソロを引き継いで出てくるサラの即興的な節回しが素晴らしい。歌詞まで即興的に変えています。
ラスト曲 "It's Crazy" は、ホーン奏者にとってのラスト曲であったため、ジャムセッション風に各楽器がソロを取っていきますが、クリフォードの格の違いが改めて浮き彫りになる感じですね。
寺島さんのフレーズを借りれば、このアルバムには2人の歌手がいます。サラ・ヴォーンとクリフォード・ブラウンです。この2人の「たぐいなき」名唱を聴くことができるのがこのアルバムです。
Tags: Brown, Clifford · Vaughan, Sarah · vocal
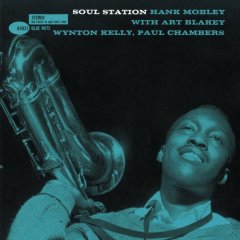
ハンク・モブレーに関しては以前に『ディッピン』の記事で取り上げましたが、アドリブのラインがモゴモゴしているというか、フレーズがピシッと決まらないことがあるわけです。ところがあら不思議、この『ソウル・ステーション』でのワン・ホーンは実に味わい深い。モゴモゴな分、決して乱暴に吹き荒ぶことがないため、フレーズが穏やかにまとまっているわけです。
このアルバムは1960年2月7日のセッション。メンバーはハンク・モブレー(ts)、ウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・ブレイキー(ds)。素晴らしいメンツです。ハンクはブレイキーとはもちろん、ウィントン・ケリーとも相性がいい。というのも、彼のフレージングがバリバリ、パキパキしたものでないため、ウィントンにせよブレイキーにせよ、目一杯バックで仕事をするタイプでないとサウンドが間延びするんですね。特にウィントンはワン・ホーンものだとソロに、コンピングに大活躍しますが、このアルバムにもそのことは当てはまります。
1曲目 "Remember" はスタンダード。このアルバムは1曲目とラスト曲に有名なスタンダードを配し、真ん中の5曲はオリジナルという構成になっています。それにしても、この「リメンバー」はどうでしょう。ビリー・ホリデイのヴァージョンが有名ですが、インストものではまずトップに挙げられる名演です。まずテンポがよく、それがモブレーのフレージングを後押ししています。そしてウィントンのソロがこれまたよくできています。この曲だけでこのアルバムにはまる人は多いはず。
2曲目 "This I Dig of You" はオリジナル曲。テーマのあとはウィントンが先発。これまた素晴らしい。モブレーは途中モコモコし始めますが、ウィントンのピアノが推進力となって演奏を前に進めていきます。ブレイキーのドラミングも素晴らしく、ここではドラム・ソロも取っています。
3曲目の "Dig Dis" もオリジナルですが、ブルースです。冒頭2コーラスのウィントンに続いてモブレー。なかなかファンキーなソロですが、音色が丸く、オーバーブローにもならない(できない?)ので上品なブルースに聴こえます。茫洋たるテナー。再びウィントンがソロを取ってエンディングへ向かいます。
4曲目は "Split Feelin's"。曲名が示しているように、ラテン・ビートの部分と4ビートの部分が交互に出てくる構成の曲です。ソロの先発はモブレー。全編4ビートですが手癖フレーズがたびたび出てきて、「あ、また出た!」と嬉しくなります。ソロの後半でコルトレーンみたいなことをしていますが、ピシッと決まらないところが彼らしい。ウィントンは、全く間然とするところのないソロでびしっと決めています。最後にテナーとドラムの4バースを経て、再びラテン・リズムのテーマが出てきます。
5曲目はタイトル曲の "Soul Station"。16小節のかなりファンキーなナンバー。自作でかつ得意なファンキー・チューンということで、モブレーはレイドバックしてくつろいだソロを展開します。3コーラスそれぞれに違う展開というか狙いを持ったソロで構成力も感じさせます。ウィントンは力強くレイドバックしたソロで、なんだかブルースものをマッタリと弾くときのオスカー・ピーターソンみたいな出だしです。もっとも球を転がすような単音フレーズになると彼の個性がはっきりと出ています。ベースのポール・チェンバースもきっちりワン・コーラスソロを取り、テーマに戻ります。ドナルド・バードの「エイメン」も16小節のファンキー・ナンバーだったと思いますが、それと並び称されるような16ファンキー曲です。
最後は再びスタンダードで "If I Should Lose You"。哀調ある曲想が魅力でパーカーもストリングスで吹いていました。面白いのは、モブレーのソロがまさに「哀愁」を強調したものであるのに対して、ウィントンのソロはここでも元気に跳ねて転がっているところです。
ハンク・モブレー入門としてはぜひ聴いておきたい一枚です。
Tags: Blakey, Art · Kelly, Wynton · Mobley, Hank · tenor sax
October 6th, 2007 · 1 Comment

このブログは "Wordpress" というプログラムを使っています。これはオープン・ソースでダウンロード自由、ただし自己責任でというプログラムなのですが、なかなか使い勝手がいいので "Movable Type" から乗り換えたわけです。乗り換えの理由の一つ、というよりも決定的だったのが、管理画面で "Hello, Dolly" の歌詞が一節ずつ出てくるという仕様でした。正確には仕様というより、標準プラグインにこの "Hello, Dolly" が含まれていて、「ジャズ・ファンとしてここは乗り換えずにはおれまい」とばかりに乗り換えたわけです。今回、その "Wordpress" が大幅にヴァージョン・アップして2.3になったのですが、そのプログラムのコード・ネームが "Dexter Gordon"!どう見てもジャズ・ファンが一枚も二枚も噛んでいるプログラムということが分かります。このブログも2.3にヴァージョンアップしたので、記念(というほど記念すべきことでもないですが)にデク主演の映画、『ラウンド・ミッドナイト』について書こうと思います。
映画『ラウンド・ミッドナイト』。ベルトラン・タベルニエ監督。ジャズ・ピアニストのバド・パウエルとフランス人フランシス・ボードラスとの交流を下敷きにした物語。ピアニストだと絵面にインパクトがないために、主人公はテナー奏者に変更。さらにテナー奏者つながりでレスター・ヤングのキャラクターを付け加えられた主人公デイル・ターナーを演じるのがデクスター・ゴードン。フランシス・ボードラス役はフランソワ・クリューゼ。音楽の総監督で自身もエディー役で出演しているのがハービー・ハンコック。
時代は50年代から60年代にかけて。舞台はパリ。ニューヨークからパリにやってきたジャズの巨人デイル・ターナーがクラブ・ブルーノートで演奏をしていると、土砂降りの雨の中、ずぶ濡れになりながら戸口のところで耳を傾けている男がいる。フランシスだ。イラストレーターだがほとんど仕事にありつけず、クラブに入るお金すらないのだ。何回目かのライブでふとしたことから二人は知り合いになる。しかし、ギャラを直接もらうことすら許されず、お客の置いていったお金を拝借しては勝手に飲んで酔いつぶれ何度も病院に担ぎ込まれるデイルを見てフランシスは決心する。「このテナーの巨人をうちに引き取り、マネージメントをやろう」と。フランシスの献身もあってデイルはギャラを直接受け取っても飲みつぶれるようなことはなくなり、順風満帆の未来が約束されているようだった。しかし、フランシスの田舎に共に帰ったデイルは、ニューヨークに戻ると言い出す。デイルと共にニューヨークへ行ったフランシスは、しかしデイルや他のミュージシャンの周りをうろつく麻薬の売人の姿を見て、「明日パリに帰ろう。空港に来てくれ」と言い残す。しかし当日空港にデイルの姿はなく、フランシスは一人パリに帰る。ある日フランシスのもとに電報が届く。それはデイルの死を告げるものであった。
このようなあらすじで、時代は当然ハードバップ全盛期です。にもかかわらず、ハービーの音楽は今の音楽なんです。途中でゲスト参加するショーターの "Rhythm-A-Ning" のアドリブ・ラインなんて50年代のハード・バップでは決して出てこないようなライン。仮に50年代の音楽の焼き直しだったとしたら、映画的には成功しても音楽的にはつまらない結果になっていたんじゃないかと思います。そして、いまやニュー・スタンダードの地位を確保した名曲 "Chan's Song"。特にニューヨークに戻って出演したクラブでの演奏はとてもよい。フルの演奏ではないんですが、デクのイントロからフレディー・ハバードのテーマにかけてフィーチャーされていてとても美しい。このテイクがサントラ盤にもブルーノート盤にも入っていないのはとても残念です。しかし、使われている1曲1曲が入念な作品であるため、音楽だけでも充分に楽しめる作りになっています。
音楽的な充実感と、聖林映画にはない芸術性の高さでとても素晴らしい映画に仕上がっています。ちなみにブルーノートでの演奏シーンで、最前列で聴いているトラの一人がジャッキー・テラソン。後にデビューしますが、このときは勉強がてらエキストラをやっていたのでしょう。
Tags: Gordon, Dexter · Hancock, Herbie · Shorter, Wayne · tenor sax

『バグス・グルーヴ』と対になっているアルバムが、この Miles Davis & the Modern Jazz Giants です。カタカナ打ちするとあまりにも長くなるので英語で打ちました。こちらは件の「クリスマス・セッション(1954年12月24日)」に加えて、1曲だけ "'Round Midnight" が1956年10月26日のセッションです。メンバーはクリスマス・セッションは例によってマイルス、ミルト・ジャクソン(vib)、モンク(p)、パーシー・ヒース(b)、ケニー・クラーク(ds)、一方56年のセッションはマイルスのほかコルトレーン(ts)、レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)の黄金クインテットによる「マラソン・セッション」の1曲です。
伝説となっている事件が起きたのは、このアルバムの1曲目 "The Man I Love" でのことです。その伝説とは「俺のバックでピアノを弾くな」というマイルスの発言に怒ったモンクが、この曲のソロの途中で弾くのを止めてしまったというもの。しかし、真相は単に音楽的な理由からバッキングを断り、モンクもそうしたというだけだとマイルスは語っています。さらに弾くのを止めてしまった事に関しては、モンクがリハーサルと勘違いしたという説が言われていますが、こちらはどうでしょう?この曲はすでにテイク2で、テイク1は出だしにごたついていたので、これをリハーサルと勘違いするというのは少々強引な解釈だと思います。ただ、モンクの場合『モンクス・ミュージック』でもコルトレーンの番でもないのに、「コルトレーン、コルトレーン!」と叫んで、つられたアート・ブレイキーがとちったりしていますから、勝手に思い込むようなところがあるのかもしれません。それにしても、ミルトのイントロから感動的なマイルスのテーマ吹奏、テンポアップしてミルトの畢生のソロ、テーマを倍に伸ばしたフレーズを弾いた後モンクが弾くのをやめて延々とリズムが刻み続けられる中、マイルスがペットで「弾き続けろ」と吹くやいなや、はじかれたようにモンクが複雑なソロを展開し、その最後のリフを受けてマイルスがソロに入り、オープンからミュートへとサウンドを変えて雰囲気を鮮やかに転回するあたりに、尋常でない緊張感を感じるため喧嘩説に説得力をもたらしているわけです。
2曲目の "Swing Spring" はリズム・チェンジの曲です。普通リズム・チェンジは急速調でアドリブの妙技を自慢する題材になることが多いのですが、ここではテンポを遅めにして、アドリブもメロディーの彩を楽しめる作品になっています。マイルスのソロ、ミルトのソロと続き、マイルスの後ソロでは珍しく "When Lights Are Low" のメロディーを引用したりしています。モンクのソロではBメロのところでビ・バップ初期に聴かれたようなバップバップしたメロディーが出てきて微笑ましい。再びミルトがソロを取りそのままマイルスとユニゾンでテーマを弾いて終わり。
3曲目の "'Round Midnight" は上にも書いたように56年10月26日、マラソン・セッションからのテイクです。例のヴァンプと合奏もあり、コロムビア盤に引けを取らない名演ですが、それもそのはずでコロムビア盤よりも後の録音なのですね。
4曲目 "Bemsha Swing" はモンク(とデンジル・ベスト)の曲で、唯一マイルスのバックでモンクがピアノを弾いているもの。ここでのバッキングは実に丁寧で、マイルスとのインタープレイのようにも聴こえるので、喧嘩状態というのはやはりガセでしょうね。ソロはミルト、そしてモンクと続きマイルスとミルトの4バース・チェンジを経てテーマに戻ります。
5曲目の "The Man I Love" (take 1)は、ミルトのイントロでごたついてやり直し、マイルスのテーマでも、モンクが急に強い音を出してマイルスが引いたようなところがあったりして、なんとなく変な雰囲気です。もっとも、ソロに入るとミルトもモンクもマイルスも素晴らしいソロを取っています。こちらのマイルスはオープンで吹き続ける分平板な印象で、やはりtake 2の緊張感には敵いません。
マイルスがぐったりと椅子に座り込むほど疲れるのは、「ザ・マン・アイ・ラブ」のようなバラードを卵の殻の上を歩くような細心さで演奏した時だといわれます。確かに、このアルバムの1曲目に聴かれるようなマイルスのプレイは、その緊張感と繊細さで耳を傾けずにはいられません。
Tags: Coltrane, John · Davis, Miles · Jackson, Milt · Monk, Thelonious · trumpet
September 29th, 2007 · No Comments
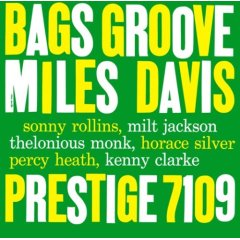
「バグス・グルーヴ」という、シンプルさがとりえの何の変哲もないFのブルースが、今日も明日もどこかのセッションの口開けブルースで演奏され、洛陽の紙価を高めたのはおそらくこのアルバムの演奏によるものでしょう。まあ、「洛陽の紙価を高める」というフレーズを一度は使ってみたくて、敢えてこんなことを言い出したのですが、実際この曲のアドリブで聴かれるマイルスのアドリブこそ、一度はどこかで使ってみたいようなフレーズに溢れています。もしこの演奏なかりせば、「バグス・グルーヴ」はMJQのレパートリーのブルースの一つで終わってしまったでしょう。
アルバム『バグス・グルーヴ』は1954年12月24日のクリスマス・イブに吹き込まれたことから、「マイルスのクリスマス・セッション」と呼ばれる歴史的に有名なセッションが含まれたアルバムで、『マイルス・デイビス・アンド・ザ・モダンジャズ・ジャイアンツ』という長々しく禍々しい名前のアルバムと対になっています。この2枚のアルバムに収められた「クリスマスセッション」が有名な理由は、これが「ケンカ・セッション」であったという口裂け女も真っ青の都市伝説に基づいています。つまり、「俺のバックでピアノを弾くな!」といつもの通り居丈高に言ったマイルスにカチンと来たモンクが、文句を言わずに「ザ・マン・アイ・ラブ」(『モダンジャズ・ジャイアンツ』に収録)で弾くのを止めてしまい、焦ったリズムセクションのざわめきや「早く弾けぇー」と命ずるマイルスのペットが入っているという伝説です。近年、マイルスの自伝が出版されたりしてこれが文字通り「伝説」で事実と違うことは明らかとなりました。しかし、サッチモが歌詞の紙を落としたからスキャットが生まれたという伝説と同じで、これは「喧嘩セッション」のほうが納まりがよいような気がします。モノゴトはこれ「詩と真実」ですから。クリスマス・セッションのメンバーはマイルス(tp)、ミルト・ジャクソン(vib)、セロニアス・モンク(p)、パーシー・ヒース(b)、ケニー・クラーク(ds)です。
都市伝説の視点で言うと、本作『バグス・グルーヴ』の1曲目でタイトル曲の「バグス・グルーヴ」(take 1)は、喧嘩こそ発生していないものの、マイルスとモンクの確執による異常に高いテンションの中生まれたたぐい稀なる名作ということになりますが、その視点を取り去ってもこれは実に深い味のある名作です。まずマイルスと作曲者のミルト・ジャクソン(vib)がユニゾンでテーマを奏でます。その後に出てくるマイルスの抑制されたブルース・プレイ。ラインの狙いというかフレージングは『ウォーキン』に聴くブルース・プレイと同じですが、『ウォーキン』に比べると格段に抑制的で「少ない音符で最大の効果」を発揮するマイルスの特徴が見えはじめています。
続くミルトのソロは、作曲者ということを差し引いても絢爛たるソロで、絢爛過ぎてこれがヴァイブでなく管楽器だったら、かなり粘っこいフレージングになっていることでしょう。クールなヴァイブの音色だからこそ成り立つような、絢爛たるブルースです。
モンクのソロは、ドイツ人批評家ヨアヒム・ベーレンが「歴史上もっとも構成力を持ったソロ」と言ったそうですが、ドイツ人が「構造的だ」などという場合は、たいてい「スイングしていない」の言いかえではないのですかね? 8) 前のフレーズが後のフレーズに論理的に発展していくということなのかも知れませんが、モンクの特色は強く出たソロではあります。
再び出るマイルスのソロがまた素晴らしい。一体何度この演奏を聴き返したことでしょう。マイルスの以前の記事でも書いたと思いますが、マイルスの場合、ソロが一巡してもう一回取るアドリブが凄くよい。抑えたマイルス→絢爛たるミルト→奇妙なモンク、と来て再びソロを取ったマイルスが、短い小節数の中で起承転結を考えた素晴らしいソロを取ります。
2曲目は、同じ「バグス・グルーヴ」のテイク2。1曲目よりも緊張感が欠けているのですが、マイルスのアドリブを聴くと面白いことが分かります。それは、マイルスという人は大きなラインを予め描いておいてそれに沿ってアドリブを展開する人だった。したがって、テイク1も2もアドリブ全体の構成は似通っていて、各部のフレージングにいくらかの違いがあるということです。ミルトのソロはこちらのほうがさらにタメが効いて粘っこくなっていますが、大きなラインは似ています。モンクはテイク1とは全く違ったアプローチで弾いていてストライド・ピアノなども繰り出していて、私としてはこちらのソロのほうが好きです。
3曲目からは54年の6月29日のセッションに変わります。メンバーはモンクがホレス・シルバーになった他、ロリンズが加わります。こちらのセッションも名手ぞろいなので手堅い演奏になっています。"Airegin", "Oleo", "Doxy" はどれもロリンズの曲で、いずれもいわゆるジャズ曲(ジャズ・スタンダード)になって現在でもよく演奏される曲ですが、ここにその原点があります。
5曲目、7曲目に2つのテイクを配するスタンダードの "But Not for Me" はチェット・ベイカーの歌が有名ですが、それぞれテンポを変えて全く違うアプローチをしているところに興味を惹かれます。この曲の解釈としてはどちらも極めつけ。必聴です。
喧嘩セッションという伝説はしょせん都市伝説ですが、このセッションもまた伝説的なセッションということができます。
Tags: Davis, Miles · Jackson, Milt · Monk, Thelonious · Rollins, Sonny · Silver, Horace · trumpet