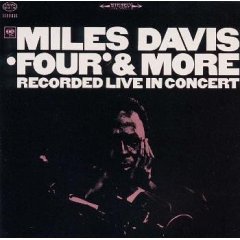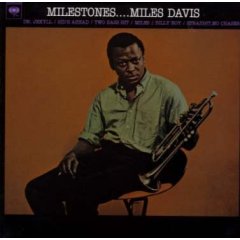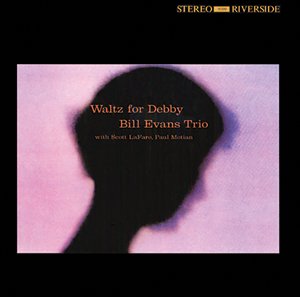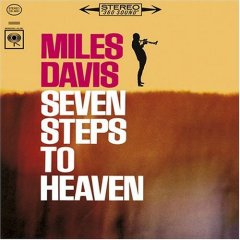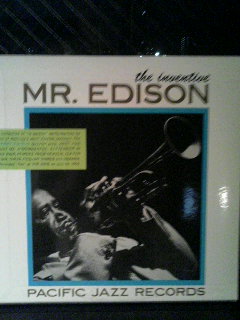September 27th, 2007 · No Comments

セロニアス・モンクの場合、バド・パウエルとは違ってピアノ・トリオの作品は驚くほど少ない。管を入れて分厚いハーモニーを出したほうがモンクの世界をより正確に描けるというのもあるのでしょうが、より大きな理由として、モンクはハーレム・ストライド・ピアニストの流れを汲んでいて、本質的にはソロ・ピアニスト兼作曲家だからだと思います。初期モンクのピアノ・トリオは3枚ほどで、1枚がこの『セロニアス・モンク・トリオ』、もう1枚が、『プレイズ・デューク・エリントン』(Riverside)、残りの1枚が『ザ・ユニーク』(riverside)です。後者2枚がそれぞれ「エリントン集」「スタンダード集」という性格なのにたいして、本作はモンクのオリジナルがメインとなっていて丸々1枚トリオで固めた(1曲ソロ・ピアノがありますが)作品としては最初のものです。
録音は1952年10月と12月セッション、そして1954年9月のセッション。メンバーは52年10月がゲイリー・マップ(b)とアート・ブレイキー(ds)、12月はドラマーがマックス・ローチに代わります。54年のセッションはパーシー・ヒース(b)とブレイキー。しかし、この疎らぶりはどうでしょう?一説には、「モンクはボブ・ワインストック(プレスティッジの社長)に飼い殺しにされていた」と言われていて、仕事が極めて少なかった。さらに、バドの罪をかぶるような形で麻薬所持の罪を着せられ有罪となり、あの悪名高き「キャバレー・カード」を取り上げられたため、クラブへの出演もままならなくなった。そんな時代の演奏なので、一種の開き直りというか、何ものにも媚び諂わず、哄笑すら聴こえてくるような演奏になっていますが、そこがまた魅力でもあります。
1曲目 "Little Rootier Tootie" はモンクのオリジナル曲。それにしても、テーマに聴かれる甲高い音。ホイッスルを模したものだそうですが、一種のシニシズムが感じられるような曲想です。アドリブに入るといきなりモンクの世界。アート・ブレイキーのドラミングはモンクの間を上手く埋めながら音楽を推進させています。2曲目の "Sweet and Lovely" は甘いスタンダードですが、テーマに差し挟む不協和音がその甘さを排除して、モンクの独自性を出しています。ソロに入ってダブルタイムになったあたりで、モンクのルーツであるストライド・ピアノや目くるめくピアノの技法が遺憾なく発揮されます。このピアノを聴いても、まだ「モンクは下手だ」という人がいたら、耳が逆さまについてるんだと思います 😛 続く3曲目 "Bye-Ya" はラテン・リズムを伴ったモンク曲。モンクのプレイに即座に対応するブレイキーが光る1曲です。4曲目 "Monk's Dream" はモンクが見た悪夢を模したと言われていますが、サビのところが面白いメロディーをもった曲です。ここまでの4曲が52年の10月セッション。
5曲目 "Trinkle Tinkle" からは12月のセッションになり、ドラマーがローチになります。曲名から分かるとおりキラキラした感じの曲想を持った複雑なナンバーです。6曲目は "These Foolish Things"。この大スタンダードも、モンクにかかると独自の曲のように聞こえます。7曲目(私のレコードだと、ここからB面)の "Blue Monk" はB♭のブルースで、私がとても好きな曲です。この曲と次の "Just a Gigolo" は54年のセッションにいったん飛び、再び最後の3曲が52年12月のセッションになります。ただ、CDでは曲順がいろいろになっているので注意してください。さて「ブルー・モンク」ですが、ブルースということもあって、マイルスとやったクリスマスセッションの「バグス・グルーヴ」にかなり近い演奏になっています。パーシー・ヒースとブレイキーがそれぞれ素晴らしいソロを取って、テーマに戻ります。この曲のすばらしさは、モンクの特質と同じく伝統的なものと近代的なものが見事に融合している点です。ニューオリンズ・アンサンブルでやっても違和感がないし、バップでやってもちっともおかしくない、そういう優れた特質を持った曲なわけです。「ジャスト・ア・ジゴロ」はソロ・ピアノ。モンクのロマンティックな資質がよく出ています。
9曲目は "Bemsha Swing"、再び52年12月のセッションです。ここではマックス・ローチが積極的にモンクに絡んで行き大活躍しています。最後の曲は "Reflections"。非常に美しい曲でいくつもの名演奏が残っている曲です。
モンク初期の傑作。
Tags: Blakey, Art · Monk, Thelonious · piano · Roach, Max
September 25th, 2007 · No Comments

ブルーノートの名ジャケというと、トップに挙げられるのがこの『ソニー・ロリンズ Vo. 2』です。後にロックのジョー・ジャクソンがこのジャケットをパロディー化したようなアルバムを出して、ジャズに対するアイロニカルなアプローチを試みていることからも、このジャケットの名ジャケ度がわかろうというものです。

CD屋の店先でこのジャケットを目にしたときは笑ってしまいました。
ロリンズのほうはブルーを基調とした色合いで、テナーが中心にどーんと構えて、ベルがこちらを向いています。この迫力がいい。『ブルー・トレイン』も名ジャケですが、あのうつむいた感じが後のコルトレーンを髣髴とさせるのに対して、目を上げてあさってのほうを見つめているこの写真は、やはりロリンズの姿勢というかその音楽を上手く表現しているように思えるわけです。ホントは疲れて飴ちゃんで糖分補給しているコルトレーンと、一服して適当な方を向いているロリンズであったとしてもです。まあ、入れ物についてばかり語っていても仕方がないので中身のほうに行きましょう。
このアルバムは1957年4月14日のセッションを録音したもので、メンバーはロリンズ、J.J.ジョンソン(tb)、ホレス・シルバー(p)、セロニアス・モンク(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・ブレイキー(ds)。ピアノが2人いるのは、モンクが特別参加として彼の曲に参加しているからです。タイトルの「Vol.2」は、前年の12月にブルーノートで吹き込まれたアルバムがあるので第二弾という意味。ブルーノート時代はこの後、『ヴィレッジ・ヴァンガードの夜』(57年)、『ニュークス・タイム』(58年)で終わりを告げ、コンテンポラリーに吹き込んだあと、ロリンズはヨーロッパに楽旅に出かけ、その後『橋』(1962)での復活まで、有名な「雲隠れ」をするのはのちの話。
A面1曲目はロリンズ・オリジナルの "Why Don't I" で、リフを積み重ねるロリンズらしい曲想のナンバー。ロリンズはまさに全盛時代という感じで、ぶっとくて豪快なテナーで自由なソロを取ります。J.Jのソロも彼らしく端正ながらも力強さがあっていい。ピアノはホレス。独特の粘りのあるタッチのピアノです。また、素晴らしいのがソロの後ろで絶妙な表情の色分けをするブレイキーのドラム。そのあと、ドラムと各楽器が4バースをしていきますが、ロリンズが飛び出しをしてしまいます。しかし、前にもどれかの記事で書いたように、こうした失敗は加点法のジャズではカウントされず、それを上回るエネルギーがある場合は全く問題ないわけです。
2曲目 "Wail March" もロリンズ・オリジナル。出だしこそマーチですが、テーマはバップで、しかも急速調。そんなテンポでもサックスのように流麗なソロを取るJ.J.は本当に凄い。ロリンズ、ホレスと素晴らしいソロが続いていきますが、ここでも全体を牽引しているのはブレイキーの熱のこもったドラムです。
3曲目 "Misterioso" は、有名なモンクの曲。6度を基本に飛び上がりながら展開していく3コードのブルースです。テーマが終わって冒頭に出てくるロリンズのソロ。ジャズの魂が感じられる素晴らしい出だしです。モンクとロリンズは相性がよく、バッキングを努めるモンクの上で、他の誰のものでもないロリンズの節を展開しています。この「他の誰でもなく」という修飾語はジャズにおける最大のほめ言葉ですが、その典型がモンクです。モンクが独自のピアノソロを取った後は、J.J.のソロ。ここでバッキングがホレスに代わっている。ダブル・タイムになった後、お決まりのブルース・フレーズが飛び出します。ホレスのソロもモンクに影響を受けたのか、モンク風のフレーズから始まり、徐々に粘っこいブルースになり、ポールのベースソロを経て、ブレイキーとの4バースに入りますが、ロリンズは「草競馬」の一節を引用したりして乗っている。A面のハイライトといえる名演奏でしょう。
B面1曲目もモンクの "Reflections"。J.J.とホレスが抜けます。タイトル通り内省的で美しいラインを持った曲です。このカルテット演奏は、お互い(モンクとロリンズ)の個性を充分に引き出していて、名演と呼ぶことができます。また二人の相性の良さを如実に示している演奏でもあります
2曲目はスタンダードの "You Stepped Out of a Dream"。割と速めのテンポで演奏されます。ソロの順はロリンズ→J.J.→ホレス→ポール。ここでも演奏の推力となっているのがブレイキーの激しくも繊細なドラミングで、ロリンズに対しては最初から攻撃的なシンバルやタムの連打を加え、J.J.に対しては彼が吹き上げ始めるまではハイハットとシンバルレガートで抑え、ホレスにはリムショットでおかずをつけるといった配慮を見せています。4バースを経てテーマに戻り終了。
3曲目もこれまたスタンダードで "Poor Butterfly"。この演奏はとても不思議で、ロリンズははじめと終わりにテーマを崩し気味に吹いているだけなんですね。にもかかわらず、ロリンズの楽想の広さというか深みが感じられるわけです。なんというのか、無理にアドリブを数コーラス取らなくても自分の世界が展開できるロリンズの凄みが表れている演奏だと思います。
ジャケだけでなく、中身も超濃い一枚です。
Tags: Blakey, Art · Johnson, J.J. · Monk, Thelonious · Rollins, Sonny · tenor sax
September 24th, 2007 · No Comments
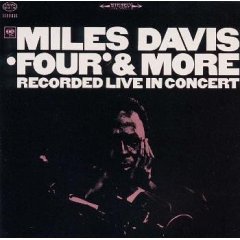
音楽の命はテンポだなと思う時があります。たとえばチャーリー・パーカの「ココ」などを(速吹きできないので)ゆっくり吹いていると、驚くほどクラシカルで優雅な展開だということが分かって首を傾げる。何も無理してあのテンポで吹かなくても充分綺麗なのにと疑問に思うからです。しかし、あのテンポから繰り出される疾走感とか一体感というものがなければ、「ココ」は「ココ」でないし、バドの「インディアナ」も「バドのインディアナ」ではなくなる。テンポと、さらにそこに内在するスピード感によって、狙いとする音楽のテクスチュアリティーが決定してしまうわけです。そういえば『ポピュラー・エリントン』の記事で紹介した、エリントンに対するフランスの批評家アンドレ・オデールによる批判も、要するにエリントンの「コ・コ」(パーカーの「ココ」とは別の曲)のテンポ設定に対する批判でした。クラシック音楽でも、テンポの設定が指揮者ごとの曲に対する解釈の違いを際立たせることがあるように、テンポというものは音楽の本質を握る重要な要素だと思えるわけです。
マイルスのライブ盤『フォア&モア』は1964年2月12日、リンカーン・センターのフィルハーモニック・ホールで行われたライブ録音。メンバーはマイルスのほか、ジョージ・コールマン(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)で、『セヴン・ステップス・トゥー・ヘヴン』の5月セッションに始まるクインテットです。尺の関係で「チョッパヤ」の演奏を選んで編集したものがこの『フォア&モア』、バラード演奏主体に選曲したものが同じコロムビアから出ている『マイ・ファニー・バレンタイン』です。この2枚、どちらがいいかと訊かれれば、まずたいていの人は『フォア&モア』だと答えるぐらいにチョッパヤ曲の高揚感や疾走感は尋常でない。1曲目 "So What" にしても2曲目 "Walkin'" にしてもそれ以前のマイルスによるオリジナル演奏を考えるとまったく別の曲に仕上がっているようで、フシが違うよ、そもそもタイトルが違うよと言いたいほど。「ウォーキン」なんて全然「ウォーキン」じゃないわけです。トニーがとにかく凄い。突っかけ気味に連打することで、演奏自体を前へ前へと押しやっていきます。マイルスは「トニーと演るようになってから、音楽を高域で捉えられるようになった」と『自伝』に書いていますが、たしかにそれまでのような抑制したプレイではなく、高音を連発していきます。またテンポやリズムが自由に変化するのですが、本当に自由だったらしく、「予め決めておいたわけではない」とジョージ・コールマンは述べています。この結果、『カインド・オブ・ブルー』ではまだまだソロ回しに終始していた「ソー・ホワット」などのモード曲が、真の意味で解放され自由なインタープレイを導入することが可能になったわけです。
3曲目の "Joshua" は『セブン・ステップス』でも演奏されたフェルドマンの曲ですが、リズムの変化はますます奔放になり、テンポを自由に動かしながら突き進んでいく演奏に、このグループの実力が表れています。5曲目の "Four" にしても6曲目 "Seven Steps to Heaven" にしても、その疾走感は変わりなく、迫力満点です。
最後の "There Is No Greater Love" だけはスタンダードでテンポもミディアムですが、マイルスの吹き方は以前とは明らかに違って、高域の多用、音の自由な選択、あえて伝統的なフレージングをはずして掻き鳴らすような奏法になっています。ただ唯一変わらないのはトランペットの音色で、『ミュージングス・オブ・マイルス』の "A Gal in Calico" と全く変わっていないことに驚かされます。
完成されたものに安心するのではなく、つねに挑戦し続けるマイルスの姿をよく表したアルバムだと思います。
「あとは全速力で駆け抜けるのみ」 ---ジョン・エフランド
Tags: Davis, Miles · Hancock, Herbie · trumpet · Williams, Tony
September 20th, 2007 · 1 Comment
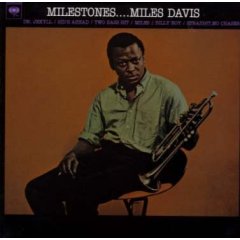
『天国への七つの階段』の記事でも書いたとおり、「マイルストーンズ」という曲の大空に広がっていくような解放感が好きです。アルバム名も文字通り『マイルストーンズ』。「里程標 (mile-stones)」と「マイルスのサウンド (miles-tones)」がかかった、洒落のあるネーミングです。58年の吹き込みで、コルトレーン、キャノンボール、ザ・リズムセクションのセクステット編成。
まずジャケットがよい。ペットをしっかり握って、クッとこちらを睨むように「どうだ!」という目つきで写っているマイルスが素晴らしい。彼が新たな一里塚を踏破した自信と、自らのサウンドを確立した確信が現われています。
1曲目 "Dr. Jekyl" はジャッキー・マクリーンの曲。ハード・バップ期に流行った「ペック」という奏法をモチーフにした曲想です。ペックについては、以前の記事で扱っていますが、鳥が啄ばむ(ペック)ような感じの短いリフの積み重ねのことです。これは意外と保守的な演奏。つまりコードを重視した感じです。ところが2曲目 "Sid's Ahead" になると事情は変わります。「ウォーキン」をぱくったようなマイルス作曲のブルースですが、バップのようなブルース演奏を期待していると驚かされます。私自身最初聴いた時はなんだか分かりませんでしたが、何度も聴くうちに、これは「モード」に対する挑戦なんだと分かってきました。調性感を犠牲にしたために、浮遊したような安定感のない、悪くいえば不安を掻き立てるようなソロが続きます。実際にはまだ「モード」そのものではなく、テンションをわざと入れていくようなアプローチなんです。ここでのバックのピアノはマイルスだと言われています。
3曲目の "Two Base Hit" はディジー・ガレスピーの名曲で、ドラムのフィリー・ジョー・ジョーンズが大活躍しています。そして4曲目、タイトル曲の "Milestones" です。疾走するようなAメロと叙情性すら感じさせるBメロ。先発のキャノンボールは、畢生の名ソロです。続くマイルスのソロも、アルバム裏面の解説にある通り「ビックス・バイダーベック以来、もっとも美しいミュート・ホーン奏者(マイルスのこと)をフィーチャーしている」といえる美しく、はかなさを感じさせる名演。コルトレーンはもう少し行数が長くないとまとまらないかなといった感じです。ピアノのレッド・ガーランドは、まさに彼の限界というべきか、バッキングのつけ方に戸惑っている感じで中途半端です。
このガーランドが「マイルストーンズ」で不完全燃焼の仇を討つ、あるいは憂さを晴らすかのように、ビバップ全開でトリオ演奏をしているのが、5曲目の "Billy Boy"。最後はモンクの名曲 "Straight No Chaser"。ここで、面白いことが分かります。このセッションの途中で、レッド・ガーランドがカンカンに怒って帰ってしまい、そのため2曲目の「シッズ・アヘッド」でマイルスがピアノを弾く羽目になったと『自伝』にありましたが、「ストレイト・ノー・チェイサー」で弾くガーランドのピアノソロの後半は、パーカーの元でやっていた若い頃のマイルスのたどたどしいソロ(『サヴォイ』の「ナウズ・ザ・タイム」)をそのままコピーしたものです。これは嫌味でやったとしか思えません。タッチも乱暴で開き直ったように響きます。1ヶ月前のこの時点ですでに二人のカクシツというかカクチクはあったようです。本当の「喧嘩セッション」は、実はこちらなのです 😛
歴史的名盤『カインド・オブ・ブルー』の直前に聳え立つ名作。比べてみるとずっと不完全ですが、その不完全さとそれゆえの力強さが逆に魅力になる一枚でもあります。
Tags: Adderley, Cannonball · Coltrane, John · Davis, Miles · trumpet
September 18th, 2007 · No Comments
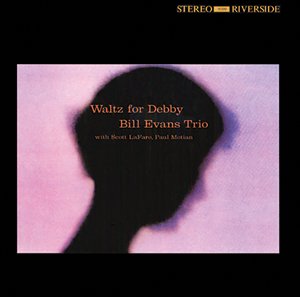
ビル・エバンスの来日公演に出かけました。モダン・ジャズにやっと開眼したばかりだったのですが、家族が新聞を見て「ビル・エバンスという人が来るから、聴きに行きな、お金は自分で工面しな」と無茶振りをしたので、手持ちのお金を遣ってチケットを取り寄せ、またいつも行っているレコード屋で「ビル・エバンスって人の代表作を下さい」とアドバイスを貰って『ポートレイト・イン・ジャズ』を買い、それを何度も聴いて予習をした後、勇んで芝の郵便貯金ホールに出かけました。しかし、残念なことにこの日コンサートは中止になっていました。前日にビル・エバンスが急死したからです。代役も立っていたのですが、払い戻しに応ずるというので払い戻しをしてもらい、後日そのお金を遣って購入したのが、Riverside4部作の一枚である『ワルツ・フォー・デビイ』でした。
打ちのめされました。この世にこんな美しいピアノがあるのかと。冒頭の "My Foolish Heart"。曲そのものを知りませんでしたし、何をやっているのかも正直わかりませんでしたが、果てしなく美しく、そして力強い。2曲目の "Waltz for Debby" がこれまたすごい。イン・テンポに入ってポール・モチアンのドラムがシャーシャーと入ってくるところなんか、今聴いてもトリハダ物です。その頃はまだインタープレイの妙味など分からなかったので、ベースはソロに聞き耳を立てていましたが、これもギターのように旋律性が高くて驚きました。そして何がよいといって、クラブの雰囲気がよく出ているところ。私語が後ろのほうで聞こえています。私も含めてたいていの人は、この2曲で打ちのめされます。
3曲目 "Detour Ahead" はぼんやりとした輪郭のテーマ弾きから始まるので、背後の私語やグラスの触れ合う音がよく聞こえて自分もヴィレッジ・ヴァンガードにいるような気持ちになる演奏です。後半になると徐々に盛り上がっていくところも上手い構成です。
B面の "My Romance", "Some Other Time" もこれまでのムードの延長線上にある名演です。最後の曲、マイルスの "Milestones" はアップ・テンポで演奏され、少しムードの方向は違いますが名演です。寺島さんが『チェット・ベイカー・シングス』は一つの組曲で、「ヴァレンタイン」はいわゆる「サマータイム」だと書いていましたが、『ワルツ・フォー・デビイ』にも全く同じことが当てはまります。全体のムードが統一されて、全部で1曲として聴けるわけです。それもそのはずでこのレコードは、ビル・エバンス、スコット・ラファロ(b)、ポール・モチアン(ds)のトリオによる、マンハッタンのヴィレッジ・ヴァンガードでのライブを編集したもので、ムードの統一を図った編集がなされているわけです。対になる『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』はもう少しバリエーションがあり、スコット・ラファロとのインタープレイにもさらに焦点が当たっています。録音は61年の6月25日。この直後の7月6日、ラファロが急死することで、このジャズ史上最も重要なトリオの一つはその歴史に終止符を打ちます。
後になって分かったことですが、晩年のエバンスはかなりムズカシ的な演奏をしていたようで、あの時実際にコンサートを聴いて初心者の私が理解できたかどうかは不安です。しかし、それでも生エバンスに会えなかったことは今でも残念でなりません。
CDになってからボーナス・トラックが追加されています。このアルバムは名盤過ぎて、CD・アナログともに音質からジャケットまで様々な付加価値をつけた商品が出回っていますが、下のリンクは近く再発される通常盤です。
Tags: Evans, Bill · piano
September 16th, 2007 · No Comments
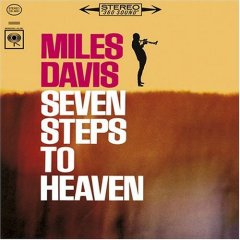
"Seven Steps to Heaven"(「天国への7つの階段」)は、てっきりマイルスの作曲だと思っていたら、ヴィクター・フェルドマンの作曲と知って驚きました。マイルスの曲としては "Milestones" と並んで、心が広々と大空に拡大していくような曲想で、特に気に入っていた曲だからです。確かに、「マイルストーンズ」の時点でモーダルな曲になっているのに対して、「天国への七つの階段」はコーダルな曲で、サビなんか三度も転調しています。ライナーのクレジットだけでなく『自伝』にも「フェルドマンの持ってきた曲」と書かれているので気づいたというわけです。
アルバム『セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン』はこの曲の他、マイルスがスタジオ録音でスタンダード物をやった最後のアルバム、そしてハービー-ロン-+トニーが一堂に会した最初のレコーディングとして有名です。セッションは2つ。63年の4月と5月のもので、4月はロサンゼルス、5月はニューヨークでの録音です。さらにメンバーが違い、4月はヴィクター・フェルドマン(p)、ロン・カーター(b)、フランク・バトラー(ds)、5月はジョージ・コールマン(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)となります。この2つのセッションを交互に並べているのがこのアルバムです。
1曲目の "Basin Street Blues" は4月。サッチモも吹き込んでいる古い曲ですが、ここでの演奏は新しい。カデンツァから始まって、リズムがインテンポになってコーラスに入ってもなかなかメロディーを出さない。小出しにしている。「あれなんだっけ?」と思っているとフェイクされて、煙に巻かれる。中盤(5分を過ぎたあたり)でやっと丸々メロディーが出てきて納得するという仕掛け。このパターン、実はキースがスタンダーズでよくやっているパターンなのですが、元はマイルスだったんですね。フェルドマンのピアノも快適にスイングし、フランク・バトラーの「古めかしさ」と調和しています。現代若手4ビートが古い曲をやるときのお手本にもなっていそうな名演です。
2曲目の "Seven Steps to Heaven" は5月のセッション。上にも書いたように、広々とした曲想の上をマイルス、ジョージ・コールマン、ハービーがソロを取っていきますが、それを支えているトニーのドラミングがすでに凄いことにも驚かされます。45年生まれですからこの時わずか18歳!この曲、フェルドマンの作曲ということで4月のロス・セッションでも吹き込まれたのですが、ボツになり、改めてこのメンバーで吹き込んだそうです。
3曲目の "I Fall in Love to Easily" は、伝統的というかマイルスによるバラード演奏の典型のようなナンバーですが、プレスティッジ時代よりもずっと音の選択が広がっていて、やはり時代の違いを感じさせます。フェルドマンのソロもマイルスのコンセプトに合わせて新しい感じで弾いています。
4曲目 "So Near, So Far" はかなりてこずったらしく、最初4月のロス・セッションで吹き込んでも上手く行かず、5月のNYセッションで吹き込んだうちのリハーサル・テイクの方。本テイクはやはり間違った音だらけで使い物にならなかったということだそうです。確かにドラムに過重な負担を強いるアレンジですが、トニーがこれをこなしていることに驚かされます。
5曲目の "Baby, Won't You Please Come Home" は20年代からビックス・バイダーベックなどが賑々しく演奏してきた曲ですが、マイルスは最初バラードと間違うばかりにテンポを落としてヴァース(もともとあったのか、マイルスがカデンツァ風に付け加えたのか)から吹き始め、その後もマイルスがライブでよくやるようにテンポを動かしながら演奏を続けていきます。
ラスト曲の "Joshua" もフェルドマンの曲ですが、やはり5月のNYセッションでの吹き込みを採用。激しい転調と4/4から3/4へと変化するなど、トリッキーな難曲ですが、全員自然な演奏を繰り広げています。
このアルバムを丹念に聴いていけば、4月から5月へのたった1ヶ月でマイルスのやりたかったことがより明確化していく過程に気づきます。またヴィクター・フェルドマンという有能なミュージシャンが、ツアーの誘いを断ってくれたためにハービーへと繋がり、最強の第2次黄金カルテットに至ることを考えると、不思議な気持ちになるアルバムです。
Tags: Davis, Miles · Hancock, Herbie · trumpet · Williams, Tony
September 16th, 2007 · No Comments

バンドのサウンドをエクスパンドしようと常に努力を続けていたマイルスには、ワン・ホーン物は驚くほど少ない。そのうちの1枚で、全編これワン・ホーンで通したのがここで紹介する『ザ・ミュージングス・オブ・マイルス』です。別名『シャツのマイルス』。マイルスはこのレコーディングの6週間後、ニューポート・ジャズ・フェスティバルの演奏で名声を確立し、コロムビアからのオファーを受け、それがプレスティッジのマラソン・セッション、内緒で吹き込んだ『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』に繋がったことは、関係記事でもろもろ述べてきたとおりです。
このアルバムは1955年6月7日のレコーディング。メンバーはマイルスのほか、レッド・ガーランド(p)、オスカー・ペティフォード(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)で、第一次黄金クインテットの3名が揃っています。ワン・ホーンであるため、マイルスの歌心やトランペティズムが充分に表現されていて、聴いていて楽しくなり強面のマイルスとお近づき出来たような気分になります。
1曲目 "Will You Still Be Mine"。マット・デニスの曲で、トム・アデーア作詞の面白い歌です。「○○(とてもありえないようなこと)があったとしても」というフレーズを積み重ねていき、「それでもあなたは私のものかしら?」と落とす、六難九易のような内容。面白い歌詞なので紹介します。
恋人達が5番街をデートで散策しなくなっても、
この親しみに満ちた世界が終わりを告げても、
それでもあなたは私のものかしら?
タクシーがセントラル・パークの周りを走らなくなっても、
夏の宵闇に窓が明かりを灯さなくなっても、
愛がその秘密の火花を失ってしまっても、
それでもあなたは私のものかしら?
ハドソン川にかかる月がロマンチックでなくなり、
春が若者の空想を掻きたてる事もなく、
グラマーガールがその魅力を失っても、
サイレンが全て誤報になってしまっても、
恋人達が腕を組む気が失せてしまっても、
それでもあなたは私のものかしら?
コニー・ヘインズがトミー・ドーシー楽団で歌ったバージョンでは、さらに「ありえないこと」を追加して楽しい歌に仕上げています。
さてマイルスもまた、この曲のヒューモラスな面を理解して、軽妙に吹き流していきます。バックのオスカー・ペティフォードが、後のポール・チェンバースとは違って圧倒的な音量でゴンゴンと迫ってくるところも面白い。レッド・ガーランドもシングル・トーンで転がるようなソロを取っています。クインテット編成時に、マイルスはアーマッド・ジャマルに出馬を要請していたのですが、シカゴに安定した仕事を持っていたジャマルに断られ、レッド・ガーランドを迎えたそうです。また、ガーランドはボクサー出身であったので、よくマイルスにスパーリングの相手をさせられていたようです。
2曲目 "I See Your Face before Me" は一転バラード演奏。マイルスはものすごいピアニッシモで抑制されたテーマを吹きます。ピアニッシモが甚だしいので、雑音の多いところで聴いたらマイナス・ワンに聴こえるほどです。そのままレッド・ガーランドのカクテル・スタイルのピアノに移り、後テーマを同じくピアニッシモで吹いて終わります。3曲目はマイルス・オリジナルの "I Didn't"。 "So What" にも匹敵するシンプルなタイトルぶりの循環。フィリーが後半の4バースで張り切ります。
4曲目の "A Gal in Calico" は、その魅力的な演奏でしばしばテレビのBGMにも使われているトラックです。しかしここでのマイルスのミュートは凄い。トランペットでもサブトーンというのでしょうか、下のほうで広がっていく音の魅力が一杯です。晩年に世界ツアーで吹いた「タイム・アフター・タイム」でもこのサブトーンが出ていましたが、全く変わらない音色に驚きます。
5曲目の "Night in Tunisia" は有名なジャズ曲。作曲者のディジー・ガレスピー以来、この曲はハイノートを目一杯に突き上げ、「元気があれば何でも出来る」アントニオ猪木状態で吹くのが伝統ですが、マイルスはやはり抑制感をもたせてハイノートを連発するような体育会系の演奏はしていません。一箇所突き上げるところはありますが、それ以外は旋律を大切にした綺麗なソロです。ガーランドはなんだか早々にブロックコードに入っていますね。そしてここでもバックのオスカーが力強くベースをランニングさせています。フィリーのマイルスの4バースを終え、サビからテーマに戻ります。
6曲目 "Green Haze" は再びマイルスのオリジナル曲、といってもブルースです。この曲は最初にレッド・ガーランドがソロを取り、マイルスが二番手です。途中からダブルになりますが、マイルスのストレートなブルース・プレイもなかなか味がありますね。オスカー・ペティフォードもごつい音でソロを取り、マイルスに戻って終了。
じっくり聴けば聴くほど味の出てくるマイルスのワン・ホーンセッションでした。近々再発されるようです。
Tags: Davis, Miles · trumpet
September 14th, 2007 · No Comments

死者を悼む歌をエレジー(elegy)といいます。英語で書かれた3大エレジーと言えば、トマス・グレイの "Elegy Written in a Country Churchyard"(「墓畔の悲歌」), アルフレッド・テニスンの In Memoriam(「イン・メモリアム」), そしてホイットマンの "When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd"(「ライラック・エレジー」)ですが、ジャズの3大エレジーといえばなんでしょう?私が思うには、「ジャンゴ」「クリフォードの思い出」そして「湯の町エレジー」です。まあ、最後のは冗談ですが、この前の授業で英米文学3大エレジーの話をしていて、「ライラック・エレジー」の代わりに「湯の町エレジー」といったらノートに取っている学生がいて慌てました。近江俊郎を知る学生も今はいないんですね。実際には何がふさわしいでしょうか?「バディー・ボールデンの思い出」("I Thought I Heard Buddy Bolden Say")なども味わい深い名曲ですが、前二つほどポピュラーでもないし、取り上げられる機会も少ない。"He Loved Him Madly" もその後頻繁に取り上げられている曲ではないし、"The King Is Gone" にもそれほどのポピュラリティーがあるとは思えないわけです。
むしろ、アルバム一体としては、今日取り上げる『レフト・アローン』がビリー・ホリデイへの追悼盤として著名であり、「レフト・アローン」という曲もしばしば取り上げられるので、3大エレジーの一角に食い込ませてもいいのではないかと思います(って、ジャズ3大エレジー論争なんてないのですが)。ただこの曲は、ビリーへの追悼曲ではなく、ビリーの生前に書かれた曲である点でいまひとつしっくりこない。さらに驚いたことにAmazonのレビューを見ていたら、「レフト・アローン」のセッションもビリー存命中のものだったという記事があって(2曲目以降のトリオ演奏は死後ですが)、このレビュアーが日時を捏造する必然性も全くないのでおそらく本当だとすると、ますますこれがエレジーでいいのかという疑念は強くなります。が、まあいいでしょう。枕なんですから 8)
このアルバムの冒頭1曲目にしてタイトル曲の「レフト・アローン」。とても哀愁たっぷりの魅力的な演奏です。リーダーはマル・ウォルドロンですが、ビリーのパートをアルトで吹くジャッキー・マクリーンが全部持っていってしまいました。『サムシング・エルス』の「枯葉」みたいです。非常に人気の高いアルバムですが、こうも人気が高いと「人の知らないことを知ったかぶりする快感」に支配されがちのジャズファンの中には色々とけちをつける人が出てきます。いわく、「日本人好みの曲想だ」。自分がアメリカ人になったつもりで書いています。いわく、「軟弱マクリーンだ」。フリーでも聴いていてください。いわく、「盤が磨り減る前に飽きる」。SPと違ってLPが磨り減ったの見たことないんですが、針圧間違えていませんか?
2曲目 "Cat Walk" は1曲目の陰に隠れていますがなかなかの名演。特にベースのジュリアン・ユーエルが頑張ってウォーキング・ベースにソロに活躍します。ただA面3曲目以降はあまりピンと来る演奏がなくて残念。でも冒頭2曲の魅力で充分です。
ちなみに、冒頭で述べた3大エレジーのうち、テニスンの『イン・メモリアム』は学友の死を悼んだ詩であり、ホイットマンの「ライラック・エレジー」はリンカーンの死を悼んだエレジーです。
Amazonのユーズドではとんでもない値段をつけているので買う必要はないです。いずれすぐに再発されます。下のリンクは「録音日時の問題」が指摘されているレビューが乗っているので貼りました。
Tags: McLean, Jackie · piano · Waldron, Mal
September 13th, 2007 · No Comments

お上が辞めるそうなので、私も書こうと思っていた記事を引っこめて、今回はフレッチャー・ヘンダーソンの『挫折の研究』について書くことにしましょう
フレッチャー・ヘンダーソン。80年以上も昔にジャズ・オーケストラを組織したジャズ史上の巨人です。そのスタイルは後にベニー・グッドマンが編曲を譲り受け空前のスイングブームを巻き起こしたことからも分かるように、ブラス・セクションと木管セクションによるコール・アンド・レスポンスと、その合間を縫って名人がホットなソロを取るという普遍的なものでした。エリントンが「ワン・アンド・オンリー」で各メンバーの出す音色すら考慮して取替えが利かないまでに練り上げたものであるのに対し、ヘンダーソン(そして編曲者ドン・レッドマン)のスタイルはジャズ・バンドの標準的スタイルとなったわけです。そして人材もルイ・アームストロング、ロイ・エルドリッジ、コールマン・ホーキンス、チュー・ベリー、ベン・ウェブスター、ベニー・カーター、ジミー・ハリソン(ジャズ・トロンボーンの父)、ジョン・カービー、ウォルター・ジョンソン、カイザー・マーシャル、そしてアートブレイキーに至ります。油井先生はこれを「『フレッチャー・ヘンダーソンに雇われたことがある』という経歴は、お役人の『東大卒』の肩書きと同様、ジャズのエリートを象徴した時代があったのだ」と上手く説明しています。
このフレッチャー・ヘンダーソン楽団の歩みを、1923年から1938年までコロムビアに吹き込んだ録音を集大成した4枚組みボックス・セットがこの『挫折の研究(A Study in Frustration)』です。しかしアルバムのタイトルとして『挫折の研究』とはずいぶん縁起が悪い。タイトルをつけたのはジャズ史上最大のプロデューサー、ジョン・ハモンド。タイトルの理由はフレッチャー・ヘンダーソンが最高のメンバーと音楽を擁しながら、挫折を続けてきたことにあります。
全米娯楽の中心地でありながら、純ジャズ的には不毛の地にひとしかったニューヨークで、エセル・ウォーターズの伴奏コンボを率いていたヘンダーソンが、みようみまねでダンス・バンドらしき演奏をおぼえ、名編曲者ドン・レッドマンを得て1923年夏クラブ・アラバムにデビューし、翌24年秋シカゴから招いた天才青年ルイ・アームストロングを通じて、はじめてジャズ・イディオムの真髄にふれ、以後10年間他の追随を許さぬオーケストラに成長し、不況のため挫折。数年間売り食いの生活ののち、ベニー・グッドマンに譲り渡した過去のアレンジが空前の「スイング・ブーム」を巻き起こしたため再起。最高の演奏を続けながらも他のバンドほどに人気を獲得できず再び挫折。ついにフンドシを貸し与えたベニー・グッドマンに拾われるが、眼の手術を受けるために退団。50歳にして振り出しに戻り、今は老女となったエセル・ウォーターズの伴奏者として巡業の旅にのぼった末、中風のためにたおれ、クリスマスの鐘の音をききながら54歳の生涯を閉じる(油井正一『ジャズの歴史物語』)
なぜこれほどの不運と挫折に見舞われたのか。アフリカ系アメリカ人でありながらも、名家の生まれでお坊ちゃん育ちであった彼には次のようなネガティブな面があったと油井先生はまとめています。
1) 数字に弱かった。マネージメントも悪かったが、しばしばタダ働きをした。
2)統率力に欠けていた。メンバーは個性の強い連中が揃っていたから、掌握力のなさが目立った。メンバーの遅刻や無断欠勤が多くなり、これがよく契約キャンセルにつながった。
3)のち「ローズランド」をはじめホール経営者は、ヘンダーソンのリーダーシップに疑念を抱き、契約をしなくなった。
また、1928年の交通事故で鎖骨がポキッと折れて、これが精神力までポキッと折ってしまい、「やる気」がなくなったことも指摘されています。レスター・ヤングとの契約までこぎつけ、入団させたのにも関わらず、メンバーがレスターの進歩性に気づかずにギャーギャー騒ぎ、押し切られる形でレスターを退団させてベン・ウェブスターを後釜に入団させたところなども、リーダーシップ不足の面目躍如です。
ここまで書けば分かると思いますが、お上にそっくりです。ただ一点違うのは、フレッチャー・ヘンダーソンの音楽はど真ん中だった。一流だった。今聴いてもすごいと思えるところです。4枚組み全64曲なので全部は取り扱えないですが何曲かポイントとなる曲をピックアップしましょう。(面倒なので何枚目の何面何曲は書きません)
"Everybody Loves My Baby" はサッチモがはじめて声を吹き込んだ録音だといわれています。 "Sugarfoot Stomp" はビッグ・バンド・スタイルの標準ともなる名アレンジ+名演で、サッチモのソロも際立っています。"The Stampede" はサッチモ退団後の演奏ですが、この時期としては最高の演奏です。"Henderson Stomp" には面白いエピソードがあって、ある日ハンバーガーショップでしょんぼりしているファッツ・ウォーラーを見かけたので、どうしたのかとヘンダーソンが尋ねると「食欲に任せて12皿のハンバーガーを食べてしまったけれど、お金がない。ここの支払いをしてくれたら曲を進呈するよ」。ということで進呈されファッツ自身も客演した2曲のうちの1曲です。"Rocky Mountain Blues" はこのバンドの最高傑作のひとつ。素晴らしい躍動感と整然としたアンサンブルに驚かされます。 "I'm Coming to Virginia" は白人コルネットのビックス・バイダーベックにあこがれて吹き込んだ曲。ペットの担当はジョー・スミスという、これまたビックスに通じるクールなトーンを持ったトランペッター。ちなみに、ジョン・ハモンドはサッチモよりもジョー・スミスが上といっています。 "Singin' the Blues" も同様にビックスの演奏を模範として吹き込まれた演奏。トランペットはボビー・スターク。"King Porter Stomp" は計3回吹き込まれているこのバンドの代名詞的演奏。のちにベニー・グッドマンがバニー・ベリガンをフィーチャーした名演を吹き込んでいます。"Christopher Columbus" は有名なベニー・グッドマンの「シング・シング・シング」中間部に挿入されたことでも知られた曲。ロイ・エルドリッジが、チュー・ベリーが、バスター・ベイリーが不朽のソロを取ります。そして"Stealin' Apple"。チュー・ベリーの代表的ソロが聴ける演奏で、パーカーも好んで聴いていたそうです。
現在CDは廃盤。でも丹念にレコード屋を回れば置いてあるはずです。私も10年ほど前にLPで手に入れました。それまでは油井先生が1曲ずつ解説したラジオ番組のエアチェックテープを聴いていたのですが、ちょっとした手違いで家族に捨てられてしまったことは前に書いたかもしれません。それでこの辺の曲をしっかり記憶しているんです。
Tags: Armstrong, Louis · Berry, Leon Chu · big band · Hawkins, Coleman · Henderson, Fletcher
September 12th, 2007 · No Comments
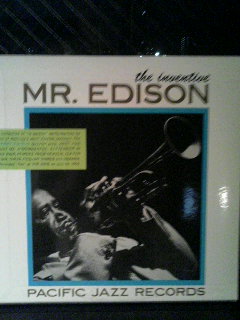
9月に入ってから雨が続きますね。そうです「9月の雨」です。 "September in the Rain"。ジョージ・シアリングは有名ですが面白くない。たまには若い人を取り上げようと思って、ロイ・ハーグローヴの『パブリック・アイ』を探したけれど見つからない。ひょっとしたら、学生に貸したかもしれません。いまから10年前ぐらい、学バンのトランペッター達は口を揃えて「ロイ・ハーグローヴが好きです」と答えていました。そんな一人に貸したのか、とにかく見つからない。おまけに現在では廃盤になっているようです。その代わりというわけではないのですが、ハリー・"スイーツ"・エディソンが「9月の雨」を吹いたアルバムがこれです。
「中間派」という言葉があります。これは純然たる日本発の用語で、発明は大橋巨泉氏といわれています。その内容は、「モダン・ジャズの時代に入ってもスイング・スタイルでやっていた人々のセッションだが、古色蒼然たるスタイルではなくモダンなフレーバーも取り入れたスタイル」というもので、バック・クレイトン、ヴィック・ディッケンソン、バディー・テイト、ルビー・ブラフ、そしてハリー・エディソンなどによるセッションのことを指します。ベイシーアイツが多いのは、もともとベイシー・バンドがモダンに近かったということでしょう。中間派とはミュージシャンやスタイルそのものを指す言葉ではなく、セッションの方向性を指す言葉と考えるといいでしょう。
このアルバムもそんな「中間派セッション」の一つで、西海岸の名門クラブ「ヘイグ」でのライブ録音です。メンバーは"スイーツ"のほか、アーノルド・ロス(p)、ジョー・カムフォート(b)、アルヴィン・ストーラー(ds)で、録音日時は53年の7月1日となっています。
A面1曲目の "September in the Rain" は、中間派の魅力が充分に表れた演奏です。ミディアム・テンポで余裕があるんですね。こういう演奏を聴きながら雨の日に屋内で過ごす気分はまた格別です。2曲目の "S' Wonderful", 3曲目の "Just You, Just Me" も同じくリラックスした演奏で楽しい。4曲目 "Indiana" はバド・パウエルの名演、そして「ドナ・リー」の元歌としても有名ですが、実は1917年作の超古い曲。チョッパヤのテンポでスイーツが張り切ったソロを取ります。「12番街のラグ」のフレーズを引用したり、リフを積み上げていったりと縦横無尽なソロ。続くピアノ・ソロでは、後半まんま「ドナ・リー」のフレーズが出てきて面白い。ドラムとペットの4バースを経てテーマに戻って終わり。古い曲のため逆にモダン風味が強い演奏になっているようです。
B面1曲目の "Pennies from Heaven"は、A面の「インディアナ」とは反対にスイング時代のジャム・セッションなどでもよく取り上げられたのですが、ここでは逆に一番伝統的でスイングスタイルの風味が強い演奏になっています。こういうところが面白い。2曲目はバラードの "These Foolish Things"。スイーツのメロディーと一緒にピアノやベースも自由に間を埋めながら歌っています。アドリブに入ると、かなり自由に崩して、一時「ウィロウ・ウィープ・フォー・ミー」になったり、ブルース・リフを繰り出したりとやりたい放題です。ピアノが半コーラスソロを取った後、サビから再びスイーツに戻して後テーマかと思いきやアドリブのまま吹き続け、コーダはパーカーがよくやるクラシックをもじったフレーズと "If I Had You" をくっつけておどけたエンディングです。3曲目は "Tea for Two"。リフの畳み掛けで盛り上がり、聴衆のものと思われる掛け声まで入っています。それに鼓舞されたのかベイシー楽団の「ティックル・トー」の一節を長々と引用してさらに盛り上がったソロを取ります。その後ピアノがソロを取り、再びスイーツに戻して1コーラスアドリブした後、後テーマをきっちり吹いて終わります。
「9月の雨」だけでなく、中間派セッションの魅力溢れるライブ盤。ジャケ違いですがCD化されていてボーナス・トラックもあるようです。
Tags: Edison, Harry Sweets · trumpet