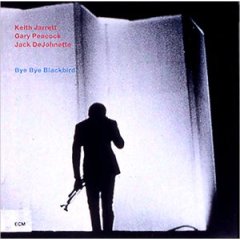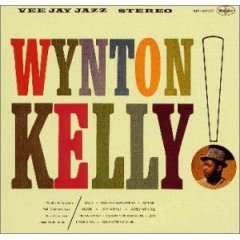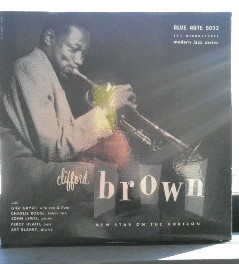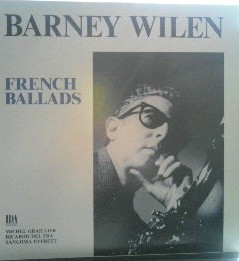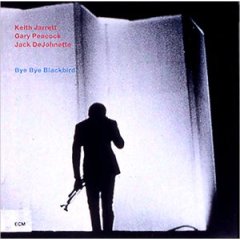
マイルスは1991年8月25日に亡くなりましたが、その後に出された「トリビュート物」の数は計り知れず、中には「マイルス頼み」のバイショウ的感覚が突出しすぎで、却っていやらしいものもあります。マイルスに限らず、こうしたいやらしい「トリビュート」を見せられてきたジャズファンには、私を含めてトリビュート物に懐疑的な気分を持っている人が多いようです。
このアルバムもまたキースによる「マイルス追悼盤」と言うことが出来ますが、しかし、そんないやらしいトリビュート物ではありません。レコーディングは1991年10月12日、マイルスの死の直後といってもいいような日付ですが、直後過ぎて「んじゃ、死ぬ前から準備していたのか?」という疑念さえおきそうです 😛 が、まあ、そんなことはないでしょう、演奏を聴けば分かります。メンバーは、いつもの通りゲイリー・ピーコックのベースに、ジャック・ディジョネットのドラム。
1曲目 "Bye, Bye, Blackbird" はマイルスの十八番で、『ラウンド・ミッドナイト』その他のアルバムに彼の演奏を聴くことができますが、キースにとっても得意曲だったらしく、以前に紹介した『アット・ザ・ディア・ヘッド・イン』でも取り上げています。
2曲目 "You Won't Forget Me" は、シャーリー・ホーンの吹き込みでも有名な曲ですが、実にしみじみした悲しい曲想で、マイルスの死を悼むキースの心情が伝わってきます。特に後半、寺島さんの言う「あれ」がでてきます。「あれ」とはキースのスタンダーズ物で、時折原曲のコードや展開を無視してたたみかけるような、美に淫するような哀愁感漂う即興演奏をおこなう部分のことで、この曲でも悲しげな「あれ」が展開されます。
"Butch and Butch"はオリバー・ネルソン作で、正統派バップの香りも高い曲です。ディジョネットのドラムソロが大きくフィーチャーされています。4曲目の "Summer Nights" はアンダーレイティッドなアルバム『クワイエット・ナイト』からの一曲でしょう。キースのは哀愁あるボッサの名演です。
5曲目 "For Miles" はキース他3人名義なので、即興演奏でしょう。マイルスへ捧げた曲です。最初の展開から「天国への7つの階段」となりそうに聞こえますが、そのままポリリズミックなドラムソロへと展開して、その後ベースラインが「ソー・ホワット」みたいなことをはじめた後、キースがスパニッシュ全開に入ってきます。『スケッチ・オブ・スペイン』への敬意でしょうか。後半はスパニッシュあるいは北アフリカ的ななムードをたたえた「あれ」が10分ほど続きます。むしろこの曲は「あれ」のかたまりといってもいいような哀愁に満ちたトラックで、このアルバム中の白眉だと思います。
6曲目の "Straight No Chaser" はモンクの曲で、マイルスは『マイルストーンズ』で取り上げています。ビバップど真ん中という感じの演奏。
7曲目のスタンダード "I Though about You" もマイルスの十八番で、『いつか王子様が』ほか数枚のアルバムでも取り上げている曲で、明るくも物悲しい美曲&美演に仕上がっています。地味だけれど、耳を傾けるとナミダモノの演奏。
8曲目 "Blackbird, Bye, Bye" も3人名義ですが、"Bye, Bye, Blackbird"を下敷きにした即興的な演奏で明るくこのアルバムを締めくくっています。
Tags: Jarrett, Keith · piano

ハード・バップのど真ん中にある曲は何かと聴かれれば、"Nica's Dream"じゃないかと答えています。この曲、作曲はホレス・シルバー、ハード・バップど真ん中からファンキーあたりまでの屋台骨を支えたピアニストで、ブルーノート後期に「宗教物」といわれる懐疑的なレコードを連発したものの、最近は回帰して普通のジャズを堂々と弾いている人です。
彼の "Nica's Dream" といえば、ブルーノートの『ホレスコープ』が有名ですが、この曲に限って言うと、今回紹介する "The Jazz Messengers" の演奏が非常に優れています。録音は1956年(モダンジャズの当たり年です)の4月と5月。メンバーはリーダーのアート・ブレイキー(ds)他、ドナルド・バード(tp)、ハンク・モブレー(ts)、ホレス・シルバー(p)、ダグ・ワトキンス(b)です。この後、ホレスがバードやモブレーを引き連れて独立してしまい、残されたブレーキーはその後ピアノと作曲にボビー・ティモンズを迎え、リー・モーガン(tp)、ベニー・ゴルソン(ts+作曲)をメンバーに、歴史的なアルバム『モーニン』を吹き込んだことを思えば、大人の事情とはいえ歴史の偶然と不思議さに思いをいたします。
1曲目 "Infra-Rae" はハンク・モブレーの曲で急速調とマイナーな曲想が魅力のハード・バップらしい曲。ソロの先発はバード。情熱的なソロが魅力です。続いて三連も豊かなホレスらしいピアノソロ。そして作曲者モブレーのわりとすばしこいソロが続きます。モブレーはパーカーがよく繰り出すフレーズをところどころ引用したりして乗りに乗っています。最後にアンサンブルとブレイキーの4バースを経てブレイキーのドラムソロ。特に後半はドラム・ソロのショーケースになっています。
そして2曲目にして、永遠の名曲 "Nica's Dream"。ここでのバージョンは情熱的なホレスのバッキングにサポートされてモブレーが先発。これが実に味のあるソロ。曲を吹いているというより、何かを語りかけられているような気にさせられる名ソロです。続くバードのソロはクリフォード直系のクルクルと回転するフレージングを基調とした華やかなものです。クリフォードほど上昇下降を展開しませんが、それが彼の個性です。バードの後に出てくるホレスのソロ。冒頭の音を聴いて御覧なさい。どれほど彼がこの曲にかけているか聞こえてきます。そして、時を同じくしてブレーキーが細やかに奏法を変えてきます。これほどお互いの音を聴き合えていたのに・・・ホレスのソロを経て、アンサンブル?ショートソロの展開となり、曲に戻ります。実に名演。マイナー、ラテン・フレーバー、「マイルス・ロリンズ・コルトレーン」抜き、2管。これぞハード・バップのイデアではないかと思われる演奏です。
3曲目の "It's You or No One" はスタンダード曲。バップ風にアレンジされています。全員が快調にソロを飛ばします。4曲目 "Ecaroh"も優れたハード・バップ曲で、ネーミングはHoraceのアナグラム。メジャーキーですが、不思議と各人のソロがくすんでいるところがやはりハード・バップらしい。5曲目"Carol's Interlude" はモブレー作曲のマイナー曲。これなんかも実にこの時期らしいし、ブレイキーも煽りに煽っているんですよね。 "The End of a Love Affair" はスタンダードですがテーマはラテンリズムで演奏されています。この曲はハービーさんとチャカ・カーンも演奏していて、本当にエバーグリーンな名曲だと思います。
最後はモブレー作曲の、その名も "Hank's Symphony"。チャイナな感じでブレイキーもシンバルを銅鑼に見立てて叩くイントロから急速調なテーマになだれ込みます。テーマ終了後ブレイキーのかなり長いドラムソロが全面にフィーチャーされ、管はアンサンブルを中心とした裏方に徹しています。
下のCDではなんと5曲もプラスされていますが、再発の端境期で妙に高い中古にリンクしています。いま急いで買う必要はありません。いずれ再発されます。
Tags: Blakey, Art · Byrd, Donald · drums · Mobley, Hank · Silver, Horace
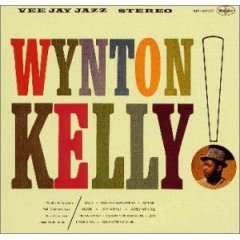
ウィントン・ケリーがマイ・ベスト・フェイバリット・ピアニストであることは以前の記事にも書きましたが、その中でも最も優れているのが『ケリー・アット・ミッドナイト』であるのに対して大衆的な魅力は『ウィントン・ケリー(邦題『枯葉』)』にあると書きました。たしかに『ケリー・ブルー』という、より人口に膾炙されている名作もあるにはあるのですが、あのタイトル曲「ケリー・ブルー」は時代がついている。一方、この『枯葉』に聴かれるようなピアノソロは今でも十分通用するし、今でもこれほどスイングしているピアノはなかなか聴かれないのが事実です。
このアルバム、メンバーはウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、サム・ジョーンズ(b)、ジミー・コブ(ds)です。
1曲目の "Come Rain or Come Shine"。ビル・エバンスの演奏が実にシンネリ・ムッツリしているのに対して、ケリーのそれは実に跳ね回って楽しそうです。邦題「降っても晴れても」という割りに晴れが続いているようです(エバンスは雨続きのようですが)。2曲目はバラード "Make the Man Love Me"。歌伴の得意なウィントンですが、歌に丁寧なコンピングを施しているような名演になっています。
そして、タイトル曲の「枯葉」。これ、普通に使うコードとは若干違う解釈をしているんですよね、Bメロの部分が。まあ、それにしてもビル・エバンスとは別の行きかたを取りながら、これはこれでやはり潤みや哀愁のある名演に仕上がっています。
続く "Surrey with the Fringe on Top" (「飾りのついた4輪馬車」)も軽快なテンポながらも、イントロなんかエバンス風で笑います。やっぱり意識していたんでしょうね。しかし、アドリブに入ると、これはもうウィントンとしか言いようのない、個性全開のスイングするピアノに変わるところがまたよい。
5曲目 "Jone's Avenue"、6曲目 "Sassy"は共にケリーのオリジナル。後者はサラ・ヴォーンの愛称で、彼女に捧げられた曲だそうです。どちらも、オリジナルということもあって『ケリー・アット・ミッドナイト』に収められていそうな「乗りのよい」曲想です。
"Love I've Found You"はバラードで、しみじみとした曲想の中に左手の力と右手のつけるおかずも綺麗で、ケリーの絶頂期が捉えられています。バド派なんだけれど、バドのようにメランコリックではないケリーの魅力全開のトラックだと思います。続く "Gone with the Wind" はジミー・コブのドラムの妙技も聴けるスタンダード。ウィントン以上に歌っているドラムが魅力です。4バースにも聴かれますが、それ以前にウィントンのアドリブの背後に聴かれるドラムが魅力を振りまいています。
最後の曲 "Char's Blues" は冒頭にミキサー室の声が入ったあと、軽快なブルースが始まります。ウィントンらしく華麗なピアノソロに続いて、サム・ジョーンズのベースソロも聴くことができます。
ウィントン・ケリーの絶頂期を捉えたジャズ・ピアノファン必携の一枚です。
Tags: Kelly, Wynton · piano

昨年12月にオスカー・ピーターソンが亡くなりました。彼はライオネル・ハンプトン、ベニー・カーターと並んで、決して亡くなることはないジャズマンと思っていたのでびっくりしました。もっとも82歳ということで、あの巨躯を支えて来たことを考え合わせれば、大往生といえるのではないでしょうか。オスカーPの作品は枚数も多いので、今回は特に私の好きな1枚を紹介します。
この The Way I Really Play(邦題『オスカー・ピーターソンの世界』)はMPS (Music Productions of Stuttgart) 時代の最高傑作として評判の高いアルバム。さらに、このレーベルは音がよいので、ピーターソンのテクニックが余すところなく捉えられているといわれています。録音は1968年4月、ドイツ、フィリンゲン。ハンス・ゲオルク・ブルナーシュワー・プライベート・スタジオというドイツらしく長い名前のスタジオ録音ですが、スタジオ・コンサート風にリスナーが入っていて拍手などが聴こえます。メンバーはピーターソンのほか、サム・ジョーンズ(b)、ボビー・ダーハム(ds)のピアノ・トリオ編成。
1曲目 "Waltzing Is Hip" はタイトルどおり3拍子の曲ですが、ピアノのレンジをフルに使ったダイナミックで乗りに乗った演奏と、それをしっかりと捉えた録音に驚きます。このガンガンに飛ばす高テンションの1曲目から、実にリラックスしたムードの2曲目 "Satin Doll" へと繋がるところが特に好きで、何度もテープを逆戻しして聴いたものです。
実はこのアルバム、中学生の頃に近所のレンタル・レコード店で借りてテープにダビングして、そのテープを長い間聴いていました。思い返すと、当時はレコードをレンタルしていたんですね。CDとは比べ物にならないほど繊細な扱いを要求するレコードで、こちらも出来るだけ傷をつけないように「お借り」して、家に帰るとすぐにテープにダビングして、再び仕舞い、翌日返しに行ったわけです。とはいえ、私がレンタルで済ましたジャズ・レコードはこれぐらいしか覚えていないので、ジャズ・コーナーはあまり充実していなかったんじゃないかと思います。当時猖獗をきわめていたフュージョンなら割とあったのかもしれませんが、今と違い不寛容だった当時は見向きもしなかったので覚えていません 😀
その「サテン・ドール」が、リラックスしたムードで実によい。10分近い演奏なんですが全く飽きさせることなく、ピアノを目一杯に使ったフルレンジのオーケストラルな演奏から単音でシンプルに展開するソロ、可憐な音使いで小さく花を咲かせたと思えばブルージーにやくざな音を多用してみたりと、自在にピアノをコントロールしています。「この時間がこのまま続いてくれれば」と思わせる素晴らしい演奏です。ただし、キース・ジャレット顔負けの唸り声が入っています 8)
3曲目は "Love Is Here to Stay" 。ライナー・ノーツでいソノてルヲさんが「アート・テイタム風のイントロ」と書いていますが、全くその通りで華麗に球を転がしています。リズムが入ってくるとミディアム・テンポになりテーマを終えた後のアドリブは、これまたジャズ・ピアノのショーケース。「サテン・ドール」ほど長くありませんが、よくまとまった作品です。4曲目の "Sandy's Blues" はピーターソンのオリジナル。「サンディー」とはサンドラ夫人のこと。タイトルどおりのブルースで、リラックス・ムードが横溢しています。途中からテンポアップしてブギ、速弾き、コード弾きと様々な技巧を駆使してエリントンが呼んだように「鍵盤の大王」の貫禄を見せつけ、再びテンポを落としてブルースになります。この辺の緩急のつけ方も心憎い1曲。
5曲目はディズニー映画の名曲 "Alice in Wonderland"。1曲目と同じくワルツです。ビル・エバンスもこの曲で名演を残していますが、聴き比べればジャズ・ピアノ2大スターの個性の違いがよく分かるでしょう。ラスト・ナンバーは再びOPオリジナルで "Noreen's Nocturne"。ノクターンとは名ばかりで、夜にかけたら目が覚めてしまうほど景気のいい曲。サム・ジョーンズがギリギリとベースを掻き鳴らし、ボビー・ダーハムが太鼓を連打して演奏を盛り上げています。
私も現在はテープでなくCDでこれを楽しんでいます。
Tags: Peterson, Oscar · piano

ハービー・ハンコックのライフワークの1系統として、ティンパン・アレイや40?50年代ジャズ曲からの脱却というか、新しいスタンダード(ニュー・スタンダーズ)の追求というのがあるような気がします。これはハービーさんの師匠マイルスが推し進めていたもので、特に『ユア・アンダー・アレスト』にその姿勢が集約されていますが、従来のスタンダードではなく、かといってオリジナル曲でもない、ニュー・スタンダードを創出しようという流れをハービーさんが受け継いでいるような印象です。
今回紹介する『ポッシビリティーズ』も、このニュー・スタンダード系統のアルバムです。各曲にそれぞれゲストをフィーチャーして従来のスタンダードとは一味違った曲を取り上げ、その「可能性」を追求しているわけです。
1曲目 "Stitched Up" でフィーチャされるのが、ブルース歌手のジョン・メイヤー。こてこてのブルースではなく、白人のソフィスティケーションが入った聴きやすいブルース。歌が終わった後に出てくるハービーさんのソロはしつこい畳みかけでブルース・フィーリングがあふれるモノ。そのままフェードアウトします。2曲目の "Safiatou" のゲストは、ギターのカルロス・サンタナとペナン出身の歌手アンジェリーク・キジョーです。サンタナの南米的な情熱あふれるギターとメランコリックな声のキジョーとの掛け合いで歌が進み、ハービーのソロも二人のムードを引き継いだメランコリックなものになっています。
3曲目の "A Song for You" はレオン・ラッセルの名曲で、カーペンターズやカーメン・マクレエの名演が残っています。ここでのゲストは美人で、昨年は妊婦ヌードで世間を騒がせたクリスティーナ・アギレラ、しかし上手い歌手ですね。このアルバム中のベスト・トラックといってもいいような歌ですが、こう感じるのは私がとりわけこの曲を好きだからかもしれません。4曲目はポール・サイモンの曲で "I Do It for Your Love"、ゲストもポールです。元の歌を知りませんが、思いっきりジャズになっていて、歌+伴奏ではなくポールもヴォーカル・セクションを受け持っているといった感じです。
5曲目の "Hush, Hush, Hush" は黒人霊歌かと思ったら、ポーラー・コールという人の曲。歌はアニー・レノックス、スコットランド出身の歌手だそうです。そして6曲目、ニュー・スタンダード物の常連さん、21世紀のガーシュウィンかコール・ポーターかといった風情のスティングが登場します。曲は "Sister Moon"。カサンドラ・ウィルソンみたいな声で歌っています 😉 この人はもともとジャズとの親和性が高いので、当たり前といえばあたりまえですが、ジャズとして素晴らしいトラックになっています。
7曲目はブルースのジョニー・ラングとイギリスのジョス・ストーンがゲストで、 "When Love Comes to Town"、U2の曲だそうですが、ベタのブルースですね。後半どんどん盛り上がっていき、ハービーさんのソロでクライマックスに達します。8曲目はビリー・ホリデイの名曲 "Don't Explain"。フィーチャーされているのはアイルランドのダミアン・ライスとリサ・ハニガン。なんか辛気臭い演奏です 😥
9曲目はスティーヴィー・ワンダーの名曲 "I Just Called to Say I Love You"。ゲストはラウル・ミドン。盲目の歌手だそうです。そしてハーモニカでスティービーご本人も参加しています。しかし、この歌手、素晴らしい声です。スティービーのハーモニカも優しく美しい曲に仕上がっています。最後は "Gelo na Montanha - 第一楽章"。作曲とゲストはフィッシュのメンバートレイ・アナスタシオ。エコロジカルな音楽みたいです。
個人的な好みでは、1、2、3、4、6、7曲目のようなコクのあるトラックが気に入りました。
Tags: Hancock, Herbie · piano

今から10年ほど前、東芝EMIでは "24bit by RVG" と銘打って、ブルーノートの名盤を名録音エンジニア、ルディー・ヴァン・ゲルダー(RVG) によるリマスタリングでCD化し、紙ジャケット仕様で発売していました。と言うより、もう10年も前になるんですね。ライナーの裏に第1弾発売が1998年7月となっているのを見て改めて気づきました。なんだかつい最近の出来事だったような気がしていたんです。昨年からプラケース仕様ではあるけれど、再びRVGリマスタリングが再発されています。
このリマスタリング・シリーズでも、ヴァン・ゲルダー本人が会心の出来であると語っているのが、今日紹介する『ミッドナイト・ブルー』です。録音は1963年1月7日。リーダーはケニー・バレル(g)で、他にスタンリー・タレンタイン(ts)、メジャー・ホリーJr.(b)、ビル・イングリッシュ(ds)、レイ・パレット(conga)という60年代ブルーノートの色彩が濃いメンバーです。
1曲目の "Chittlins Con Carne" はケニー・バレルのオリジナル曲で、このアルバムの顔とも言うべき曲です。最近「大和証券」のCMに使われましたが、イントロが長いので30秒CMでもほとんどがイントロに費やされ、テーマが出て来るのはCMの終わりぐらいということになり、それが却ってこのCMを印象的なものにしています。曲として聴く分にはそんなに長く感じるイントロではないのですが、CMの時間枠の中では長く感じるものなんですね。しかし名曲です。2曲目の "Mule" はブルース。ゆったりとしたスローブルースで黒々としたフィーリングが横溢しています。スタンレーが名ソロ。3曲目の "Soul Lament" はバレル・オリジナルのバラードで、ソロ・ギター。バレルの特色がよく分かる演奏に仕上がっています。4曲目でタイトル曲の "Midnight Blue"、5曲目の "Wavy Gravy"もバレル作曲のブルース。6曲目の "Gee Baby" は一応スタンダードですが、これもブルースの雰囲気を持った曲です。最後の曲 "Saturday Night Blues" も当然ブルース。スローなシャッフルのリズムに乗って各人がレイドバックしたソロを取ってゆきます。
いつもならば1曲ずつソロ・オーダーを書いたり、寸評を加えたりするのですが、このアルバムに関してはそういうことが余計に思える。と言うのも、このアルバムは全体で一つの曲、つまり『ミッドナイト・ブルー』という曲であり、一つ一つのナンバーはその楽章という感じがするからです。それほどまでにカラーがブルース一色に統一されたアルバムです。この頃から、いわゆるグルーヴ物と呼ばれるもう少し饐えた感じの退廃したアルバムが出てくるわけですが、この作品は饐える直前の熟成感が堪えられない名盤だと思います。
Tags: Burrell, Kenny · guitar
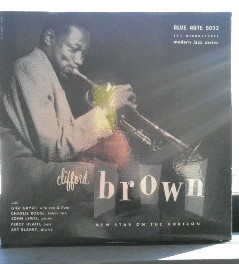
日記ブログのほうで『美味しんぼ』の記事を書きましたが、その際10インチ盤について言及しました。レコードのLPにはサイズで12インチ(30cm)と10インチ(25cm)があり、初期のジャズLPには、よくこの10インチ盤が用いられていました。しかし12インチに比べると、当然ながら収録時間が短く、アドリブの発達とそれに伴う収録時間の延長化によって12インチが主流になっていったわけです。
この10インチオリジナルは、おそらくコレクターという人々からすると垂涎の的なのでしょうが、私はそれほど興味がありませんでした。しかし、数年前東芝EMIからブルーノート(そして後にはベツレヘムなど他レーベル)の10インチが復刻されたことがあり、その際にできるだけ持っているCDやレコードと重複しないように集めたことがあります。今回紹介する『クリフォード・ブラウン―ニュー・スター・オン・ザ・ホライズン』もそのときに買った一枚です。しかし、これはBNのクリフォード関係をまとめた名盤『クリフォード・ブラウン・メモリアル・アルバム』と重複しまくり、というか全曲が納まっています。この10インチ復刻は完全予約制で、私もカタログを見ながら被らないように被らないように注文し、その時点ではこのアルバムを当然除外していました。それで当日品物を取りに行くと、いろいろよくしてくれていた店員さんが「私は『クリフォード』を一枚買いましたよ」といって見せてくれたわけです。実物を見ると、しかしなんとも欲しくなるもので「やっぱり僕も注文しておけばよかった」と言うと、「お譲りしますよ」とのこと。そのまま買って帰ったというわけです。
録音は1953年8月28日。メンバーはクリフォード・ブラウン(tp)、ジジ・グライス(as, fl)、チャーリー・ラウズ(ts)、ジョン・ルイス(p)、パーシー・ヒース(b)、アート・ブレイキー(ds)のセクステット編成。
A面1曲目は "Cherokee"。"All the Things You Are" や "How High the Moon" と並ぶバップの聖典です。曲の最初と終わりにアレンジがありますが、あとはクリフォードのソロ。1コーラス目はジョン・ルイスのピアノが弾くチェロキーのメロディーの上空でブラウニーのペットがアドリブを炸裂させます。後にブラウン?ローチ双頭クインテットで絶世の名演を繰り広げるこの曲は、その演奏の冒頭でハロルド・ランドとブラウニーが互いに半コーラスずつメロディーとアドリブを対位法的に吹き分けています。その原型は実にここにあるわけですね。1コーラス目のサビに入ったところはパーカーの影響がもろに出ています。2コーラス目。ピアノがコンピングに変わり、より自由に飛翔するブラウニーが聞けます。2曲目の "Easy Living" がこれまた名演。ちょうどストリングスのようにアレンジされたバックを従えて、素晴らしいバラード演奏を繰り広げています。途中ダブルテンポになるところでナミダモノのフレーズが出ます。3曲目は クインシー・ジョーンズの "Wail Bait"。ラテンリズムのイントロに続いて整然としたアレンジのテーマが演奏されます。ソロの先発はジョン・ルイス。続いてジジのアルト。再びテーマが繰り返されたあと、満を持してブラウニーの輝かしいソロが炸裂します。次がラウズのテナーですが、やはりブラウニーには誰もかなわない。
B面1曲目はクリフォードのオリジナルで "Minor Mood"。イントロは冒頭がメジャーなのにマイナーになっていく不思議な曲想。テーマは『クールの誕生』の "Jeru"に似たようなメロディーで、ちょっとトリスターノ楽派の風味も入っています。そのせいかブラウンのソロも長く起伏に富んだホリゾンタルなライン。続くジジ、ラウズのサックスもそうで、なんだかリー・コニッツのセッションを聴いているような感じがします。2曲目の "Hymn of the Orient" はジジ・グライスの曲。哀愁のあるテーマです。ブラウニーが先発。曲の哀感を保ったまま目くるめくソロを展開します。ラウズとジジは半コーラスずつソロを取り、ピアノのジョン・ルイスが美しいソロを取ります。ドラムと各楽器との4バースを経て後テーマになだれ込みます。3曲目の "Brownie Eyes" はタイトル通りクリフォードのペットを全面にフィーチャーしたクインシーのバラード。A面の「イージー・リビング」と対になるような名バラードです。
最近このジャケット・デザインで『メモリアル・アルバム』が再発されたようです。しかも別テイクを含めると計18曲、3倍も入っています。『メモリアル・アルバム』は従来のジャケット写真のほうがよいような気もしますがRVGリマスターということで、音質も楽しみです。
Tags: Blakey, Art · Brown, Clifford · Lewis, John · trumpet

授業でハービー・ハンコックの音楽を聴かせました。「カンタロープ」。何人かは反応していましたが、中には狐につままれたような顔して聴いている学生もいて、やはり歌がないとポイントを絞って聴けない人もいることに改めて気づいたわけです。「歌入りでハービーさんのCDというと去年の『ポッシビリティーズ』かな」などと考えながら、授業終わりに「はり猫」へ行くとかかっていたのがこのアルバム。聴いていると、ショーターやティナ・ターナーも参加している。マスターに訊くと「つい最近出たアルバムですよ」とのこと。早速アマゾンで注文して取り寄せました。
アルバム・コンセプトはジョニ・ミッチェル曲集です。この女性はカナダ出身のロック歌手で、私達ジャズファンからするとロック畑の人が作ったということで話題になった『ミンガス』というアルバムと、ジャコ・パストリアスの恋人ということで記憶している人が多いかもしれません。
メンバーはハービーさんの他、ウェイン・ショーター(ts,ss)、デイブ・ホランド(b)、ヴィニー・カリウタ(ds)、リオーネル・ルエケ(g)。また、各曲にそれぞれ歌手がついて歌っているところは『ポッシビリティーズ』と似た構成となっています。
1曲目はジョニの名作 "Court and Spark"、歌はノラ・ジョーンズです。抑制感のあるハービーのイントロから、いわゆる「おしゃれなリズム」になってノラのけだるい歌声が入ってきます。中間で聴かれるショーターのソプラノは典型的なもの。もっとも、ショーターは常に個性満開なので、どんなことがあってもケニーGと間違われるようなことはないのですけれどね 8) ハービーさんのソロは、かなり前衛的です。
2曲目はブルース的な "Edith and the Kingpin" で、歌うのはティナ・ターナーです。イントロは「チャンズ・ソング」みたいです。ここでのティナは "We Are the World" の男みたいな声や "What's Love Got to Do It?" に聴かれる迫力はあるけれどくぐもったような声に比べると、ずいぶん伸びています。タバコをやめたのでしょうか?ショーターはテナーを吹いています。
3曲目は歌なしで "Both Sides Now"。ハービーのピアノとショーターのテナーによるインタープレイが全面的にフィーチャーされています。
4曲目でタイトル・チューンの "River" はコリーヌ・ベイリー・メイの歌。彼女の事をネット調べると、キャッチフレーズが「ソウルフルでオーガニックな歌手」…「オーガニックな歌手」って何でしょ?野菜かっつうの!おそらく「ナチュラル」とか「健康的」という意味であることは推測できますが、つくづくですね。ちょっと鼻にかかったようなかわいらしい声で呟くような歌い方は魅力的です。
5曲目は再びインストに戻って "Sweet Bird"。これもジョニの曲。私は歌なし万事OKなので、アルバム全体ではこの曲が一番好きです。ショーターのテナーもじっくり鑑賞できるし、どこへ行くのか分からないような自由すぎるソロでありながらも、歌い上げるところはきっちり歌い上げる構成力を持ったショーターのソロが堪能できます。背景で宇宙的なイメージの高音を出しているのはギターのルエケでしょうか?効果的です。
6曲目の "Tea Leaf Prophecy" では、満を持して Joni Mitchell 本人が登場します。ブルース的に延々と繰り返して反戦が謳われる歌詞を、彼女が説得力ある声で歌っていきます。カーメン・マクレエのように分かりやすいディクションです。
7曲目。ここで唐突にエリントンの "Solitude" が来ます。名曲で好きな曲だけに、ハービーさん流に解体されているのが却って残念です。
8曲目 "Amelia" を歌うのは、ボサノヴァ歌手のルシアーナ・スーザ。ボッサ風のかろみのある声で歌い流していきます。逃避行の歌ですかね。
9曲目の "Nefertiti" は言わずと知れたショーターの名曲。マイルスのアルバムでは、フロントが延々同じメロディーを刻んで、リズムのほうが逆にアドリブをしていくという変わった構成でしたが、ここでもショーターはかなり解体しつつもテーマに拘泥し、ピアノを始めリズム隊がインプロヴァイズしています。ただ、ショーター本人がテーマからついつい逸脱するので、ときおり集団即興演奏になりギターがサポートしてます。
ラスト・ナンバーの "The Jungle Line" は再びジョニの曲で、詩を朗読するのはカナダの異色シンガーソングライター、レナード・コーエン。60年代の前衛芸術家達の試みみたいな感じで、「随分ゲージツしちゃって」という印象のトラックです。
最近のハービーさんは高踏的なんだか卑俗的なんだかわからないようなところがありますが、このアルバムはバランスが良いように思います。個人的にはトラック1,2,4,5,6がよかったです。
Tags: Hancock, Herbie · piano · Shorter, Wayne
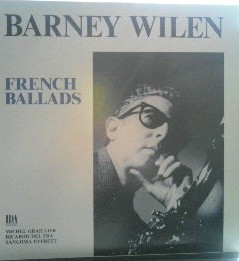
バルネ・ウィランにはこのアルバムから入門したために、ずっと「パリの粋なエスプリを感じさせるテナー」という印象を持っていました。寺島さんも、その著書で「国立(くにたち)にはバルネがよく似合う」とおっしゃっていましたが、確かに雨の昼間の国立でこの『フレンチ・バラッズ』を聴いたらとても合いそうです。で、このアルバムから興味を持って他の作品を聴いていったのですが、ずいぶんとまた話が違う。同じ時期の他の作品ももっと前衛的なアプローチをしていたり、逆に極めて正統派のバップをやっていたりするし、若い頃の作品にいたってはハード・バップど真ん中だったりして驚きました。しかし、例外的な作品であるにせよ、この『フレンチ・バラッズ』は大傑作です。その証拠というわけではないですが、廃盤のためAmazonマーケットではなんだかとんでもない値段をつけて売られています。私の場合は一回アナログで再発された時にたまたま見つけて買いましたが、幸福な買い物でした。今でも折に触れて聴き続けています。
セッションは1987年6月24?26日、録音はフランスのイエール。Google Earthで調べてみると、パリ近郊の町のようです。メンバーはバルネ・ウィラン(ts)の他、ミシェル・グライユール(p)、リカルド・デル・フラ(b)、サンゴマ・エベレット(ds)のワン・ホーン・カルテット。曲はシャンソンを中心として全てフランス関係の曲で、それがタイトルの由来となっています。
A面1曲目「詩人の魂 (L'Ame des Poetes)」、シャンソン曲です。しかし、これが非常に深い印象を与えます。冒頭のテーマからフランスの香りがプンプン漂う。バルネの音色も深みが増した感じ。そして凄いのがドラムのサンゴマ・エベレット!彼のシンバル・ワークがこの演奏を傑作へと押し上げた感があります。いわゆるインタープレイでバルネに積極的に絡んでいくわけです。この1曲で打ちのめされました。
A面2曲目はミシェル・ルグラン作曲ですが、ジャズでもたまに取り上げられる "What Are You Doing the Rest of Your Life" 、邦題「これからの人生」。サブトーンを駆使して低音部を吹ききっている傑作で、テーマを歌い上げているだけですが哀愁感たっぷりです。3曲目「パリの空の下 ("Sous le Ciel de Paris")」はエディット・ピアフも歌っていたシャンソンの名曲。アップ・テンポの3拍子でAメロを低音部で吹き、サビから高音部に移ってそのままアドリブに突入しますがあっという間に終了。むしろ次のピアノがフィーチャーされた感じでなかなか聴かせるソロ。ピアノが終わって再びバルネ登場。少しソロを取ってエンディングという構成です。
A面4曲目は再びルグランの曲で、日本でも有名な「おもいでの夏 (Un Ete)」。ソプラノ・サックスでやはり哀愁たっぷりに吹き上げています。ラスト曲は「夢の城 ("Monoir de Mes Reves")。ジャンゴ・ラインハルト、フランス読みすればジャンゴ・レナールの曲です。ドラムが叩き出すビギンのリズムの上でバルネとグライユールがソロを取り、楽しい演奏が繰り広げられています。
B面1曲目は「枯葉 ("Les Feilles Mortes")」。フランス性を出すためにヴァースから演奏しています。テーマからは4ビートのミディアム。演奏時間はこのアルバムで最長の7分10秒でアドリブを4コーラスとっています。ただ4コーラス目はひょっとしたらピアノが入るはずだったのに入らなかったのか、バルネが途中から入っています。しかしどのコーラスもスムーズで美しいアドリブ。2曲目は再びルグランの曲で "Once upon a Summertime"。しかし、高井さんのライナーによると、これも元歌はシャンソンだそうです。ピアノを大きくフィーチャーした構成で、バルネも高音部にまでサブトーンを浸潤させさわやかに吹いています。ベース・ソロも出てきます。
B面3曲目はジャンゴの曲で "Tears"。ピアノレスの構成で、わりと自由にアウトしたり、パーカッシブ・トーンを繰り出したり、フリージャズに傾斜した経験をいい形で生かしています。そして最後は再びピアフとサッチモの名唱で知られるシャンソン曲「バラ色の人生 ("La Vie en Rose")」。冒頭からアドリブをはじめて、ちらちらとテーマの片鱗を吹きつつもじらせながら、最後の1コーラスでやっとテーマの全貌を明らかにするという心憎い構成。こういう「誰でも知っている」名曲にふさわしい仕掛けです。
下のリンク先はCDのもので、私の持っているLPよりもずっと曲数が多いです。値段はとんでもないものですが地道に中古レコードをまわれば、もっとリーズナブルな価格で求められるはずです。
Tags: tenor sax · Wilen, Barney

日本のジャズ・レーベル「イースト・ウィンド」というと、ナベサダや菊地雅章、富樫雅彦ら日本の一流ジャズ・ミュージシャンに光を当てる一方、ザ・グレイト・ジャズ・トリオのアルバムでL.A.だか桑港だかの抜けるような青空をジャケットに使ったレーベルとして、私の記憶にはインプットされています。風景メインのあのジャケットは「時代がない」ように見えて実は非常に「時代がかって」いて、今見ると「ああ、あの頃流行のね」という感想がどうしても湧いて来るのが不思議です。風景の切り取り方にも時代性というかハヤリスタリがあるのでしょう。
今回紹介するアート・ファーマーの『トゥ・デューク・ウィズ・ラブ』はそのイースト・ウィンドで制作された名アルバムの一つで、1975年3月5日にニューヨークで録音されたものです。タイトルが示すとおりデューク・エリントンに捧げられたもので、彼はその前年の1974年5月24日に亡くなりました。メンバーはアート・ファーマー(flh)の他、シダ・ウォルトン(p)、サム・ジョーンズ(b)、ビリー・ヒギンズ(ds)という名人達です。プロデューサーは伊藤潔、伊藤八十八、それに守崎幸夫。
この頃の録音の特色として、レンジを広く取る代わりに音のエネルギーがないものが多くありましたが、これは普段のボリューム位置で聴くと薄く聴こえるけれど、ボリュームを上げていくと音全体がふんわりと厚くなり、サム・ジョーンズのベースもビリー・ヒギンズのシンバルも真に迫って聴こえてくるような名録音です。うちの安いキカイでもそうなのでよい機械を使えばもっとよく聴こえることでしょう(LPでの話です)。
A面1曲目 "In a Sentimental Mood"。ファーマーのフリューゲル・ホーンがどこか遠くへ呼びかけるような音色で哀愁あるテーマを演奏し、そのままソロに。バックのベースとドラムの張り切り方が凄い。
2曲目は "It Don't Mean a Thing"、「スイングしなけりゃ意味がない」です。ベースのテーマから入り、フィル・インで全員が合奏に突入します。ソロの先発はシダ・ウォルトン。エリントンを意識したかのようなソロです。続いてファーマー。ここでもウォルトンのコンピングが独自の色合いを出しています。続くベース・ソロを経てテーマに返します。ラッパとドラムが「ユニゾン」でテーマを演奏し終えます。実に名演。
3曲目の "The Star Crossed Lovers" はシェイクスピア・フェスティバルにエリントンが書き贈った曲で、『ロミオとジュリエット』をテーマとした曲だそうです。このタイトルの出典は有名で、同戯曲のプロローグで述べられる "From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-cross'd lovers, take their life"(お互いを仇と憎むこの両家から、この星回りの悪い一対の恋人は、生を受けたのでございます) という詩行からきています。半音進行を伴ったなんともいえぬ味わいと懐かしさを持った曲で、フリューゲル・ホーンの音色とも相性がよく、素晴らしいバラード演奏に仕上がっています。続くウォルトンのピアノも上手い。鍵盤を連打しながらアドリブを盛り上げるや、一転ブルース・フィーリングあふれたソロに切り替えるところなんか息を飲みます。
B面は1曲目が "Brown Skin Gal in the Calico Gown"。イントロのウォルトンがエリントンにそっくり。テーマはAメロでドラムがシャッフルを叩き、Bメロが4ビート。ソロに入るとダブル・タイムになりますが、なんと言うかウォルトンのコンピングとヒギンズのドラミングのために、小さなエリントン楽団がそこで演奏しているようです。面白いことにピアノ・ソロになるとエリントン風味は消して、シダ・ウォルトンそのもののアドリブとなっています。
2曲目は有名な "Lush Life"、ビリー・ストレイホーンの曲。曲そのものが美しいので余計な色をつけずに、フリューゲル・ホーンの魅力全開で演奏しています。この楽器はどこか孤独の翳りをもった音色なんですね。それが曲想とマッチしています。
3曲目の "Love You Madly" はエリントンの口癖をそのまま曲名にしたもの。マイルスも "He Loved Him Madly" という曲を書いてエリントンに哀悼の意を捧げています。ミディアム・スイングの演奏だけれど、テーマはフリューゲル・ホーンとミスマッチ。ただ、アドリブに入ってからくっきりとしたラインを描き出すファーマーはさすが。途中ダブル・タイム・フィーリングをはさみ熱いソロを取っています。
CD化もされているようです。別テイクの追加などはないようですが、オリジナル6曲でも充分価値のあるアルバムだと思います。ファーマーが吹いているのはフリューゲル・ホーンですが、便宜上トランペットに分類しました。
Tags: Farmer, Art · trumpet