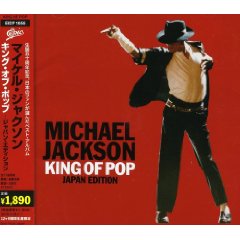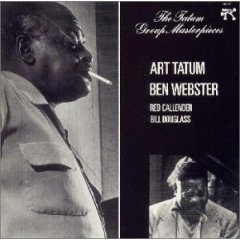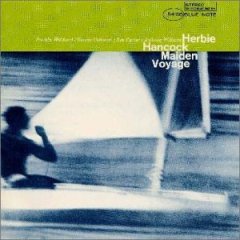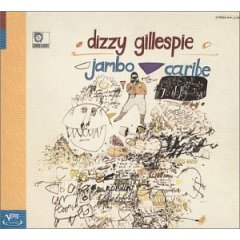Side-A
1. Sun Showers
2. Yours and Mine
3. I'll Get By
4. Mean to Me
5. Foolin' Myself
6. Easy Living
7. I'll Never Be the Same
8. Me, Myself and I
9. A Sailboat in the Moonlight
Side-B
1. Can't Help Loving' Dat Man
2. When You're Smiling
3. I Can't Believe that You're in Love with Me
4. I'll Never Fail You
5. The Man I Love
6. All of Me
7. I'm in a Lowdown Groove
8. Love Me or Leave Me
9. Until the Real Thing Comes Along
Disk 2の曲は以上のとおり。このアルバムのA面を彩るセッションはレスターヤングとビリーのインタープレイ、そしてメンバー全員による集中したソロとメンバー間に漂うグルーヴにより、ジャズ史上最高のセッションと言われます。私も、この面は何度かけたか計り知れません。最初の4曲は'37年5月11日のセッション。メンバーはレディーのほかバック・クレイトン(tp)、バスター・ベイリー(cl)、ジョニー・ホッジス(as)、レスター・ヤング(ts)、テディー・ウィルソン(p)、アラン・リュース(g)、アーティー・バーンスタイン(b)、コジー・コール(ds)。1曲目"Sunshower"ではレスターのイントロの後、クレイトン、ホッジスによるテーマ演奏が続き、バスターのオブリガートを伴ってビリーが抑えた感じで入ってゆき盛り上がった感じで抜けてゆきます。テディーのソロの後は、レスターの1、3拍(表)にアクセント置く意表をついたアドリブを経てコーダになります。2曲目の"Yours and Mine"もホッジス、クレイトンによるテーマーからビリーの歌、そしてテディー、レスターのソロへとつながります。3曲目の "I'll Get by"でホッジスのテーマの後に出てくるビリーは、"I Cried for You"以上にメロディーの動きをセーブして、おそらく数音だけで構成されている実に風変わりでいながら、きわめてモダンな感覚をもつ歌い方でこの曲を元歌以上に魅力あるものに仕上げています。そして、この日最大の成果はやはり "Mean to Me" でしょう。冒頭でテーマを吹くレスターがすごい。2回目のAの部分ですでに倍テンでメロディー崩してしまい、クレイトンのサビの後はまったく新しいメロディーを即座に取り出してきます。ここでも、レスターはあえて1、3拍にアタックをつけるといった意表をついたアドリブを展開します。続いて入るビリーの歌も圧巻で、彼女特有の後乗りで歌った後、最後のA(つまりレスターが表にアクセントを置いた部分)でレスターと同様に表拍にアタックを入れていきます。この一体感が彼らのセッションの最大の魅力です。

Lester Young
次の3曲は'37年6月1日のセッションでメンバーはクレイトン、レスター、ベイリー、テディーのほか、ギターがフレディー・グリーン、ベースがウォルター・ペイジ、ドラムがジョー・ジョーンズという「オール・アメリカン・リズムセクション」で構成されています。 "Foolin' Myself"はレスターが16小節、サビはテディー、後メロはクレイトンが吹き分け、ビリーの歌になります。この歌を聴くと、「彼女は自分がいったい何を歌っているのか熟知している」との評言が的を射ていることが分かります。同じことは次の "Easy Living"にも当てはまり、いったいこのバージョンを超える「イージー・リビング」などありえるのかという気にさせられます。とくにサビの最後 "They just don't understand"の解釈は圧倒的で、今でもこの曲を演奏する人は直接、間接的にこのバージョンの影響を受けています。当時まだ22の娘の演奏なのにね。つづく "I'll Never Be the Same" では、レスターによるオブリガートというより対旋律のように積極的な絡みにサポートされて一体感のあるビリーの歌が光ります。

若き日のレディー・デイ
最後の2曲は'37年6月15日のセッション。メンバーは上のメンバーのバスター・ベイリーに代わってエドモンド・ホール、テディー・ウィルソンに代わってジェームズ・シャーマンがピアノを弾いています。したがってテディー・ウィルソンのセッションではなくて、「ビリー・ホリデイと彼女の楽団」というクレジットになっています。ここに聞かれる "Me, Myself and I" と "A Sailboat in the Moonlight" は彼ら(とりわけビリーとレスター)による不滅の金字塔的作品です。"Me, Myself and I" では、ビリーが間奏をはさんで2コーラス歌うのですが、アプローチを変えることで、楽器演奏者とまったく同じ、あるいはそれ以上のレベルにたって(なぜならば歌詞というしばりがあるので)アドリブを展開していることがよく分かります。さらに "Sailboat"では、オブリガートをつけるレスターとビリーの間に、霊的としか言いようのない交感があって、お互いのフレーズを先取りしあいながらインタープレイの妙を繰り広げます。また、レスターによる表拍を強調したサビのアドリブが終わり、ビリーが歌い始めるや、彼はテナーでの最高音のひとつFを打ち出し、それに弾かれたように、ビリーが同様に表拍にビートを置いたフレーズで一音一音歌詞を叩きつけていくあたりはいつ聞いても背中に電流が走るほどです。ここまでのインタープレイは、モダンジャズになってもビル・エバンスとスコット・ラファロを俟たなければ生まれませんでした。
もしこの時点でビリーが引退してしまっていたとしても、彼女のジャズに対する影響は少しも減じることがなかったでしょう。しかし、彼女にはまだ使命がありました。それは「奇妙な果実」を歌うこと、そして後期のトーチソングを歌いついでいくことでした。これによってレディーは、ジャズに限定されず「歌の世界」そのものに影響を与えていくこととなったわけです。
まるで、締めの文章のようですが、まだB面が残っていました 8)
B面1曲目、"I Cant Help Lovin' Dat Man"は'37年11月1日のセッションからで、この日のセッションにはビリーの十八番となる"My Man"も吹き込まれています。この曲では、メロディーの変化を極力抑えたビリー節がよく出ています。
2曲目と3曲目は年も改まった'38年1月6日のセッション。2曲目 "When You're Smiling"はレスターのアルバムで私が初めて聞いたビリー・ホリデイの吹き込みです。この演奏におけるレスターは神がかっていて、スイング時代としては最高のインプロヴィゼーションを展開しています。後にリー・コニッツがアルバム『トランキリティー』の中で、このアドリブラインをそっくり真似たのは有名な話です。ビリーの歌い方もモダンなフレージングです。4曲目 "I Can't Believe that You're in Love with Me"はテンポをぐっと落として叙情的な歌に仕上げています。
4曲目 "I'll Never Fail You" は'38年11月9日のセッション。続く"The Man I Love"は'39年12月13日と疎らになってきます。これは彼女がアーティー・ショーのバンドシンガーになったり、52丁目のクラブ「カフェ・ソサエティー」の呼び物になったりで、徐々にスターダムを駆け上がっていった結果かと思われます。"The Man I Love"でのビリーの歌とレスターのソロはこの時期屈指のもので、必聴の1曲といえます。
6曲目の"All of Me"は'41年3月21日のセッションで、ビリーとレスターによる、驚くべきインタープレイの妙が聴かれるトラックです。7曲目"I'm in A Lowdown Groove"は'41年5月9日、8曲目"Love Me or Leave Me"は'41年8月7日、そして最後のトラック"Until The Real Thing Comes Along"は'42年2月10日で、このセッションがコロムビアにおける一連のセッションの最後となります。"Love Me or Leave" は"Lullaby of Birdland"の元歌で、トリッキーなコード進行とメロディーを持っている曲ですが、ビリーがまったく自分のものとして料理してしまっていることに改めて驚かされます。
ビリーのコロンビアにおける吹込みの真価はビバップを飛び越えて、ウェスト・コースト・ジャズの時代になり明確な形をとります。リー・コニッツ、アート・ペッパー、ジェリー・マリガン、チェット・ベイカーといったミュージシャンたちが、レスターとのコラボにインスパイアーされてこの時代に吹き込まれた曲をモダンジャズとして蘇らせていくからです。さらにモダンジャズ期の歌手たちにとってこれらの吹き込みはお手本として、時には乗り越えるべき障害として彼らの前に立ちはだかることになるわけです。
そのビリー・ホリデイ本人はこの後、畢生の名曲「奇妙な果実」と出会い、自分自身の人生と歌とを重ね合わせることにより歌にドラマを持ち込むというそれまでにはない新たな「歌のあり方」を開拓していくのです。
この選集にきわめて近いアルバムを挙げておきます。1枚目はコロムビア時代をまとめた選集、2枚目は中でもレスターとのコラボに焦点を当てたすばらしいコンピです。
Tags: Holiday, Billie · vocal · Wilson, Teddy · Young, Lester

ビリー・ホリデイが亡くなって、今年で50年。ルイ・アームストロングと共に、それまでの歌のあり方を圧倒的な才能で一挙に転換してしまったこの20世紀最大の天才歌手をしばらく集中的に取り上げてみようと思います。
細かいことを考えなければビリーは3つの時期に分かれます。前期(ブランスウィック・ヴォキャリオン時代)、中期(コモドア・デッカ時代)、そして後期(ヴァーヴ時代)。それぞれ吹き込んでいるレーベルに対応するだけでなく、楽曲に対するアプローチとコンセプトにも対応している。
今回は前期、つまりブランスウィックやヴォキャリオンに吹き込んでいた時代について取り扱いたいと思いますが、この時期についてまとめると「リズムの時代」と言えます。たとえば、この時期の最大のヒット作といえる"I Cried for You"をに耳を傾けるとそのことはたちどころに了解されるはずです。この元歌の出だしはメロディーの動きがとても激しいんです。"I"がミ、"cried"が上のシ、"for"がその下のラ、最後の"you"はオクターブ下のラにまで落ちていく。のど自慢の歌手が歌えばこの上昇下降の音形をこれ見よがしにトレースするのに対して、ビリーはこの出だしの5度のジャンプを省略し、これに代わってリズムでフレーズの妙を展開します。さらに続くフレーズではメロディーの動きを抑えて、ほとんど同一の音でリズムに綾をつけていきます。そう、これは後にロリンズが繰り出す「モールス信号」、さらに現代のラッパーたちの原型と呼ぶべきものです。こう考えると、NYの地下鉄で日本のサラリーマンがビリーのレコードを見ていたら、近づいてきたアフリカ系のラッパーの兄ちゃんが "May I see it?"と、普段なら使いもしないような "May . . ?"で「見せてください」と頼んだというエピソードもうなづけます。と言うことで、この時期のレディーは形式的にすでに完成され、何をどう歌うべきかと言う指針を後代に残した重要な時期であると思うのです。ちなみに、中期は「フシの時代」と言うべきであり、後期は「心の時代」というNHK教育テレビの日曜早朝の宗教番組のような様相を呈してきますが、それはまた次の機会に。ただ、この全てを通じて結局変わらなかったのは(それは激変したにもかかわらず)彼女の声であり、それは常にサックスのサウンドであったことです。激変したのに変わらなかったという彼女のパラドクスに関しては、後期に関する記事で取り上げる予定ですが、未定です。
伝記的には1932年ごろハーレムで歌っているところをジョン・ハモンド坊ちゃんに見出され、翌33年11月27日にベニー・グッドマン楽団(まだプレークする前)と共に吹き込んだ "Your Mother's Son-in-Law"が初レコーディングとなり、これ以降いわゆるコロンビア系の吹き込みは230曲とも、それ以上とも言われています。これについてすべて解説するのは骨が折れるので、今回はそのベスト集を下敷きに解説してみたいと思います。特に今回取り上げる『ビリー・ホリデイの肖像』はLP時代末期、油井先生監修の元、ビリー・ホリデイ研究では日本の第一人者と言うべき大和明先生が選びに選んだ2枚組みなので、そこいらのアメリカ製CDコンピなど足元にも及ばないほど厳選されたものです。曲データは以下のとおり。
Disc-1
Side-A
1. I Wished on the Moon
2. What a Little Moonlight Can Do
3. Miss Brwon to You
4. If You Were Mine
5. It's Like Reaching for the Moon
6. These Foolish Things
7. I Cried for You
8. Did I Remember
9. No Regrets
Side-B
1. Summertime
2. Billie's Blues
3. Pennies from Heaven
4. This Year's Kiss
5. Why Was I Born
6. I Must Have That Man
7. My Last Affair
8. Carelessly
9. Moanin' Low
Disc-2
Side-A
1. Sun Showers
2. Yours and Mine
3. I'll Get By
4. Mean to Me
5. Foolin' Myself
6. Easy Living
7. I'll Never Be the Same
8. Me, Myself and I
9. A Sailboat in the Moonlight
Side-B
1. Can't Help Loving' Dat Man
2. When You're Smiling
3. I Can't Believe that You're in Love with Me
4. I'll Never Fail You
5. The Man I Love
6. All of Me
7. I'm in a Lowdown Groove
8. Love Me or Leave Me
9. Until the Real Thing Comes Along
一枚目、冒頭の3曲はブランスウィック・セッションにおける最初の吹込みでありながら、一気に理想的な演奏にまで到達した不滅の3曲と言うことができます("A Sun Bonnet Blue"が省かれている)。録音日時は'35年7月2日。"I Wished on the Moon"の歌いだしはこの時期に特徴的な低唱と、ビートに微妙に遅れて乗っていくという彼女のトレードマークに彩られています。特筆すべきは "What a Little Moonlight Can Do"の演奏で、これは3分芸術としての極地を示した多面的な演奏です。テディーの魅力的なイントロから、ベニー・グッドマンがクラリネットの低域を活用したテーマを半コーラス吹き、その後一転して高域でテーマを演奏する。続くビリーは早くも"Ooh-ooh-ooh"の3音をオリジナルに逆らってD音だけで歌いとおすという個性を発揮しています。曲全体がチョッパやで突っかけるような2ビートを刻んでいるのに対して、ビリーは微妙に遅れつつビートを前後にゆすることでタメの効いた乗りで歌っています。ビリーの後はベン・ウェブスター(ts)、テディ・ウィルソン、ロイ・エルドリッジ(tp)のソロが続きますが、ビリーの圧倒的な歌唱の前に霞んでます。 "Miss Brown to You"は、ベニーによる冒頭のイントロが魅力的で、油井先生はこの部分をそれこそ「真っ白になるまで聞き込んだ」と言っています。"What a Little Moonlight"と同じくクラの低域を活用し後半になって高域に動かしていくテーマ演奏の後は、ビリーの歌。テンポがよいのでタメの効いた乗りから自在にアクセントを動かしてスイングを作り出していきます。Aメロの部分とBメロに入ってからでアプローチを変え、後半部分はまるでトランペッターのようなアタックです。また、この曲ではピー・ウィー・ラッセルなどがよくやるグロール・トーンをところどころ使って、まるで二つの音を同時に出そうとするような歌い方をしています。歌い終わっても名残惜しむかのように、デディーのピアノに合いの手を入れていくところもすばらしい。
4曲目の "If You Were Mine"は'35年10月25日のセッションで、何気ない演奏ながらも心のこもった歌が聴けます。とくに "Every my heart, every my life"の積み上げのところは実にしみじみしています。
5曲目から7曲目までは'36年6月30日のセッションで、エリントンのところからハリー・カーネイ(bs)とジョニー・ホッジス(as)が参加しています。5曲目 "It's Like Reaching for the Moon"ではホッジスがエリントン臭(と言うかホッジス臭)全開のソロを受けて、ビリーが例のグロール・トーンを時おり交えながら歌いついでいきます。ハリー・カーネイはここでクラリネットのオブリガートをつけていてちょっとしつこい感じ。6曲目 "These Foolish Things"はイギリスの小唄で、歌詞といい曲想といいビリーに似合いそうですが、冒頭ちょっとビブラートをつけすぎで歌いこなせてない感じがします。しかしサビが終わってAメロに戻ってきたあたりのフレーズ("Win the marks and make my heart a dancer")は最高で、やはりすばらしい出来を示しています。そして当時としては驚異的な売り上げ15,000枚(3,000枚程度が普通だったらしい)を誇った "I Cried for You"。マクラでも述べましたが、メロディーの動きを最小限に省略して、これに代わってリズムを大胆に動かしていく彼女の特色がよく出ています。サビのところの対句となるフレーズを、入りを少しずらすことでそれぞれ異なったフレーズに仕上げているところも見逃せません。
A面8曲目からB面2曲目までは'36年7月10日の吹き込みで、バニー・ベリガン(tp)とアーティー・ショウ(cl)が参加しています。後にビリーはアーティーの楽団に参加し、黒人女性としては初めて白人バンドのバンドシンガーになるわけです。しかしながらさまざまな障害と彼女のストレートな性格から退団にいたるのは後の話。8曲目の "Did I Remember"ではイントロの直後から、自信を持ったビリー節を炸裂させて印象的なトラックになっています。続く "No Regrets"でも、ギターのイントロに続いてビリーが入ります。このセッションはペットとクラの絡みが中心なので音が高域に偏る憾みがありますが、アンサンブルのすばらしさと、ビリーの自信に満ちて文字通り"後悔しない"かのような潔いフレージングがその欠点を補って余りあります。
しかし、このセッションの最大の成果は続くB面冒頭の2曲、 "Summertime" と "Billie's Blues" でしょう。この "Summertime"は、しかしすばらしい。バニー・ベリガンの印象的なイントロに続いて、ビリーは低唱を生かした出だしから、いつもと同じく後乗りでメロディーの変化もぎりぎりまで抑えています。それにもかかわらずきわめてブルージーで威厳を持った歌になっている。2コーラス歌った後出てくるアーティーのソロもよく、さらにその後再び2コーラス目を歌うビリーのフレージングは冒頭の力強いアタックから最後のコーダ処理にいたるまで目を見張るものがあります。この "Summertime" の歌いだしのフレージングを、後にジャニス・ジョップリンが意図的に模倣します。ジャンルも、そして声質(ビリーがサックスの声なのに対して、ジャニスはディストーションをかけたギターの声)も違いますが、ビリーの後継者はジャニスかもしれません。真の後継者とは師のやり方をそのまま真似るのではなく、その精神を受け継ぐものだと思います。同じように、パーカーの真の後継者はパーカーのやり方からはどんどん離れつつ、その精神だけは失わなかったマイルスです。2曲目の "Billie's Blues"は「ブルースを歌うレディー」としては数少ないブルース(12小節形式という意味でのブルース)で、当時の趣向も手伝ってブギウギのリズムに乗って比較的アップテンポで歌われます。1コーラス目はアーティーがオブリガートをつけ、2コーラス目はベリガンが、続いてアーティーの力強いクラリネットと、ベリガンのダークで太いトーンを生かしたソロが続きます。再び出てくるビリーは3連符を畳み掛けるように効かせたすばらしい12小節で演奏を締めています。
3曲目 "Pennies from Heaven"は'36年11月19日のセッションでベニー・グッドマンやベン・ウェブスターが再び参加しています。ここでのビリーは自由なフレージングでインプロヴァーザーとしての面目躍如。オブリガートをつけるベニーも控えめですばらしい。ここでは省かれていますが、同日のセッションで吹き込まれた "I Can't Give You Anything but Love"も必聴の一曲で、サッチモの歌とトランペットの影響が直接的に現れていて、実に興味深い演奏です。
4-6曲目に聞かれる'37年1月25日のセッションは彼女のセッション中最も重要なもののひとつで、レスター・ヤングとバック・クレイトンが参加しています。4曲目 "This Years Kiss"の冒頭に演奏されるレスターの美しくてしなやかなフレーズは、そのままビリーの歌に引き継がれていきます。同じように "Why Was I Born"では冒頭のテーマをバック・クレイトンが取り、ビリーの歌は自由にフレーズを作り変えながら、繊細な情緒を歌いだしています。そしてこの日最大の成果ともいうべきトラックが6曲目の "I Must Have That Man"。ビリーの畳み掛けるような歌に控えめに絡んでいくクレイトンのオブリガート、そのムード引き継いでレスターとベニー・グッドマンのソロ。最後の合奏などお互いがお互いの音を聞きあい、気持ちを理解しあっているからこそ生まれるグルーブ感がたっぷりです。このセッションは、ちょうどビックス・バイダーベックとフランキー・トランバウワーがそうであったように、気心の知れた仲間が集まって和気藹々と最高傑作を生み出したところにその価値がある。ジャズはなんだかんだ言って、強いもの勝ちなところがあり、傑作といわれる演奏もどちらかというと競い合い、腕比べ、丁々発止のやり取りから生まれることが多い。サッチモとアール・ハインズの28年の演奏や、パーカーとディズ、バドとファッツ・ナヴァロなんかはそうした試合系の典型です。一方で、ここに聞かれるような調和系というのか、お互いが相手を上回ろうとがんばりすぎず、むしろ互いに引き立てあうように演奏を高めていく音楽観は、ビバップを飛び越えてマイルスに直結する姿勢であり、晩年のマイルスの映像を目にするにつけ、この姿勢は彼が生涯保ち続けたものだという確信を深くします。
7曲目の"My Last Affair"は'37年2月18日のセッションで、メンバーはがらりと変わるものの上のセッションのムードを引き継いだ感じがして面白い。とくにヘンリー・レッドアレンのソロがよく、彼女の歌も、歌詞をちょっとクールに眺めて面白いフレージングを見せています。
8-9曲目はエリントンのところからクーティー・ウィリアムス(tp)、ホッジス(as)、カーネイ(bs)の3人がやってきた'37年3月31日のセッション。8曲目の "Carelessly"ではホッジスが、9曲目の"Moanin' Low"ではクーティーがそれぞれビリーのバックでオブリガートをつけますが、ちょっとつけすぎでやかましい感じがします。
レコード1枚目はここまで。2枚目のA面は彼女のキャリアにおいてのみならず、ジャズ史上最も重要なセッション群が続くので、稿を改めたいと思います。
Tags: Holiday, Billie · vocal · Webster, Ben · Wilson, Teddy · Young, Lester
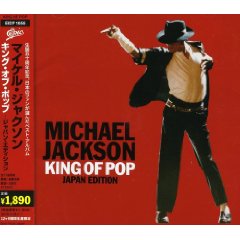
遅ればせながら、MJのペスト盤を購入しました。
このベスト集は、各国のファンによる投票を基に、それぞれの国のエディションを製作したそうですが、これはジャパンエディション。
私はとにかく学生時代の思い出 "Man in the Mirror", "Thriller", "Bad"と、マイルスが取り上げたことで知った "Human Nature" そして平和への希求を表現した "Heal the World"が入っていないと気がすまない感じだったのですが、このジャパンエディションは見事にその希望を叶えてくれ、おまけに "We Are the World" のデモバージョンまで含まれています。大満足!私が日本人だからジャパンエディションと相性がいいのか、日本のマイケルファンのレベルが高いのか、私は後者だと思っています。
"We Are the World" デモバージョンは、本番とは歌詞も若干違うのですが、特に気づいたのが "there's a choice we're makin', we're savin' . . ." のリフレインが、"there's a chance we're takin', we're takin' . . ." となっていたところです。デモの歌詞だと、"takin'"が近いところに繰り返し出てきて、さらに"chance"の"n"音と"takin'"の"n"音が耳につき語調が悪い。完成版の "choice - makin' - savin'"のほうが響きもきれいだし、意味の力も鮮烈。言葉一つもゆるがせにしない詩人マイケルの姿が垣間見えます。
"Heal the World"は Dangerous のバージョンと違って、冒頭につっかえつっかえ読む子供の台詞がはしょられ、エンディングのリフレインも省略されています(元のはちょっとしつこいかも)。
いずれにせよ、この価格とあいまって絶対にお勧めできる一枚となっています。
Tags: Rock, Pops, Classical
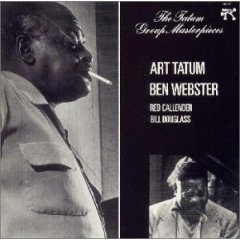
盲目のピアニストアート・テイタムは超弩級のテクニシャンで天才なのですが、いまひとつ人気がありません。その理由は多くの人が気づいているように「うるさい」んですね。上手いんだけれどのべつ幕なしに「コロコロコロコロ」やられると耳につく。音楽で「耳につく」なんていうのは最悪なことなんですが、それでも耳について仕方がない。さらに、テイタムのソロ集などは大体が3分前後の演奏で、どの曲も同じように珠を転がしているので単調な感じがする。同じバカテクでもオスカー・ピーターソンが、そのバリエーションの豊かさから高い人気を得ているのに対して、アート・テイタムがいまひとつ人気がないのは、そういうわけだと思います。
それにしても、アニタ・オデイが "You're the Top" の中で歌詞をアドリブし、素晴らしいものの引き合いに "Tatum's left hand" (テイタムの左手)と歌っているように、実際目の前で展開されたら魂消るような上手さであることには変わりありません。ソロ集だと単調に流れる憾みがあるので、今回はホーン入りの名盤を紹介します。
メンバーはテイタム(p)、ベン・ウェブスター(ts)、レッド・カレンダー(b)、ビル・ダグラス(ds)で、録音は1956年9月11日。
1曲目は "Gone with the Wind" 。エラがベルリンで歌った名唱が残されていますが、それに匹敵するような名演です。イントロからテーマまでテイタムが弾ききっていますが、それにしても手数の多いこと 🙂 せわしない感じすらしますが、その後に出てくるベンの悠揚迫らざるテナーと良い対比をなしています。この1曲目でこのセッションが成功していることは分かります、
2曲目の "All the Things You Are" はバップの聖典ですが、二人にはそんなこと無関係。「名バラッド」としてアプローチしています。ベンの深い音の背後でコンピングをつけるテイタムはしかし、コンピングという範疇を超えています。つまり出しゃばりすぎなわけです。ホーンと一緒になってアドリブしているわけですが、それがインタープレイに昇華されずに、同時に色んなことやっているという風情を醸し出しています。ビリー・ホリデイがらみのエピソードで「ベンは非常に短気だった」というのを聞いたことがありますが、この時彼は怒り出さなかったのかしら?あるいは「俺のバックでピアノを弾くな」とマイルスばりの発言はなかったのでしょうか?しかし、いずれにせよ56年という段階で、この曲を「ありきたりのバップ」にしていないところは凄いです。
"Have You Met Miss Jones" は邦題「ジョーンズ嬢に会ったかい?」は、テイタムを尊敬するピアニストオスカーPが、人気盤『プリーズ・リクエスト』で吹き込んでいますが、ここでの演奏はぐっとテンポを落としてゆったりとしたバラードに仕上げています。それにしてもベンのテナーの音色は実に豊かです。サブトーンが満遍なくいきわたっていて「これぞテナー」という音色。テイタムはやはりバックで手数多くやっていますが、この頃になると、「このアルバムはこういうもの」という気分に切り替わって、楽しく聞けます。
4曲目の "My One and Only Love" といえばコルトレーンとハートマンを思い出しますが、彼ら二人もわりとストレートにやっているせいか、この演奏とかぶります。もちろんハートマンがベンで、コルトレーンが後ろでうるさいテイタムの役です。かなり長いテイタムのソロがフィーチャーされた後ベンに受け渡されますが、二人とも全トラック中最高の出来を示していると思います。
5曲目 "Night and Day" にいたってやっとテンポが上がります。テーマのテイタムはストライド+テイタムという世にも恐ろしい展開になっています。ハイ・テンポだとベンも吹き荒ぶ傾向があって困りものなのですが、これはちょっと速いといった程度なので荒まずに吹いています。
6曲目の "My Ideal" は再びバラード。ここでのベンのソロは聴きもので、レイドバックしてブルージーな、実にくつろいだソロを取っています。テイタムはテイタムでテイタム満開の上昇下降を繰り返す「コロコロ」ソロから、一転ブルース・フィーリング豊かなソロに転じます。左手が走っているのは相変わらずですが。これは味わい深い。レコードでいう「B面2曲目」のジンクスがここでも発揮されています。
ラストが "Where or When"。テーマはテイタム。テーマの旋律を凌駕するような感じで左手が走りまくっています。もう、一人オーケストラ状態です。何ていう曲か忘れそうです。ということでベンが再びテーマのメロディーをしっかり吹きなおしています。
CDではこの後別テイクが3曲収められています。
いろいろ書きましたが、名盤ですよ。テイタムはソロだとベースやドラムも一人で受け持って、おまけに受け持てるだけの技量があるので時にうるさく感じますが、それでも一聴しただけで、ここまで強烈な個性を感じさせるピアニストは少数です。この辺の、強烈で傲慢なまでの個性というのが当時のジャズ界に見られるバイタリティーの源泉なのかもしれません。いまの人たちなら、それだけのテクがあっても「空気を読んで」控えてしまうかもしれません。さらに、この盤はベース、ドラム入りなので(全く空気を読んでいない場面も多いですが)少しだけ抑えた感じになっています。
まあ、「空気読む」なんて最低のフレーズなんですけれどね。
Tags: piano · Tatum, Art · tenor sax · Webster, Ben
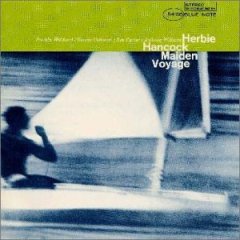
ちょうどジャズに興味を持ち出した頃、奥平真吾さん(当時11歳!)がデビュー作『処女航海』をリリースして、おまけに彼と私が一歳違い。にもかかわらずこの大きな違いは何なんだ!?という大きな疑問にぶち当たりました。さいわい「才能の違い」という答えがすぐ見つかり、この疑問は解決しましたがね 8) その後、この曲がハービー・ハンコックの代表作であり、ジャズ史にも影響を与えたエポック・メイキングな作品だったと知ったのはだいぶ後のことです。
最初にこのタイトル曲を聴いた時は、とくかく「クールな音楽」「抑えに抑えた音楽」という印象を持ちました。いわゆるクール・ジャズは『クールの誕生』をはじめ、ゲッツやコニッツなど聴いていたのですが、以前も書いたとおり、あまり彼らの音楽を「クール」だと感じたことはありません。一方で "Maiden Voyage" のイントロからして抑制感の極み。ジョージ・コールマンのサックスもショーター的というか、独自の抑揚を持っていて、激しく上昇下降するバップや音を敷き詰めて熱くうねっていくコルトレーンとは違う、クールなフレージングです。普段は熱い、いや暑いことすら多いフレディー・ハバードのトランペットも、実に抑えたブローイング。ハービーさんも、当然のように内省的なソロを取っています。普通、これだけ抑えていると退屈なものに仕上がるのですが、バックのトニー・ウィリアムスだけが自由に暴れているため、演奏をエキサイティングに仕上げています。
2曲目 "The Eye of the Hurricane"。「処女航海」ほど抑えられたものではなく、トニーのドラムを推進力にしてかなりバリバリ進んでいます。フレディーが1曲目とは打って変わって爆発的なブローイングでソロを取り、それに呼応するかのようにコールマン、ハービーも攻撃的なソロを取って演奏を盛り上げています。
3曲目は "Little One"。スローテンポのイントロから、イン・テンポになると3拍子で奏されます。コールマンの出だしはコルトレーンみたい。ちょっと懐かしいような哀愁あるフレーズでソロを構成していて、私のお気に入りでもあります。フレディーのソロもわりと崩し気味に吹いて、それをトニーが煽るという構成で面白い。ピアノは横に広がりのある和声を強調した幻想的なソロです。ロン・カーターのベースソロを経てテーマに戻ります。この曲はマイルスの『E.S.P.』にも吹き込まれています。私見ではマイルス盤の方により興味があります。
4曲目の "Survival of the Fittest" は「適者生存」という進化論の用語で、「音楽とどんな関連があるんだろう」と考えていた時期もありましたが、ある時「ジャズ曲のタイトルにはあまり意味がないものが多い」という記事を読んで納得した記憶があります。もっとも、こんな激しい曲をやったら「適者」じゃないと落ちてしまうような気もします。テンポを自在に動かして、フリーな展開を入れているところが興味深い。相当に相手の音を聴きあって、それに対して瞬時に反応できる連中でないと、ここまでフリーでありながら音楽を成立させることは難しいんじゃないかと思います。そういう意味では確かに「適者生存」かもしれません。ひところ、こういう音楽は難解な感じがして避けていましたが、今では違和感なく聴いています。感性も経験によって変容するのでしょう。
最後の曲 "Dolphine Dance" は、いまやスタンダード化された感のある名曲です。美しい旋律とモーダルな曲想が十分に生かされた雰囲気が素晴らしい。フレディーは曲の穏やかさをこわさない範囲で自由にソロを爆発させ、つづくコールマンも持ち味である甘めのムードを全開にしています。ハービーのソロも素晴らしく、何度でも聴き返したくなる演奏で、1曲目「処女航海」と並ぶ名曲・名演奏。
録音は1965年3月17日。メンバーはフレディー・ハバード(tp)、ジョージ・コールマン(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)。
Tags: Carter, Ron · Coleman, George · Hancock, Herbie · Hubbard, Freddie · piano · Williams, Tony

ベニー・グッドマンのようなオールド・タイマーのジャズを聴く場合、ジャズ(つまり、パーカー以降の"進歩的"モダンジャズ)が先験的に優れているという前提を取っ払う必要があります。なぜなら、彼らはルイ・アームストロングを含めて、進歩的芸術家であろうとするよりも腕のいい音楽職人を目指していたようなところがあるからです。
見方を変えれば、彼らを楽しむときは尖った感じの先端性や革命性ではなく、円熟味やニュアンスといったものを楽しむほうが賢いわけです。ポップス(ルイ・アームストロング)の円熟の極みについては、下のほうで紹介した『ハロー・サッチモ・アゲイン』を皆さんに聴いていただくとして、今回はベニー・グッドマンを取り上げたいと思います。
私も中学生時代は寝ても覚めてもベニーだスイングだという時期がありましたが、モダン・ジャズに目覚めると、ベニーの音楽はなんとなく退屈なものに思えてきました。にもかかわらず、「やっぱりジャズはこれだよなー」と時おり取り出して聴くアルバムが、今回紹介する『ベニー・グッドマン・トリオ・プレイズ・フォー・ザ・フレッチャーヘンダーソン・ファンド』という異様に長いタイトルのアルバムです。フレッチャー・ヘンダーソンとは以前の記事でも取り上げた、あのフレッチャー・ヘンダーソン。ファンドとは基金の意で、このアルバムはフレッチャー・ヘンダーソンが病にたおれた際に、ベニー他の有志が集まって、彼の治療費のために吹き込んだアルバムがこれです。フレッチャー・ヘンダーソンはベニーにとって最大の恩人。なぜならヘンダーソンのアレンジを買い取ることによってベニーは「キング・オブ・スイング」という赫々たる地位につくことができたからです。このセッションはその恩返しの意味もあると解されます。もっとも背景にある美談だけで美しい芸術は生まれませんが、それにしてもここに聴かれるベニーたちの演奏には魂があります。このことは長くジャズを聴いてきた人にはすぐに分かることかもしれません。
録音は1951年4月1日で、場所はニューヨークの「メイク・ビリーヴ・ボールルーム」となっています。「見せかけの舞踏場」なんてしゃれたタイトルです。メンバーはベニー・グッドマン(cl)、テディー・ウィルソン(p)、ジーン・クルーパ(ds)のトリオの他、曲ごとにルー・マックガリティー(tb)、バック・クレイトン(tp)、エディー・サフランスキー(b)、ジョン・スミス(g)が参加しています。
1曲目 "China Boy" は昔からの得意曲で、ここはトリオ演奏。最初に出てくるテディーのピアノソロも、次に出てくるベニーのクラリネットも張り切っています。クルーパのドラムソロが燃え立つばかりで、そちらに耳を奪われますが、実に聴くべきは正確なバスドラ捌きで、そのためジーンのいた時ベニーのコンボにベーシストが入る余地はなかったといわれています。
2曲目は名スタンダード "Body and Soul" 。テーマ演奏からベニーとテディーの掛け合いが際立っています。本当はあまり仲がよくなかったという話もありますが、一級の芸術家においては個人的事情がさほど影響していないことがよく分かります。ベニーはサブトーンにまで降りていったり、単に名人芸といえないような心のこもった演奏をしています。それを受けるテディーのピアノも、まるでアート・テイタムを髣髴とさせる珠を転がすような演奏。
"Running Wild"は、スイング時代のチョッパヤ曲で、演奏する人の力量が試されますが、円熟の頂点に差し掛かりつつある3人には、むしろやりがいのある曲として写っているのか、すばらしく白熱した演奏です。途中でベニーが "One more, Gene" (ジーン、もう1コーラス行け!)と叫んで盛り上げ、炎上したままホットな演奏は終わります。
4曲目は "On the sunny Side of the Street" (「明るい表通りで」)。日記ブログにも書きましたが、この曲は最近リバイバルしているようで、CMにもよく使われますね。ここでベースのエディー・サフランスキーが加わり、彼のベース・ソロを大きくフィーチャーしていますが、コーダに向かってブルージーに崩していくベニーもなかなかのもんです。
5曲目の "After You've Gone" は、モダンジャズになってもいくつかの曲でそのコード進行が使われる名スタンダード。今度はベースに加えてギターのジョン・スミスが参加し、熱いギター・ソロを展開します。そしてA面のハイライト、 "Basin Street Blues" が登場します。ここで聴かれるベニーの力強いクラリネット・ソロはエリントン楽団のラッセル・プロコープを意識したかのようなソウルフルなプレイです。この曲に参加したボントロのルー・マックガリティーも、ジャック・ティーガーデンに匹敵するような心のこもったブルース・ソロを展開しています。
B面冒頭は、ベニーの得意曲でチャーリー・クリスチャンとの因縁浅からぬ、スイング時代の名曲 "Rose Room" です。この演奏で聴かれるような「ダウンしていく感じ」のベニーは極上で、単なるテクニック自慢に陥っていません。おそらく旧友達との再会と演奏の主旨が彼に火をつけたのでしょう。
2曲目はこれもスタンダードの "Honeysuckle Rose"。ミュートを噛ませたバック・クレイトンのトランペット・ソロが実に素晴らしい。ギターも"もろ"バップというほどではないにせよ、かなりモダンな味付けを加えた名ソロ。テディーのピアノは華麗そのもの。本アルバムのトップといっていいトラックです。やはりB面2曲目の伝説は正しかったのかもしれません。
3曲目 "I've Found a New Baby" は、私がシカゴ病に罹っているときに捜し求めた曲。ここでは、そのマイナーキーを利用して、ベニー達が「シング・シング・シング」から「クリストファー・コロンブス」にいたる展開を再現し、観客もどよめいています。
そしてラストはジャム・セッション風の "One O'clock Jump"。ベイシー風の簡素なピアノを経てソロ・オーダーはバック・クレイトン→ベニー・グッドマン→ルー・マックガリティー→テディー・ウィルソン→ジョン・スミスと続き、最後はジャムセッション風の集団即興演奏で盛り上がり幕を下ろします。この演奏でもジーンのドラミングが強力な推進役になっています。
こうしたいかにも「知る人ぞ知るLP時代の名盤」といったアルバムはなかなかCDで再発されないのですが、今回グレン・ミラーと抱き合わせで出ていたので、下に紹介しておきます。4枚組みCDですが、グレン・ミラーも聴けるお徳用盤です。
Tags: big band · Goodman, Benny
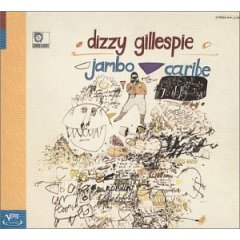
「暑くなると涼しい音楽が聴きたくなる」、なんてことは毎年書いているような気がします。おととしの夏はこんなマクラでスタン・ゲッツの『ウェスト・コースト・ジャズ』を紹介し、昨年はあまりに暑かったので、開き直ったかのように『ディッピン』を紹介していました。
暑い時のラテン・フレーバーといえばボサノバですが、今回はカリプソを紹介したいと思います。アルバムはディジー・ガレスピーの『ジャンボ・カリベ』。このアルバムの1曲目 "Fiesta Mojo" を聴いたのは、私がジャズにのめり込むきっかけとなったラジオ放送であるということは以前の記事で書きましたが、実際にアルバムを手に入れたのはずっと後のこと、CD時代になってからのことでした。
メンバーはディジー・ガレスピー(tp)の他、ジェームス・ムーディー(ts & fl)、ケニー・バロン(p)、クリス・ホワイト(b)、ルディー・コリンズ(ds)、そしてカンザス・フィールド(perc)で、1964年11月の録音です。
1曲目にして初めてディジーに接する曲となったのが "Fiesta Mojo"、『呪い士の宴会』という意味だそうすが、作曲はディズ本人。ちょっとおどけたかのように大袈裟なオープニングから、楽しいカリプソのリズムに乗ってテーマが登場。カリプソのリズムであっても、コード感豊かなバップのメロディーです。ソロはケニー・バロンのピアノからスタート。続くディジーのソロは私にとって「それまでのジャズとモダンジャズ」との違いをまざまざとみせつけるものでした。響きが軽くて緊張感があるんですね。バップの特徴です。ジェームス・ムーディのフルート・ソロを経てテーマに戻ります。
2曲目の "Barbados Carnival" はベースのクリス・ホワイトによる曲。「アーハ」というコーラスに乗って、畳み掛けるようなリズムが演奏されますが、これは西インド諸島のバルバドスでクリスが経験した音楽だそうです。
3曲目の "Jambo" はディジーの作曲で、イメージとしては「アフリカ」「カリビアン」そして「バップ」を融合させた、当時のしてのフュージョンです。いきなりディジーのスキャットで始まりますが、ディズのスキャット好きは昔からで、サッチモとスキャット合戦をやったときも、サッチモに「唾がかかる」と即興でからかわれながら楽しそうに演奏していました。ディズのアドリブはアフリカはアフリカでも、北アフリカ、イスラム圏のようなフレージングを繰り出し「チュニジアの夜」作曲者としての面目躍如です。
"Trinidad, Hello" は、"Nica's Dream" などに通じる、マイナー調の「ド」ハード・バップ曲。作曲はケニー・バロン。トリニダード(国名)と "tri" (3つまり3拍子)をかけた洒落っ気のあるタイトルですが6/8で演奏されていますが、わりとど真ん中の演奏で、ラテン・リズム一直線のアルバムが陥りがちな「ダラっとした」感じにならぬように締めています。
5曲目の "Poor Joe" はカリプソ作曲家のジョー・ウィロビーによる曲で、西インド諸島の「結婚の歌」だそうです。「気の毒なジョー」というタイトルにふさわしく、最後は細君にフライパンを投げつけられて「アー」といって倒れるところまで、ディジーが歌っています。
6曲目の "And Then She Stopped" はディジーの曲。綺麗なラインの曲でジェームス・ムーディーが大活躍です。
7曲目 "Don't Try to Keep up with the Joneses" は再びジョー・ウィロビーの曲。歌はディジーとクリス・ホワイトの掛け合い、そしてアン・ヘンリーが後半登場します。ディズがメインの歌ですが彼の歌う音の強弱がはっきりしすぎてていて、強いところは歌っているというより怒鳴っている感じがします。
最後は再びケニー・バロンの "Trinidad, Goodbye" ですが、今回は4ビート。素晴らしく中心的な演奏で、このアルバムを締まったものにしています。この4曲目と8曲目、つまりLP時代のA面B面の最後に、彼らの「こころざし」を感じるわけです。8分超の名演。これを聴くと、ディジー・ガレスピーが日本でいかにアンダー・レイティッドかを痛感します。
Tags: Gillespie, Dizzy · trumpet

バド・パウエルには大学のように「前期」と「後期」があって、前期はもう天才の極地。次から次へとフレーズが飛び出るし、どんなにチョッパヤでもものともせずガンガン進んでいた時期で、アルバム的には『バド・パウエルの芸術』、『ジャズ・ジャイアント』、『ジニアス・オブ・バド・パウエル』それに、ブルーノートの『Vol.1』『Vol.2』などを指します。一方、後期とは上記のアルバム以外の時期を指し、天才性の閃きに翳りが出てきたとか、指がもつれるようになったとか、精神に異常を来たしたとか色々言われていますが、要は前期ほどの輝きや興味を持てなくなった時期を指します。
もっとも、日本で人気の「クレオパトラの夢」は後期作品のアルバムに属しているし、後期にも波があって、いい時期と悪い時期があることは油井先生が指摘している通りです。今日紹介するのは、後期も後期、1962年にストックホルムのクラブ「ゴールデン・サークル」で録音された『アット・ゴールデン・サークル』全5集のベスト盤です。バドの『ゴールデンサークル』は名盤なんですが、何せ5枚もあるし、重複曲も多いし、うめき声がいつも以上だし、そもそも評判の悪い後期だし、ということで知る人ぞ知るといった位置に落ち着いています。その中から選りすぐったベスト盤ということで、バドの全キャリアを通じてのベスト集ではないことを断っておきます。また、未発表盤からも4曲ほど取られています。
録音は1962年4月19日と23日、および9月という記録です。メンバーはバドの他、ドルビョン・フルトクランツ(b)、スーネ・スボングベリー(ds)となっています。地元のミュージシャンでしょうか。時期的には大江健三郎が「老いたセイウチ」とたとえた時期と重なるかもしれません。
いつも通り1曲づつ紹介してもいいのですが、このアルバムに関してはそれを避け、特筆すべきトラックについて書きたいと思います。
まずは2曲目の "I Remembaer Clifford"。音楽が止まりそうで止まらない、ギリギリのところで圧倒的に成立している名演です。以前、若い友人と一緒に音楽を聴いていて、ある音楽家(いわゆるアイドル)の演奏に関して「この音楽は止まっているね」と言ったところ、「どういうことだ?」と質問を受け、音楽が止まる感覚が分からない人もいるのかと気づきました。ということでここに私なりの考えを書いてみたいと思います。
「音楽が止まっている」というのは、休符と関係します。休符を無意味に休んでいるような音楽は、どこか「止まっている感じがする」。仮にインテンポでも休符で気を抜いた途端、音楽は止まります。ドラムやベース、ポップスなら打ち込みがステディーなビートを刻んでいるので止まりそうになくても、やっぱり休符での気の抜き具合が伝わってくるような時、つまり、休符以前と休符以降がブッツリと切れているような時、私は「止まっている」と表現します。
ジャズだと、普通にやっていれば止まらないんですが、あまりにもテンポを落とすと、休符に漂う緊張感いかんで、止まって聴こえる時がある。バドのこの曲の演奏はテンポが遅すぎて=休符の間が長くて、普通なら止まって聴こえそうなほどの演奏なんですが、流れていく。理屈としては、おそらく音楽の底流に細分化された急速なビートが流れているんでしょうが、分かりやすくいえば、休符を休んでいない、休符こそ歌っているわけです。
おそらくもうボロボロだったと思うんですね、この時期のバドは。全盛期に比べて指も動かないし。にもかかわらず、音楽になっているのはこの点あるんじゃないかと思うわけです。同じことは、もう少しテンポは上がりますが、 "Like Someone in Love" にも当てはまります。この曲といったらバドを抜きには語れないほどはまった演奏です。
この時期のバドは、うなりつつ口をモグモグさせていた、いわゆる「モグモグのバド」です。
いずれにせよ『ゴールデン・サークル』は枚数が多い上に、散漫なところもあり、こういうベスト集は本当に助かります。これで全体を俯瞰した後、1枚づつ買い揃えていくのがかしこいやり方だと思います。このアルバムの魅力にはまれば、立派なバド・ファンです。いまは廃盤ですが、丁寧に中古店を当たれば必ずあります。ジャケは上の画像を参照。
Tags: piano · Powell, Bud

『フルハウス』で共演したウェス・モンゴメリーとウィントン・ケリーは相性がよかったのか、このライブ盤で再び名演を繰り広げます。
録音は1965年6月と9月。場所はライブ録音がニュー・ヨークのクラブ「ハーフ・ノート」でスタジオ録音がヴァン・ゲルダー・スタジオ。メンバーはウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、ジミー・コブ(ds)のウィントン・ケリー・トリオにウェス・モンゴメリー(g)が加わった形になっています。
まず、何はともあれ1曲目の "No Blues" です。ウィントンはイントロの天才だけれど、ここでもまたその天才性が発揮されて「絶対名演になる」という感じのイントロ。トップ・バッターはウェス。畳み掛けるようなシングルトーンによるリフをしつこいぐらい繰り返して演奏のボルテージを高めていき、同時にグループの一体化(グルーヴ感)を構築するや、オクターブ奏法に切り替えスリリングなソロを展開。続いてコード奏法に移る。この展開を何コーラスにもわたって繰り返し、ソロ全体が大きなリフのようになっていますが、間然とするところは全くありません。ウィントンも伴奏をしながらウェスに聴きほれているような風情がします。続くウィントンは全盛期ほどの迫力はありませんが、ウェスと同じくしつこいようなリフを、珠を転がすようなタッチで弾いていきます。途中ウェスの合いの手に応えたりと充実したソロです。ポール・チェンバースのベースソロを経て合奏に戻って終わり。13分にわたる熱演ですが、スリリングな展開に時間を忘れ、あっという間に終わったような感じがします。
2曲目のバラード "If You Could See Me Now" はトリオによるドラマティックなテーマ演奏に続いて、ウェスのギターが先発。これがまたいい。レイド・バックした感じのゆったりとした展開の中に恐ろしいまでのテクニックをきっちり詰め込み、精緻を極めたソロになっています。この辺がグラント・グリーンとの違いでしょうか 8) もっとも、グラント・グリーンも好みなんですがね。ウィントンのソロはそのままエンディングに入っていくような感じで、ドラマティックなソロ。
3曲目 "Unit 7" はベーシストのサム・ジョーンズによる作品。ウィントンが先発して華麗なソロを展開。その後登場のウェスは非常にエキサイティングです。
4曲目の "Four on Six" はウェス・オリジナルで「サマータイム」のコード進行を使っています。ウェスのソロは自分のオリジナルということもあって実に素晴らしい。ギター奏法のショーケースといっても過言ではありません。ウィントンは元歌「サマータイム」のメランコリックな気分がよく表れたソロです。ポールのソロはアルコ弾き。ジミー・コブのドラムソロまで付いています。最後の合奏で聞こえるのは歴史的な録音『ミントンズ・ハウスのチャーリー・クリスチャン』の "Swing to Bop (Topsy)" に聴かれるフレーズですね。
ラストはスタンダードの "What's New?"。ウェスによるこの曲のテーマ演奏を聴くと、彼のバラード解釈がパット・マルティーノにダイレクトな影響を与えていることが分かります。ウィントンのソロになるとイン・テンポに転じ、ドラムがステディーなビートを刻んでわりと明るめの雰囲気に変わります。その雰囲気を保ったままウェスがソロを半コーラス取りテーマに戻ります。味わい深いバラードだと思います。
『フル・ハウス』、『インクレディブル・ジャズ・ギター』と並ぶウェスの名盤。
Tags: guitar · Kelly, Wynton · Montgomery, Wes · piano

久々にCDを購入しました。このCDはサッチモのコンピレーションで『ハロー・サッチモ! ミレニアム・ベスト 』と対になったものです。このアルバムも、今回買ったアルバムもその音源はほとんど網羅しているのですが、こちらでフィーチャーされている "Yellow Dog Blues" や "St. Louis Blues" の収められた『W.C.ハンディー集』のLPをこの前取り出したら激しく黴が生えていて、あわててクリーニングしたものの溝に跡を残したらしくブチブチいうので困っていました。今回セールで安く買えるというメールが届いたので求めることにしました。このアルバムは権利関係を調整して、さまざまなレーベルから選り抜かれた名曲のコンピレーションです。
』と対になったものです。このアルバムも、今回買ったアルバムもその音源はほとんど網羅しているのですが、こちらでフィーチャーされている "Yellow Dog Blues" や "St. Louis Blues" の収められた『W.C.ハンディー集』のLPをこの前取り出したら激しく黴が生えていて、あわててクリーニングしたものの溝に跡を残したらしくブチブチいうので困っていました。今回セールで安く買えるというメールが届いたので求めることにしました。このアルバムは権利関係を調整して、さまざまなレーベルから選り抜かれた名曲のコンピレーションです。
1曲目 "What a Wonderful World"、邦題『この素晴らしき世界』はあまりにも有名でほとんどの人がご存知だと思います。私もずっと昔からこの曲を知っていましたが「綺麗な曲だな」といった程度の認識で、それほど強い関心はありませんでした。この曲の本当の力に気づかされたのは映画『グッド・モーニング・ヴェトナム』でこの曲が使われるシーンを観たときです。まさにこの歌の歌詞通りの美しい田園がアメリカ軍の北爆で焼かれ、ヴェトナムの青年達がゲリラの疑いで裁判手続きを経ることなく射殺されていくシーンのバックにこれが流れているわけです。何たる皮肉、いや皮肉という言葉を超えて悲劇がそこにはありました。
実際『グッド・モーニング・ヴェトナム』がきっかけとなってこの曲は再ヒットしたそうです。
2曲目 "Do You Know What It Means to Miss New Orleans" は映画『ニューオリンズ』の挿入曲で、映画ではビリー・ホリデイも歌っていますが、このヴィクター吹込みではビリーを除いたメンバーでの演奏。3曲目の "Our Monday Date" は歴史的な1928年のアール・ハインズとの吹込みではなく、タウン・ホール・コンサートからのもの。
さて4曲目の "On the Sunny Side of the Street"、邦題『明るい表通りで』がこれまたナミダモノ。レスター・ヤングの記事でもかつて書きましたが、レスターの同曲と同じく、明るくて暗い、楽しくて寂しいといったニュアンスの素晴らしさが圧倒的に迫ってくる名演、絶演となっています。
5曲目の "I Surrender Dear" はスタンダード。バニー・ビガードのクラリネットとルイのヴォーカルが全面にフィーチャーされています。
そしてお目当ての "Yellow Dog Blues" と "St. Louis Blues" は『ルイ・アームストロング・プレイズ・W.C.ハンディー』というコロムビアのアルバムからの2曲。両曲ともベッシー・スミスの名演で知られ、「セント・ルイス」のほうでは若き日のルイが伴奏を勤めていますていますが(「イエロードッグ」はジョー・スミスが伴奏)、ここでのサッチモもほとんど頂点を極めたといってもいいような演奏です。「イエロードッグ」における、畳みかけとクライマックスへのもって行きかた、そして上でも書いたニュアンスは比類なきものです。「セント・ルイス」もこれに次ぐ名演で、本来の曲では第2部にあたるハバネラの部分を冒頭に持ってきて、エモーショナルに歌い上げた後、ルイ・プリマという巨漢の女性のボーカルからルイの歌、そして掛け合いへとコミカルに進んでいく、いわゆるアンチ・クライマックス(漸減法)を取りつつ、ラスト・コーラスの合奏ではルイがハイノートを駆使して演奏を盛り上げて終わります。
8曲目の "Basin Street Blues" も1928年の伝説的な吹き込みの一角をなす曲ですが、このアルバムに収められているのは、映画『グレン・ミラー物語』のサントラ音源だそうです。ベイブ・ラッシン(ts)がホーキンス流丸出しのソロを取っていて微笑ましい。ラスト近くでジーン・クルーパのドラムソロが聴かれます。
次は名盤『エラ・アンド・ルイ』からの2曲、 "Cheek to Cheek" と "Nearness of You" です。エラ・フィッツジェラルドというと『イン・ベルリン』の派手なパフォーマンスが圧倒的で、私も最初はこのアルバムが好きだったのですが、聴きなれてくると飽きる。一方ここに聴かれるエラは抑えた味わいが深く、いつまで経っても飽きない歌だと思います。続く11曲目もエラとルイが組んだアルバム『ポギーとべス』から、もちろん "Summertime"。 これも本当に名演です。
12曲目 "When It's Sleepy Time Down South(「南部の夕暮れ」)" はロスのクラブにおけるライブ録音。この曲は彼のバンドのテーマ曲だったそうです。そしてルイ晩年の最大ヒット曲 "Hello, Dolly!" が続きます。このブログのプラグインにも "Hello Dolly"というのがあって、管理画面の上にこの曲の歌詞が出てきます。
14-16は "What a Wonderful World" と同じアルバムに収録されていたものでルイ最晩年の1968年の吹込みから。もはや特に新しいことに挑戦することもなく、トランペットもかろうじて吹いているといった時期ですが、歴史と経験からしか醸し出せない実に味わいのある演奏です。
最後はサッチモのディズニー集から "When You Wish upon a Star (「星に願いを」)"。これも68年の吹き込みですが、やはりルイの人柄、やさしさがにじみ出た歌になっています。
ジャケットは藤子不二雄(A)先生。「どーん!」といってトランペットを吹いてそうなサッチモです 🙂
Tags: Armstrong, Louis · trumpet