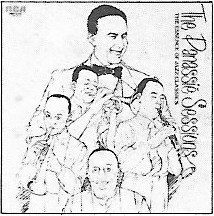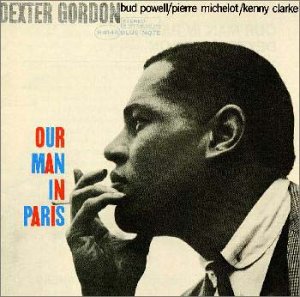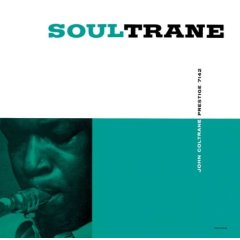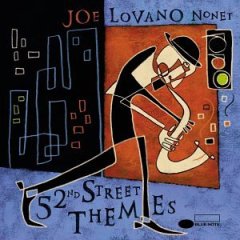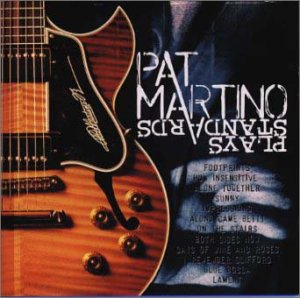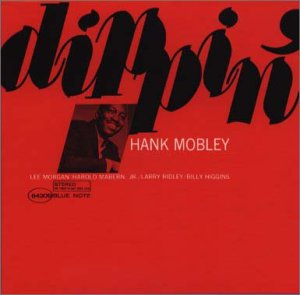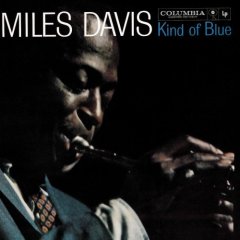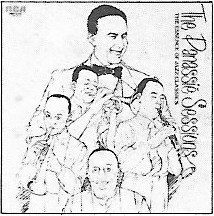
こういう選集を編めるところに日本のジャズ研究者やファンのレベルの高さが表れているんじゃないかと思える一枚です。面白いことに "panassie" のワードでAmazon USを検索してみると、"Import" つまり輸入盤で本作がヒットします。案外、日本のほうがジャズに対する理解が深いのかもしれませんが、これは今に始まったことではなく、このアルバム自体が、アメリカ以外の国におけるジャズ理解の深さを示しているわけです。本作のライナーノーツで、油井先生はこのセッションの由来について次のように書いています。
ユーグ・パナシェ(1912-74)は、フランスの古城に住む足の不自由な青年だったが、ジャズ界に最初に現われた偉大な評論家であった。わずか22歳で書いた "Le jazz hot" (英訳)『ホット・ジャズ』は、まさに啓蒙の書であり、この本によって、アメリカを含めてジャズははじめて知識人の鑑賞の対象となったのであった。私自身この本によって人生を変えられたひとりであり、感動した初版英訳本は未だに大切に保管している。
このパナシェが1938年、RCAの求めに応じて、はじめてアメリカに渡り、4セッション17曲を監修した。
この渡米を聞いたエディー・コンドンは「おいおい、フランスの若造が俺たちにジャズのやり方を教えに来るとよ。俺たちもフランスに葡萄酒の作り方を教えに行くべえか」といった。この毒舌は今も昔も変わらないアメリカ人気質を表している。ジャズを生んだのはアメリカ人だから、アメリカ人以上にジャズを知っている国民はいないという自信である。
しかしアメリカに任せておいたなら、トミー・ラドニア(1900-39)の偉才は、永久に埋もれたままになってしまったろう。またテディー・バン(1909-78)のソウルフルなギターとヴォーカルが、当時のファンを感動させたのも、このセッションによってであった。
パナシェ・セッションは、1938年という時点で全く知られていなかったニューオリンズ・アンサンブルの力強さと醍醐味を、意識して採り入れた点で、シドニー・ベシェ=ラドニアの「ニューオリンズ・フィートウォーマーズ」の諸作と共に、歴史的な価値を残したといえる。
ジャズ研究者の眼がジャズ誕生の地ニューオリンズに向けられたのは、このレコードが世に出たことが契機になっており、名著『ジャズメン』の出版(1939年)によって、バンク・ジョンソンやジョージ・ルイスの再発見につながったのであった。
その4セッション17曲が収められたのがこのレコードです。最後の「バンク・ジョンソンやジョージ・ルイスの再発見」とは、すなわち「ニューオリンズ・リバイバル」のことです。ジャズの最初期の姿は録音が残っていなかったために分からなかったものが、彼らの再発見によって明らかになったわけです。再発見というのはこの二人がミュージシャンではなく、それぞれトラックの運転手と沖仲士をしていたためです。しかしこれが却って幸いし、最初期の姿を保つのに役立った。というのも、彼らがプロのミュージシャンを続けていたら、時代と共にスタイルも変化して原形をとどめていなかったであろうからです。
このアルバムの聴き所は、まず2曲目 "Really the Blues" です。プレイ・バックを聞いたメズ・メズロウ(cl)が涙を流し「こんなブルースらしいブルースを聴いたことがない」と言ったそうです。タイトルはそこからつけられています。
4曲目 "Weary Blues" はシドニー・ベシェとトミー・ラドニアのニューオリンズ・アンサンブルが力強く、このアルバムでも屈指の名演。
8曲目の "If You See Me Comin'" は、上で油井先生が触れていたテディー・バンのギターと歌が聴ける感動的なブルース。
11曲目 "Come on with the Come On" には面白いエピソードが残っていて、トミー・ラドニアと共演者のシドニー・ドパリスとの間に揉め事があった喧嘩セッション。以下はライナーノーツから:
パナシェのアイデアはキング・オリヴァーのレコードにきく、2トランペットを再現することであった。相手がシドニー・ドパリスと聞いた途端、トミー・ラドニアは一瞬いやな顔をしたという。ドパリスはニューオリンズ・スタイルではなく、スイング・イディオムで育った。当時としてはモダンなスタイルだったので、パナシェは充分に意図を話してスタジオに入れたのだが、コーラスが進むにつれて、ドパリスはリフやグロウルを入れ、ラドニアが怒り出して妙な音を出したり、吹き止めたりして、結局のところ、失敗作となってしまった。
聴いてみると、そんなに破綻してはいないようですが、確かに「ニューオリンズ・スタイル」とは呼べないような演奏になっています。
16曲目 ""The Blues My Baby Gave to Me" は、以前に紹介した『ジャズの歴史』にも収録されていた演奏ですが、フランキー・ニュートンのシンプルなトランペットが味わい深い1曲です。
このアルバムはJazz Masters SeriesというシリーズでCD化されましたが、現在のところ廃盤になっているようです。再発を願って下にCDへのリンクを張っておきます。収録曲に関しては、以前にアップロードしたジャズ栄光の巨人たちのカタログでも分かります。
Tags: various artists

このジャケット・・・・社会活動に熱心なオバサンにこういう顔した人いますよね。このジャケットはCDになってよくなった(サイズが小さくなったから)ものの一つでしょう。私は残念なことにLPで持っています 8) きっかけはタモさん司会の昭和の名番組『今夜は最高!』にゲストとして出ていたジャズ・シンガーの金子晴美さんが「私がジャズ・シンガーを目指したのは、エラの "How High the Moon" を聴いたことです」とおっしゃっていたからです。一人の人間の人生の方向を変えるほどの力を持ったアルバムなら聴いてみたいと思い、早速千葉市で買いましたが、ジャケットを見て一瞬躊躇したのは事実です・・・
CDだと「完全版」と銘打って、MCや追加曲も含まれているようですが、私のLPにはありません。追加曲は "That Old Black Magic", "Love Is Here to Stay", "Love for Sale" そして "Just One of Those Things"の4曲です。
さて後半2曲、すなわち "Mack the Knife" と "How High the Moon" がこのアルバムのハイライトとなるわけですが、これはさすがに凄い!私も最初聴いたときはぶっ飛びました。「マック・ザ・ナイフ」は途中から歌詞を忘れ(たフリをし)て、"Oh What's the next chorus" と歌詞を作り変えてからが盛り上がります。ボビー・ダーリンやサッチモに敬意を評した歌詞に作り変えつつ声色を真似ていきます。サッチモのスキャットもそのまま真似ます。さすがです。これで会場を興奮の坩堝に叩き込んだエラさんは、続いて "How High the Moon" に取り掛かります。MC入りの完全版でも同じ曲順なので、この通りの順番で歌われたのでしょう。最初は気持ち速めのテンポで快適にスイングしながら歌詞を1コーラス歌います。そのあとドラムがフィルインしてテンポが速くなり、作り変えた歌詞をちょこっと歌ったあとスキャットに入り、いろんな曲を引用します。最初は "Ornithology"。まあ「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」のコード進行を使った曲だから当然といえば当然でしょうか。その後「モップ・モップ」、「南京豆売り」、「ティスケット・ア・タスケット」、「ソルト・ピーナツ」、さらにはヨーデル、「ヒート・ウェイブ」、アラビア風の歌、そしてコーダは「煙が目に染みる」になっています。これらを一分の隙や停滞もなく展開していくところは圧巻です。
エラは前もって準備して練習し、それを板にかけるタイプの歌手で、いわゆるその場のアドリブというわけではないのですが、それにしてもあのテンポで落ちることなく歌いきるのは、並大抵の歌手では不可能です。
このアルバムにも慣れてきてしまうと、最初の驚きは逓減して「ああまたか!」という気持ちになり、むしろサッチモとのデュオなどのほうが味があってよく聴くようになります。それでもまだ聴いたことがない人は聴いてご覧なさい。CDで買うのが勿体無ければ「マック・ザ・ナイフ」と「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」だけでもお聴きなさい。
上記2曲以外では「サマータイム」がとても優れた演奏です。
ちなみに冒頭で『今夜は最高!』について触れましたが、別の回で(確か泰葉さんがゲストだった時)この「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」のスキャットに別の歌詞を載せてタモさんや泰葉嬢などがリレーで歌っていました。ものすごい番組ですね。
Tags: Fitzgerald, Ella · vocal
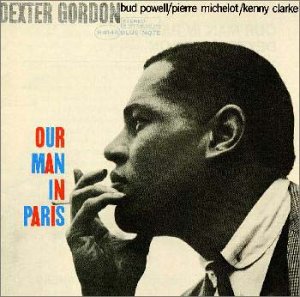
イギリス人の老婆が名作と聞かされて『ハムレット』を見た後、感想を聞かれてこう言ったそうです:「何が名作なものかい!諺を引用してつなぎ合わせているだけじゃないか?」実際には、『ハムレット』が出典となって、後に諺となったわけですが、面白いエピソードだと思います。デクスター・ゴードンを聞くと、同じように色々なフレーズが引用されていることに気づくわけですが、彼の場合はシェークスピアとは違って実際に引用しているわけです。あまり引用が多いので、テーマに戻ったとき、「ずいぶん長い引用だな、丸々1コーラス引用しているじゃん!」と思ったことすらあるほどです。まあ作り話ですけれどね・・・ 8) しかし、デクの特徴はずばりこの引用フレーズとあまり細かいことは気にしない吹き方です。したがってデクファンの人は、引用フレーズが出るたびに「また出た!」といって喜ぶわけです。
このアルバムは1963年渡仏した折、すでにパリに居を構えていたバド・パウエルやケニー・クラークらとともに吹き込んだ演奏です。最初の予定ではケニー・ドリューが参加するはずでしたが、急遽バド・パウエルが参加したものの、バドの精神状態のせいで新曲を演奏できず、手馴れたスタンダードとバップ曲を演奏することにしたそうです。
1曲目 "Scrapple from the Apple" は "Honeysuckle Rose" のコードを使ったパーカーの曲。非常に勢いがあり、デクは競馬のファンファーレやブルースでよく用いられるリフ、さらに4バースでは「52丁目のテーマ」の一節を自在に引用しながら目くるめくアドリブを展開します。
2曲目の "Willow Weep for Me" はもともとがブルースっぽい進行を持っている曲ですが、けだるい感じでぶっきらぼうな演奏をします。テーマの吹き方からして独特です。フレーズ終わりの全音符や2分音符は単調さを避けて吹くものですが、ここでのデクは「ブッブー」とワンパターンに吹きます。しかしこれがデク独特の雰囲気をもたらして、結局やったもん勝ちのようなところで圧倒的に演奏が成立しているわけです。アドリブに入ると「オールマン・リバー」などを引用しながらレイドバックしてくつろいだソロを展開します。
3曲目の "Broadway" はベイシーのところでやったレスターの演奏が有名ですが、デクも出発点はレスターでした。アドリブに入るといきなり単音の繰り返しというロリンズ流の入り方をします。盛り上がってくるとオルタネート・フィンガリングを使ってみたりベンドさせてみたり、ハーモニックス(フラジオ)を出したりと、サックス奏法のショーケースのよう。このアルバムのハイライトと言ってもいいでしょう。エンディングのバドがカウント・ベイシー・スタイルのなのも楽しい。
4曲目 "Stairway to the Stars" はデク流バラード解釈の典型で、"Willow Weep for Me" と同様、伸ばすべき音を「ブッブー」とぶつ切りにしています。彼のバラードは甘さを排除して、決してムード・テナーに陥らないものです。
5曲目のバップ・チューン "Night in Tunisia" では「サマータイム」のフレーズや中東風のフレーズを出したり、パーカッシブトーンを使ったりと、やはり乗りに乗っています。バドのピアノソロ、ケニー・クラークのドラムソロもよい。
ケニー・クラークというドラマーは手数というかおかずが多くて、時にうるさく感じられるのですが、ここではデクがわざと単調でぶっきらぼうな吹き方をしているので、それを上手く補って相性がよく聞こえます。バドは中ぐらいのコンディション。ただコンピングだけでもバドだと分からせる個性はさすがです。ベースはフランスの名手ピエール・ミシュロ。この人は映画『ラウンド・ミッドナイト』でもデクと共演しています。
このアルバムは曲の親しみやすさ、メンバーのよさ、デクスターの個性が全開と非常によく出来た作品です。下のCDにはレコード時代にはなかった2曲が追加されているようです。最後の "Like Someone in Love" はバドのトリオ演奏かもしれません。
Tags: Gordon, Dexter · Powell, Bud · tenor sax

コルトレーンの "My Favorite Things" はメディアジェニックな曲なのかも知れませんね。以前にタモさんがNHK-FMの特番でやったジャズ番組のテーマ曲がこれでした。また、伊東四郎主演のテレ東サスペンス「狂った計算?灼熱のニュータウン殺人事件」でも、この曲が重要な役割を果たしていました。聞き込みの最中に「忌中」の張り紙が貼られた家を訪ねると、別の部屋から「マイ・フェイバリット・シングス」が流れていて奇妙に思う伊東四郎演ずる近松丙吉が、徐々に犯罪を暴いていくストーリーで、この曲が事件を解くポイントとなっていました。またクラシックの赤坂達三(cl)の同曲がJR東海のCMで流れていることはご存知の人も多いと思います。
さて、ミュージカルの傑作といわれる『サウンド・オブ・ミュージック』から出たこの他愛ないといえば他愛のない曲を、コルトレーンはモーダルに解釈して全く異次元の演奏に仕立てます。まるでアラビアやインドの呪術的な音楽のよう。しつこいしつこいスケールの畳みかけがそれを助長します。またこれらが組み合わされたせいで、コルトレーンの吹くソプラノ・サックス自体がシャナイというインドの民族楽器のような音色を感じさせるわけです。これが一種のコルトレーン・マジックです。
シャナイの音色(.wav)
ソプラノ・サックスはシドニー・ベシェ?スティーブ・レイシーという偉大な例外を除けばジャズの世界ではそれほど用いられていなかった楽器ですが、コルトレーンがここで復活をさせます。この楽器、ピッチが取りづらい上にポジションによって音色のばらつきが激しい楽器なのですが、コルトレーンの棒状態が上手く作用して(本当は猛練習したんでしょうが)このアルバムでのトレーンは音痴ではなくなっています。高いところが弱いコルトレーンでしたがソプラノはもともと高いですしね。
A面2曲目の "Everytime We Say Good By" も雰囲気があっていいですが、これはほとんどメロディーしか吹いていないですね。ここではソプラノのせいもあって高域の怪しさも消え、棒吹きもこのコール・ポーターの曲想にあって名演に仕上がっています。
B面1曲目の "Summertime" はテナーに持ち替えています。音数の多いコルトレーン・スタイルで吹き上げています。これは「サマータイム」の演奏としてはシドニー・ベシェ、パーカーに並ぶ屈指の名演だと思います。これに匹敵するのはむしろジャズではなくて、ロックのジャニス・ジョップリンぐらいかもしれない。エルヴィンのソロも歌いに歌っています。
最後の曲 "But Not for Me" もテナー。しかし「フシが違うよ」と言いたくなるようなテーマの吹き方。これは原曲のよさがあまり出ていない割りに、コルトレーン独自の味付けもなくて野暮な演奏です。(2017年追記 こう書いたけれど、聴きなおすとこれはメロディーは保ちつつコードの方をジャイアントステップスに変えている野心作だと気付いた。それが成功しているかどうかは別として)
CDではLPにはなかった「マイ・フェイバリット・シングス」の別テイクが収録されているようです。
Tags: Coltrane, John · tenor sax
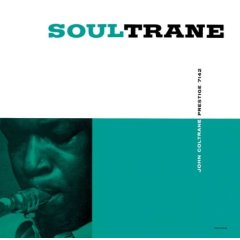
コルトレーン・ファンには猛烈な人も多くて、むかし「ディグ」だか「イントロ」だかでコルトレーンのことで揉めて、ビール瓶を割って相手の胸に擬した、なんておっかない話を聞くとコルトレーンのことは穏便に語っておいたほうが無難かなとも思います。特に私の場合、インパルス後期がダメなのですが、そんなこと口にでもしようものなら、猛者たちから「じゃあ、『バラード』でも聴いてろ!」と怒られそうで、おまけに『バラード』が「後期」以上に好きではないので、口答えしてしまいそうで怖いわけです。もっとも、そんな事件はかなり昔の話で、今では「ジャズファンの決死隊」みたいなことしている人はいないから大丈夫でしょう。
「コルトレーンの音痴ジャズ」と言ったのは寺島さんですが、これは言いえて妙です。後期の精神世界を除いてコルトレーンの欠点といえるのものが、高域での音痴ぶりとバラードの棒吹きです。高域のほうは徐々に直ってくるし、ソプラノに持ち替えてからは気にならなくなります。棒吹きは、一番つくづくなのが件の『バラード』で、これはひどい。しかし物によっては表情豊かなバラードを吹いている例もあって、このアルバムも二つのバラードで魅せられるアルバムです。
その1つが2曲目の "I Want to Talk about You"。冒頭いきなり頓珍漢というか素っ頓狂な音から始まります。「ああ、大丈夫かなぁ」と心配が頭をよぎりますが、テーマもたどたどしい吹き方。サビの一番高いところなんか音が痩せちゃってますよ。しかし、アドリブに入るとそのたどたどしさが逆に効果を発揮して味となっていきます。畳み掛けるようなフレーズも非常に魅力的に響きます。そのあと、なぜか異常に長いピアノソロ(2コーラス)とベースソロ(1コーラス)のあとサビからコルトレーンに戻ってカデンツァを吹ききり、コーダに入ります。この曲とは余程相性がよかったと見えて、後に何度か吹き込み『ライブ・アット・バードランド』では冒頭のカデンツァとともに名演となるのは多くの人がご存知の通りです。
もう1つが4曲目の "Theme for Ernie"。こちらは以前に取り上げたブルックス・ブラザーズのCDにも収録されていたバラードです。音痴度もたどたどしさもこちらのほうが良くなっているけれど、その分ちょっと平凡かな?という印象です。やはり頓珍漢でも素っ頓狂でも2曲目のほうが「らしさ」もあるし味わいも濃いと思いますね。
最後のスタンダード "Russian Lullaby" (ロシアの子守唄)は、原曲とはまったく違うチョッパヤでバラードではありませんが、これは「シーツ・オブ・サウンド」の典型といわれています。
メンバーはコルトレーンのほか、レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(ds)。下のCDは画像が出ていませんが紙ジャケで、音質も改良された盤なのでよいと思います。
Tags: Coltrane, John · tenor sax
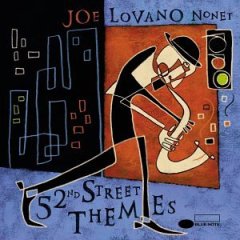
以前はジョージ・ガゾーン、ジェリー・バーガンジー、ジョー・ロヴァーノといったプロフェッサーズを頑張って聴いていましたが、結局興味をつなげずまとめて売り払ってしまいました。こういう人たちはいわゆるミュージシャンズ・ミュージシャンで、私みたいな素人が聴いてもあまり面白くない。理に走りすぎて情感や雰囲気に欠けるからです。そんな中で唯一手元に置いておいたのが、この 52nd Street Theme。
まずタイトルがよい。52nd Streetとは、マンハッタンの52丁目のこと。マンハッタンの場合南北に走る通りを "Avenue" (番街)と、東西に走る通りを "Street" (丁目)と呼ぶわけですが、52丁目は、40年代半ばまでジャズ・クラブがひしめき合い、あるクラブでチャーリー・パーカーがやっているかと思えば、隣のクラブではビリー・ホリデイが歌い、おまけに向かいのクラブではルイ・アームストロングがラッパを吹いている、といった文字通りジャズ・パラダイスでした。しかしある時期を境にこのジャズパラダイスは消滅します。52丁目の繁栄と衰退についてはマイルスが『自伝』で詳しく述べています。また、映画『バード』では、これを上手く映像化し、パーカーがニューヨークに戻ってみると今まであったクラブが全部ストリップ小屋に変わってしまって、彼が呆然とするシーンが印象に残ります。何か魔法が解けたように、「あの52丁目は」忽然と消え去ってしまったという印象を多くのミュージシャンが語っています。私自身この街の名前が好きで、以前持っていたレンタルチャットの部屋名も「52丁目」でしたし、このブログのミラー(ウェブリブログ)も"52nd Street"というタイトルで、URLもhttp://52street.at.webry.info/です。
次にノネット(9重奏団)なのでハーモニーが深い。最近はSharpのAquosのCMにしても、真矢みき嬢のウェラのCMにしても、ビッグバンド風のBGMで特に倍音成分も豊かなサックスのソリがフィーチャーされているものが人気のようですが、このアルバムも実に深いハーモニーで整然としたアンサンブルが聴けます。この方面で特におすすめなのが1曲目 "If You Could See Me Now" と2曲目 "On a Misty Night" などです。また11曲目と12曲目は相関関係にあって、11曲目 "Abstractions on 52nd Street" はロヴァーノのサックスソロ、それを受けてモンクの名曲 "52nd Street Theme" (52丁目のテーマ)につながるという趣向です。
ロヴァーノのワンホーン物だったらきっと他のものと一緒に売り払ってしまったと思いますが、このアルバムはアンサンブルとソロとの案分もよく、今でもたまに取り出して聴いています。現代版『クールの誕生』といったところでしょうか。
Tags: Lovano, Joe · tenor sax
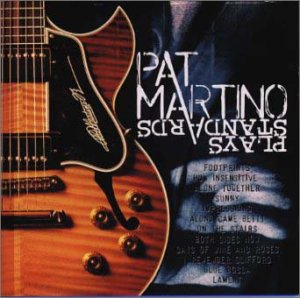
マイミクさんにもなってもらっている尊敬すべきギタリストのみきみきさんに「パット・マルティーノを聴くなら何がいいですかね?」と尋ねたことがありました。ちょうどオフミを兼ねたセッションで「酒バラ」をやる予定もあったので『イグジット』を紹介してもらい、早速買いに行きました。ところがこれが売ってないの。たぶん再発の端境期に入ってしまっていたのでしょう。仕方なしにレコード屋であれこれ見ていると、この『プレイズ・スタンダーズ』を発見しました。裏を見ると、これはコンピで上手いことに『イグジット』からも「酒バラ」を含む3曲が収録されていることが分かり、迷わずこれを購入しました。
家に帰って封を開けてみると、更に上手いことに「酒バラ」の譜面が入っていました。コピーしてみましたが、もう16分のところなんかお手上げなので8分でラインを真似たりしていました。同じ頃、ちょうどサックスの師匠から「酒バラ」でアドリブラインを作ってごらん、と課題を出されていて、B♭m?E♭7のトゥーファイブのフレーズで悩んでいたので、「サックスだしバレねぇだろう」と思いながらマルティーノのフレーズをコピーしたら、「なんだかギターみたいなフレーズですね」と見抜かれちまいました 8)
このコンピは5枚のアルバムから代表曲をピックアップしてまとめたものです。1?3曲目は Footprints から。私が特に好きなのはボサノバの "How Insensitive"。ジョビンの曲でテーマだけでも哀愁がありますが、そのムードを生かしながらもすごいソロを取るマルティーノには感服します。4曲目の "Sunny" 1曲は Live! から。ブルースのようなしつこい畳みかけが凄いです。
5?8までは Consciousness からの4曲。"Impressions" がなんといっても印象的です。ギターだとモーダルな曲の場合優れたフレーズ感が必要になるんですが、これは自然なソロが繋がる優れた演奏です。7曲目のオリジナル "On the Stairs" は、チョッパヤで正確なフレーズを繰り出すマルティーノの頂点を極めた作品だと思います。まあ、よくここまで弾けること!
そして9?11が Exit からチョイスされた曲です。みきみきさんが推薦するとおり、どれも凄い。9曲目が "Days of Wine and Roses" つまり「酒バラ」。しかし何なんでしょう、このテーマ。はっきり言ってぼんやりとした弾きかたです、ハキハキしていない。にもかかわらず、そのニュアンスが深い。だからテーマが終わってアドリブに入るところにでてくる16分がくっきりと際立つわけです。「酒バラ」をギターで弾く時はこう弾くべきだといえるような名演です。それに続くギル・ゴールドスタインのピアノソロも、ある種の潤みを帯びた音色で短いながらも優れたものです。10曲目の "I Remember Clifford"。 この曲はリー・モーガンのオリジナル以外だと、バド・パウエルの止まりそうで止まらない、ギリギリのところで圧倒的に成立する名演がありますが、このマルティーノも優れています。ある寒い冬の晩、ウォークマンにこの曲を録音したテープを入れて聴きながら歩いていたら、マルティーノのアドリブの部分で不覚にも涙を流しました。寂しさの本当の意味を知る男の演奏なのでしょう、一種のハードボイルド的ソロです。それに続くゴールドスタインも哀愁のある音色で涙を誘うソロを取っています。
最後の12曲目 "Lament" はJ.J.ジョンソンの曲で、これまた哀愁のある名曲です。アルバム We'll Be Together Again からの1曲。エレピを弾くゴールドスタインとのデュオでしみじみとした演奏に仕上がっています。
現在はむしろこのアルバムのほうが廃盤らしいので、関連アルバムを2枚ほど下に挙げておきます。
Tags: guitar · Martino, Pat
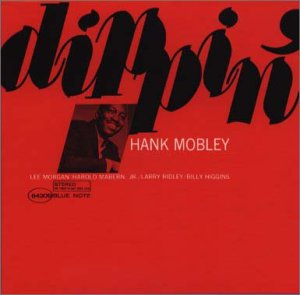
8・16に最高気温を更新してしまい、日本では猛暑が続いています。ジャズは秋冬の音楽と決まったものではないのでしょうが、暑い時にどのジャズを聴くのかには結構頭を悩ませます。もっともジャズのレコード鑑賞にとって猛暑というのは宿敵ですね。まず冷房をかけなくてはいけない。ただエアコンというのは冷房病の人につらいだけでなく、音を劣化させるんです。電気的なことではなくて、噴出し口からでてくる風や機械全体の振動が低音とかぶって低音部が非常に聴き取りづらくなる。次にアンプ。パソコンやモニターも暑いですが、アンプは尋常じゃないほど暑くなります。この熱エネルギーを電気エネルギーに戻してもっとパワーのある音聴かせてよ!といいたくなるほど暑くなって冷房の効果を弱めます。まあ、触った瞬間「アチッ!」となるほど熱いとメンテの時期に来ているんですが、そうでなくても「モワッ!」と暑いわけです。
去年書いたスタン・ゲッツの West Coast Jazz の記事では、夏には「クールサウンド」が合うと主張していましたが、あれはどういうわけか5月の記事で暑いといっても限度があったわけです。今年のように暑いときはどうするのか?一つにはジャズなど聴かず、冷房を効かせて大人しくしているという選択肢がありますが、もう一つ、もうお祭りのように熱いジャズを聴いて汗をかくという方法があります。今回紹介するハンク・モブレーのDippin'もそんなときにうってつけの一枚です。
ハンク・モブレーという人は、褒める人は「平凡な中にも味わいのある」と微妙に褒め、貶す人は「いもテナー」とはっきり貶すという、評価が真っ二つというよりは低いほうに傾いて二分されているテナー奏者です。事実油井先生の名著『ジャズ・ベスト・レコード・コレクション』ではたった一枚 (Peckin' Time) しか取り上げられておらず、そのアンダー・レイティッド具合も分かります。この人はよく言えば控えめ、悪く言えば個性に乏しいテナー奏者で、「俺が!俺が!」の並み居るテナー強豪たちの中ではどうしても埋没してしまうんですね。Dippin' でもサイドマンのリー・モーガンのほうが目立っていて、実際輝かしいプレイをしているほどです。私自身は割りと好きな人で出来るだけこの人のレコードを集めようとしていた時期もありましたが、結局情熱は長続きせずに中途半端なままで終わっています。
このアルバムは1965年6月の吹き込みで、4ビートやファンキーを飛び越えて、8ビートの演奏(いわゆる「『サイドワインダー』路線」)で吹き込まれた1枚です。メンバーはリー・モーガン(tp)、ハンク・モブレー(ts)、ハロルド・メイバーン(p)、ラリー・リドレー(b)、ビリー・ヒギンズ(ds)です。1曲目 "The Dip" はモブレーのオリジナル。8ビートです。ソロの先発はモブレーですがモゴモゴしています。それに比べてテナーの後に出るリー・モーガンの凄いこと!冒頭の1音で人を惹き付けます。
2曲目にして永遠の名作ともいえる "Recado Bossa Nova"。この曲はブラジル人ジャルマ・フェレイラという人物の作曲。ゲッツのボサノバ路線とは違って、南国の哀愁ある熱帯夜の雰囲気を醸し出しています。この曲を夏に聴くと実によく合います。特にお祭りとか花火を見物しながら聴いていると、自分がいま日本の夏祭りにいるのかリオのカーニバルにいるのか分からなくなってくるほどです。我が家からはお祭りの山車や花火がよく見えるのですが、この曲を流しながら雰囲気を楽しんでいます。ポータブルプレーヤーを持っている人はこれを聴きながら夜店の雑踏を歩けば雰囲気出ること間違いなしです。もっとも、一人で夜店歩きをしてもちっとも面白くないですが・・・ここではモブレーのとつ弁スタイルも逆に効果が高く、テナー、ペットともに名ソロ、さらにピアノが情熱的なソロを展開しています。この曲は後にイーディー・ゴーメの『ザ・ギフト』として日本のCMに使われ、わが国でリバイバルしました。ちなみに小川隆夫さんによると、ニューヨークでモブレーに会ったので、この曲が日本でブームになっていることを伝えると、彼自身はこのセッションのことすら覚えていなかったそうです!
3曲目の "The Break Through" はモブレーオリジナルで4ビートのハード・バップ。65年ということを考えるといまさら感はあったと思いますが、現在並列的に聴けばよく出来た演奏です。続く "The Vamp" もモブレーの曲。ここでもモーガンが素晴らしい。5曲目 "I See Your Face before Me" はこのアルバム唯一の4ビート・スタンダードでバラード。モーガンの凡庸さがよい意味で発揮されて実に味わい深い1曲に仕上がっています。ここではリー・モーガンも出しゃばらず、控えめで短めなミュート・ソロを取って情感を盛り上げています。最後の6曲目 "Ballin'" は3拍子。3拍子だと4ビートの手癖が使えないせいで、なかなか緊張しますがリー・モーガンは即興のリフを上手く組み合わせたりして印象的なソロを取っています。モブレーも自作曲だし頑張ってソロをとっています。この人の場合、ハーモニック・アイデアに乏しいわけではなくて、きっぱりと言い切るためのアーティキュレーションがはっきりしないために、いまひとつの評価を受けているということがよく分かるトラックです。
実はこのアルバムを見直したのは、かつて行われていた「はり猫」のライブで、「リカード・ボサノヴァ」の情熱的な演奏を聴いたことがきっかけです。そのときも夏の宵で、町内会長みたいな人が着流しの浴衣で来店していて、中年以上の男性が必要以上に浴衣を着こなすとモーホっぽく見えるということを頭の片隅で考えながら聴いていました 😆
ちなみにこのアルバムに限らず、赤主体のジャケットは色褪せしやすいですから気をつけたほうがいいですよ。私のなんか褪せて、もう半ばピンクです。
Tags: Mobley, Hank · Morgan, Lee · tenor sax
[ニューヨーク 16日 ロイター] テンポの速い「ビバップ」スタイルでジャズに改革を起こした米ドラム奏者のマックス・ローチさんが15日、当地で亡くなった。83歳だった。ジャズ専門の音楽レーベル、ブルーノート・レコードが16日に明らかにした。同氏の死因については公表しなかった。
ローチさんは、1940年代後半─1950年代前半にかけてのビバップ隆盛期にジャズにおけるドラムの位置付けを新たに定義し、英雄的存在となった。
同社スポークスマンによると、ビバップが登場前のジャズは、主にダンスホールで演奏されるスイングミュージックとされ、ドラムはバンドの拍子取りと位置付けられていたが、ローチさんが拍子取りからシンバルへとドラムの役割を変え、ドラムがより前面に出て重要な役割を担うようになった。また、その過程でジャズは一般的なダンスミュージックからクラブで鑑賞するより芸術的なものにシフトしたという。
ローチさんはまた市民活動家としても知られ、これまでに奴隷制度や人種差別問題を提起した曲も作ってきた。(ロイター)
ジャズの巨星がまた一つ落ちてしまいましたが、パーカーのダイアル、サボイ時代からドラムを叩いている人ですから天寿を全うしたと言えるのではないでしょうか。バド・パウエルの名作の数々もローチの太鼓だったし、『サキコロ』をはじめとしたロリンズの諸作、そしてクリフォード・ブラウンとの双頭クインテットなど50年代のジャズを強力に支えたドラマーでした。Blue Noteの歴史を扱ったDVD『ブルーノート物語』では、老いて関西芸人のような好々爺に見えるローチ晩年の姿を見ることができますが、本当は人種闘争の闘士なんですね。非常に面白いエピソードを紹介しているブログ記事を見つけました。
マックス・ローチにまつわる話(Jazzジャズ・Jazzy Bounce)
公民権運動時代のミュージシャンはミンガスにしても、アルバート・アイラーにしてもここで語られているようなエピソードがありますね。やはり当時の人種問題というのは部外者には窺い知れぬほど根深いものだったのでしょう。
晩年はバークレーで教鞭をとっていたと思います。
Tags: Roach, Max · 雑記
August 19th, 2007 · 1 Comment
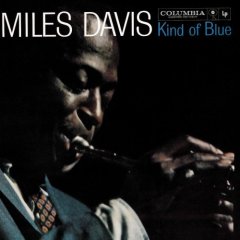
学歴社会から実力社会になったほうがいいと、学歴どころか「学」のない人がたまにご高説を述べていらっしゃいますが、そうなった時に真っ先に消えていくのはご自身だと分かっているのでしょうか?学歴社会ならば安定したコースに乗っていけば、ある程度の保証があるのに対して、実力社会といったら、あんた、実力すらないあなたには厳しい社会だよ、と言いたいわけです。
などと思いっきり皮肉を言っていますが、このアルバムとどういう関係があるんでしょう?『カインド・オブ・ブルー』を語るとき、いわく「コード進行の呪縛に囚われていたジャズ界を解放した」、「バップの限界を打ち破りより自由な演奏をもたらした」などという紋切り型が横行していますが、これと上の図式とがよく似ているなと思ったわけです。バップが呪縛であってモードが解放というのは、ちょうど「学歴」という呪縛から「実力」という解放に向かうという神話の相似形です。確かにIII-VI-II-Vをなぞっていればそこそこ形になるバップに比べてモーダルな演奏というのは何でもありで自由ですが、何でもありすぎで、そこに本当の実力がないと単なるスケールの上下になってしまう。でも、本当に本物の、それこそ0から一瞬にして作曲できて手癖に陥らず、おまけに人に感動を与えられる人物なんていうのは限られていますからどういうことが起きるのか?結局、バップの時と同じく「らしいストックフレーズ集」なんかが出回って、それを必死で覚えて当てはめていくという、解放でもなんでもない結果に終わっています。
マイルス自身は『カインド・オブ・ブルー』を「失敗だった」といっています。これは紛れもない事実です。しかし世の中にはいったん褒めてしまった言葉を取り消せない人も多いらしくて、『自伝』の記述を全く無視して声高に自説を語って、最後は「いいからいいのである」などと寺島さん顔負けのトートロジーで言い切ってみたり、奥歯に物の挟まったような遠まわしな物言いで『自伝』そのものを貶してみたり、果ては「訳者の中山康樹の誤訳である」などと談じているので、てっきり原文をご存知がと思って尋ねたら梨の礫だったり、「ここまで言えるマイルスはやはり偉いのである、そうなのである」と話を微妙に逸らせたり、色々工夫しているわけです。
私の考えだと、これを「失敗作」と言ったマイルスが実際に狙っていたのは、例えば第2次黄金カルテットや『ビッチ』、あるいは『アガルタ』『パンゲア』のようにゆるゆるフォーマットの上に実力者が一堂に会してインタープレーを行うようなスタイルだったのではないかと思うわけです。その狙いに比べて、『カインド』は曲構造こそモーダルだけれど、結局順番にソロを回し、おまけにキャノンボールに至ってはトゥーファイブに分解してソロを組み立てていたりして、結局バップの延長線上に過ぎないと思ったんじゃないか?こう推測するわけです。ポリフォニックな展開を期待していたのに結局モノローグが羅列されていくだけの展開。この辺のことをマイルスは敢えて「失敗作」と厳しく批判していると思うのです。
このアルバムの魅力は一言で言うと気配・雰囲気です。ベースソロから徐々に立ち上がってくるイキフン。これに尽きると思います。そして、これまでのジャズのように結節点を目指してドミナント・モーションを展開させて句読点を打っていくのではなく、常に浮遊した感じでうねうねと彷徨っていくソロ。このあたりが素晴らしいと思うわけです。『カインド』から遅れること40年、グレゴリオ聖歌ブームが来たり、エンヤブームが来たり、ビョークが流行したり。改めてマイルスの先見性を立証しているのは事実だと思います。
ちなみに私も「ソー・ホワット」を一度セッションでやりましたが、DドリアンからE♭ドリアンに変わるところが分からなくて、ピアニストに目で合図してもらっていました 😎
Tags: Adderley, Cannonball · Coltrane, John · Davis, Miles · Evans, Bill · Kelly, Wynton · trumpet