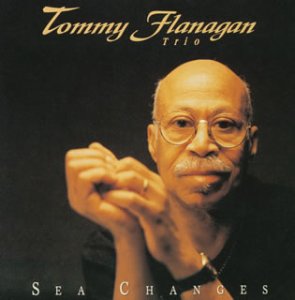September 11th, 2007 · No Comments

ジャッキー・マクリーンはいつもピッチが怪しく、そこが魅力といえば魅力だったのに、晩年に固め打ちで出してきた新作ではピッチが正しくなっていて驚きました。サックスの師匠に訳を伺うと、アンブシュアを矯正したとの答え。サックス教室の生徒ならまず最初にやるアンブシュアの矯正を晩年までして事なかったということに驚きました。もっとも、マクリーンはなんとなくいつまでも少年のイメージが強く、マイルスの『自伝』を読んでも、いつも泣いているか、悄気ているか、拗ねているんじゃないかと思えるほど。そんな彼だから、晩年にやっとアンブシュアを矯正したというのも微笑ましいエピソードではあります。しかし、例えばプレスティッジの『4, 5, & 6』などピッチがずれ過ぎて「ワンワン」という唸りが発生するところがあって聴いていて辛いです。
今回紹介する『スイング・スワング・スインギン』でもピッチの怪しさは満載ですが、聴いていて辛いというほどではありません(当然ですが)。このアルバムは1959年自己名義でブルーノートに吹き込んだ3回のセッションのうち最後のもので、初めてのワン・ホーン物です。リズム陣はウォルター・ビショップ(p)、ジミー・ギャリソン(b)、アート・テイラー(ds)。最後のオリジナル曲を除いてはスタンダードとジャズ曲で構成されていることも特筆すべき点です。
1曲目は "What's New"。後にコルトレーンが『バラード』の中でしんねりむっつりとやりますが、マクリーンは対照的にハキハキと気持ちのよい演奏をしています。冒頭で一瞬レベルがオフった感じになりますが、おそらく録音の問題でしょう。テーマからソロに入り1コーラスやった後、ウォルター・ビショップのソロもよく歌っています。マクリーンの後ソロは冒頭でパーカーの手癖フレーズを出したり、ファナティックに上がった後タメながら下がっていく例のマクリーン節を全開にして盛り上がっています。このアルバムを象徴するような名演です。
2曲目 "Let's Face the Music and Dance" はアービング・バーリンの曲で、歌ではナット・キング・コールが有名です。マイナーから入っていってメジャーに抜けていく曲想で、マクリーンは速めのテンポでマイナーに傾いた感じのソロを取っています。ウォールターのソロもバドのフレーズを引用したりして乗りに乗っています。時計を逆回ししてパーカーのヴァーヴ時代に戻ったかのようです。
3曲目 "Stablemates" はベニー・ゴルソンの曲で、ジャズ曲としてはスタンダードの地位を得たともいえる名曲です。マイナーで哀愁に満ちた曲がマクリーンにぴったりで名演となっています。
4曲目の "I Remember You"。パーカーが「コンファメ・セッション」で吹き込んだワン・ホーンにもある曲で、パーカーに対するオマージュとなっています。テーマなどなんの衒いもなくパーカー風に吹ききっているところなんかむしろ潔くて素晴らしい。
5曲目はコール・ポーターの "I Love You"。6曲目はオスカー・ハマースタイン二世の "I'll Take Romance"。どちらも張り切った演奏が聴けます。
最後の "116th and Lenox" だけがオリジナルですがブルースです。116丁目レノックス街とはハーレムの街の名前で、マクリーンが生まれ育った街のことだそうです。
マクリーンど真ん中の名盤です。最近日本盤CDが再発されました。
Tags: alto sax · McLean, Jackie

朝青龍問題で揺れる大相撲ですが、新潟の災害のお見舞いに行って、重いものなんかを運ぶ手伝いをしているお相撲さんを見ると感動もありつつ微笑ましくなります。おばあちゃんが重いものを運んでいるのを見ると反対に痛々しくなる。何事もそうなんですが、10の力のある人が10のことをやるより、100の力がある人が10のことをやるほうが余裕が感じられて安心感があるわけです。
名前がゴリゴリしている上に、ハード・ブローイングが得意で、吹き比べセッションなどで乗ってくると「ブギャー!ボギャー!」と逸脱してしまうことの多いジョニー・グリフィンが、民謡を中心に据えてじっくりとワン・ホーンで吹き込んだこのアルバムにも同じようなことが当てはまります。普段ハード目にハード目に吹き荒んでいるグリフィンが、抑え目に抑え目に民謡などに取り組むと、高出力のアンプで小さく鳴らすような余裕とくつろぎが感じられる。実に味わい深い名盤に仕上がっています。メンバーはグリフィンのテナーのほか、バリー・ハリス(p)、ロン・カーター(b)、ベン・ライリー(ds)という構成で、吹き込みは61年の12月と62年の1月。
1曲目でタイトル・チューンの "The Kerry Dancers" はアイリッシュ・フォーク。パーカーが「ハイソサエティー」と並んでよく引用していたフレーズとしても有名です。ワン・ホーンということもあり、喧嘩腰でない、ゆったりとしたユーモラスなフレーズで楽しい1曲です。
2曲目 "Black Is the Color of My True Love's Hair" はニーナ・シモンの歌でも有名なアメリカ南部の民謡。スローなイントロから、イン・テンポでテーマに入りアドリブになります。トゥーファイブのところでパーカー風の16分を入れながら立派なジャズへと仕上げていきます。バリー・ハリスもいつもの通りツボを押さえた地味目のソロを取りますが、滋味が溢れています。
3曲目 "Green Grow the Rushes" はスコティッシュ・フォーク。イントロとテーマはスコティッシュ・フレーバー全開ですが、アドリブに入るといつものバップになります。ただ、コーラスのつなぎ目で元歌を示すようなストップタイムが入って面白い。ハリスも軽快なソロです。
さて、4曲目です。"The Londonderry Air"、別名「ダニー・ボーイ」。私はこの曲がかなり好きで、以前に石田衛君がホテル・ラウンジでやっていたライブを聴きに行った時にも、お願いしてこの曲をやってもらいました。コーラスの後半25小節目の一拍で、上の3度(歌で言うと "'Tis I'll be here" の "here" のところ)に上がる時思いっきり強く、情緒なく上がる演奏や歌が多いのですが、ここでのグリフィンもライブでの石田君も、あるいはビル・エバンスもここをソフトに演奏することでテクスチャーに深みを出しています。と同時に単なるムード・テナーやカクテル・ピアノに陥らないのもこうした理性というか抑制感があるからなのでしょう。テーマが終わるとバリー・ハリスのソロですが、これがまたよい。ハーモニックなアイデアを駆使して響きを広げつつ半コーラスソロを取ります。続いて残りをグリフィンがアドリブというよりフェイクでソロを吹きますが非常に感動的です。
5曲目からはB面で、こちらでは民謡を取り上げていませんがムードは繋がっています。特に名曲・名演といえるのが7曲目の "Hush-a-Bye" (「ハッシャ・バイ」)で、その後グリフィンが何度も取り上げている名曲です。マイナーで哀愁の漂うメロディーなので、日本人向きだと思いきや、グリフィンがコペンハーゲン時代にこの曲をやると、お客が踊りだしたそうです。確かに北欧民謡風のイメージを持った曲ですね。作曲はあのサミュエル・フェイン。
テナーのワン・ホーン物としては極上の部類に入る名盤です。
Tags: Griffin, Johnny · Harris, Barry · tenor sax

ビリー・ホリデイを別格とすると、三大女性ジャズシンガーといえばエラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーン、そしてカーメン・マクレエということが出来ます。エラとサラについてはすでに記事を書いたので、今回は、カーメン・マクレエについて書いてみましょう。カーメンについて寺島さんが面白いことを書いています。いわく、「彼女の歌を聴くと、日本語を聴いているように歌詞が理解でき、英語が得意になった気分になる」と。確かめてみようと、英語の授業で学生に彼女の歌の聴き取りをやらせましたが、他の歌よりもずっと正解率が高かったので驚きました。その理由として、語を一音一音はっきり発声することと、彼女独特の歌い方、すなわち「レチタティーヴォ」といって語るような歌い方が挙げられます。以前のアルバムでハリー・コニック Jr.とのデュオがあったんですが、ハリーのほうは南部訛も強くて聴き取りづらかったのにたいして、カーメンのパートになったらたちまち歌詞が理解できたということもありました。
今回紹介するアルバムは、1972年ロサンゼルスのクラブ「ドンテ」でのライブを録音したもので、アメリカの様々な名曲をジャズに仕上げて歌っていることからこのタイトルが付けられました。編成もジョー・パスのギター、ジミー・ロウルズと曲によってはカーメン本人のピアノ、チャック・ドメニコ(b)、チャック・フローレス(ds)という小編成で、録音のよさとあいまってクラブの雰囲気が横溢しています。うちの安いキカイでも、隣の部屋で流しているのが洩れて聴こえると本当にそこでやっているように聴こえるほどです。
1曲目 "Satin Doll" はエリントンとストレイホーンの曲。ベースだけを従えて歌いだし、2コーラス目にギター、ピアノ、ドラムが入ってジョー・パスのソロになだれ込むところが心憎い。
2曲目 "At Long Last Love" はコール・ポーターの同名ミュージカルの主題歌。
3曲目 "If the Moon Turns Green" はビリー・ホリデイが歌った歌ですが歌詞が違います。ピアノはカーメン本人。
4曲目の "Day by Day" も有名なスタンダードで、トミー・ドーシー楽団のアレンジャーでもあったポール・ウェストンの曲。
"What Are You Doing the Rest of Your Life" (5曲目)は映画リチャード・ブルックスの映画「ハッピーエンド/幸せの彼方に」の主題歌で、ミシェル・ルグランの作曲。伴奏のジョー・パスは、カーメンも述べているように素晴らしい演奏です。
6曲目 "I Only Have Eyes for You" はハリー・ウォーレンの曲で、ビリー・ホリデイも歌ったスタンダードですが、フラミンゴズのドゥーワップで有名になりました。歌詞を作り変えて歌っています。
7曲目はメドレーで "Easy Living", "The Days of Wine and Roses", "It's Impossible" が歌われます。前の2曲は大スタンダードですが、"It's Impossible" はエルビスが歌ったラテンナンバーだったと思います。作曲者もアルメンド・メンザネロというメキシコのボレロ作曲家です。
8曲目 "Sunday" はジュール・スタインの曲でシナトラの『スイング・イージー!』でも歌われた古いスタンダード。
9曲目レオン・ラッセルの "A Song for You" は、以前からカーペンターズの歌で聴いたことがあり、心を打たれましたが、ここでのカーメンも素晴らしいです。これぞ「母国語で歌われているように歌詞が入ってくる歌い方」の典型でしょう。また、カーメンの特徴としてよく挙げられるのが「詞に対するアイロニカルな対応」というものがありますが、この曲にその特徴がよく表れています。アルバムのベストトラックと呼べる1曲です。最近もハービーさんがクリスティーナ・アギレラと吹き込んでいます(アルバム『ポッシビリティーズ』)
10曲目 "I Cried for You" もジャズの大スタンダードで、ビリー・ホリデイは『奇妙な果実』の中で、この歌でサラ・ヴォーンと勝負して圧勝したと書いています。まあ、あの自伝はインチキ臭いんですがね。
11曲目 "Behind the Face"、12曲目 "The Ballad of Thelonious Monk" はジミー・ロウルズの作曲とクレジットされているので、このアルバムのオリジナル曲でしょう。「モンクのバラード」では途中で「ブルー・モンク」の一節が引用されたりして楽しくやっています。
13曲目 "There's No Such Thing as Love" はアンソニー・ニューリーとイアン・フレーザーの曲。14曲目は、バート・バカラックの有名な "Close to You"。元歌とだいぶ違います。15曲目 "Three Little Words" もビリー・ホリデイで有名なスタンダード。16曲目 "Mr. Ugly" はノーマン・マップの曲でカーメンがピアノを弾いています。17曲目 "It's Like Reaching for the Moon" は再びビリーの吹き込みで有名なスタンダード、そしてラスト、 "I Thought about You" も大スタンダードで、マイルスも『いかついお爺様が』、じゃなくて『いつか王子様が』で吹き込んでいます。
昔から、カーメンを最初に聴くなら『ブック・オブ・バラーズ』、『アフター・グロウ』、そしてこの『グレイト・アメリカン・ソングブック』だといわれています。極端な人だとこの3枚があればOKという人もいます。それは甚だしい意見であるにせよ、この3枚はマスト・アイテムでしょう。
Tags: McRae, Carmen · vocal

ジャズを聴いていると、否応なしにジャズ・ジャーナリズムにも巻き込まれて行くことになり、読みたくもない論争を読まされて、ない頭で考える羽目になることがあります。古いところでは「キース・ジャレットはジャズか否か」をめぐって油井先生と岩浪洋三氏が衝突して『スイング・ジャーナル』誌を賑わせ、そこへオスカー・ピーターソンまで参戦してキースをこき下ろすや、読者欄から反オスピーの狼煙が上がりそれがまた本文記事へと波及していくなんてことがありました。この時は新進気鋭の若きキースを老人が叩き、若い読者が反論するという形でしたが、後には若いウィントン・マルサリスがキースを酷評し、キースがそれを諭しながら反論するという事件も起きました。一見かつての若手が老齢になり、新しい若手から叩かれているように見えますが、若手とはいえウィントンはとんでもない保守反動路線なので、ひょっとしたら構造は同じなのかもしれませんね。
どちらの論争でも主人公であるキースの音楽には,どこかコントロヴァーシャルな部分があるのかもしれません。確かに『ケルン』全体や「マイ・バック・ページ」を聴くと、叙情性べったりというか、没入しすぎて対象と距離が取れていないようなところがあって時に鼻につきます。ハービーはいくらファンク路線をひた走っても、どこかでそれを冷静に眺めている目がありますし、チックはスパニッシュな曲をやっていても、どこかでそれをメソダイズしようという意図が見えます。ところが若き日のキースは曲に没入するというか、完全インプロの場合は手癖と「甘ったるい」メロディーに淫して対象化しえていない時があります。しかし80年代に入って「スタンダーズ」シリーズを吹き込むようになると、この辺の距離というか対象化が上手くなってきて、ジャズ的興味が増してきました。
「スタンダーズ・シリーズ」はかなり多くて、そのどれも甲乙つけ難く、逆に言えばどれを聴いてもいいのですが、私が一番好きなのが今日紹介する『アット・ザ・ディア・ヘッド・イン』です。「ディア・ヘッド・イン」とはライブハウスの名前で、キースは高校を卒業して電気メーカーに勤めていた頃、このクラブのハウストリオとして雇われたのが世に出るきっかけだったと彼自身ライナーで書いています。それから30年、1992年の9月16日に思い出のライブハウスで行われた演奏を録音したのがこのアルバムです。こういう思い出の小屋でやるときというのは格別で名演が生まれないわけがない。
またこのCDは音がよい。キースのタッチにしろ、ベースやドラムの動きにしろ、かなり詳細に捕らえている録音技法です。ジャズでは普通すっ飛ばされてしまうような最弱音のタッチなどもばっちり捉えられていて、最初聴いた時には魂消ました。さらに選曲がいい。得意曲を並べているのではなく、多岐にわたる曲を網羅しながら、一つとしてやっつけ仕事がないのが凄い。特に4曲目 "You Don't Know What Love Is" では、元曲と全く離れたインプロヴィゼーションの塊がでてきます。また6曲目 "Bye Bye Blackbird" はマイルスに匹敵する演奏に仕上がり、アンコールのようにして始まる "It's Easy to Remember" では念入りなタッチが見事に捉えられています。そう、念が入っているわけです。入念です。入念の選曲、演奏、そして録音があいまって、このアルバムは傑作中の傑作に仕上がっているわけです。隠れた名盤、あるいは隠れなき名盤というのは、こうしたものを指すのです。
Tags: Jarrett, Keith · piano
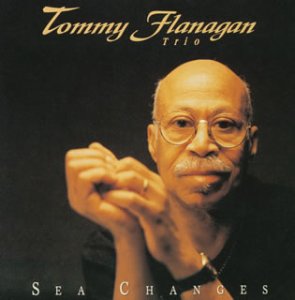
これまでも少し書いてきたように、高校時代インチキ・アルバイトをしてはお金を貯めてライブ(というよりコンサートですね)によく出かけていました。ベニー・グッドマン、サラ・ボーン、MJQ、そして寒風西新宿マイルス、近藤等則など、どれも印象的でしたが、最も印象的だったのはビル・エバンスの来日コンサートでした。なぜなら、直前に亡くなってキャンセルになってしまったのですから。この件についてはいずれエバンスの項で書こうと思っています。こんなにフラフラ出かけられたのは結局「生活費」を親がまるがかりで見てくれているからということが大学に入ると痛感されるわけです。
大学に入ると、一人暮らしで学費や生活費を自分で面倒見なければいけないので、一気にコンサートやライブに足を運ぶ機会が減りました。それどころかスレテオ道具も持ち込めない寮生活だったので、実家で何本かダビングしたテープを延々聴く生活ですから、ライブなんてとんでもない。それに諸活動と勉強があるので時間もなく、ほとんど行けませんでした。
その反動で、仕事についてからは頻繁に出かけるようになり、今回紹介するアルバムのプロモーションを兼ねてトミフラがブルーノート東京に来た時も出かけました。ブルーノートに一人で行くのは精神上不可能なのですが、ネットを通じてジャズ仲間ができるのはこの後のことなので、この頃のライブには学生を連れて行きました。帰りが遅くなるので男子学生のみです。行く前にこのCDをテープに録って渡し、当日までに聴いてくるように課題を出したりしました。全くやくざな教師です 8) ライブ会場では寺島さんにお会いして少し話を伺えたりして非常に楽しいライブでしたが、トミフラが禁煙中ということで前列の灰皿を全部片付けられてしまい、「おいおい、『エクリプソ』のジャケはどうなんだよ?あんなでかいパイプ銜えていたくせに」とやや釈然としない思いもしましたがね。
このアルバムは、名盤『オーバーシーズ』のリメイクというか「現時点での『オーバーシーズ』」を吹き込んだもので、5曲が両アルバムに共通しています(「ヴェルダンディ」、「ダラーナ」、「エクリプソ」、「ビーツ・アップ」、「カマリロ」)。また7曲目の "Between the Devil and the Deep Blue Sea" (「絶体絶命」)も、『ハロルド・アーレン集』で演奏しており、このときのプロデューサーはなんとヘレン・メリルです。さて、このアルバムのメンバーはクリス・クロス・レーベルでも活躍している4ビートの若手ピーター・ワシントン(b)とルイス・ナッシュ(ds)。ライブもこのメンツだったので寺島さんが聴きに来ないわけがない。案の定ルイス・ナッシュの横に陣取ってドラムを聴いていらっしゃいました。
このアルバムは日本制作盤でオーディオ・マニア・オリエンティッドでもあるのか、非常に音がいい。録音エンジニアはジム・アンダーソン。ドラムのスティックがシンバルに当たる時の「カツッ」というような芯の太い音まで捉えられていて、うちの安いキカイでも充分に再生されます。ピアノトリオの名盤、名録音盤といってもいいでしょう。いまは廃盤ですが、中古で安く手に入ります。
Tags: Flanagan, Tommy · piano

『相棒』という刑事ドラマが好きで欠かさず見ていますが、先日再放送でもやっていた「セレブ殺人」というエピソードでは「モノに執着することの不幸」を描いていて印象的でした。私自身、ジャズと関わってきて一番理解できないタイプの人々が「コレクター」といわれる人々です。あまりコレクターの悪口を言うと逆ねじを食らわされそうだし、そもそも他人の趣味に容喙するのは野暮なので、「セレブ殺人」を見ていただくことにしましょう 8)
このアルバムはMGM Verve の溝あり盤で持っています。はぁ?上で言ったことは何なんだ!と言われそうですが、実は血眼になって捜し求めたわけでもなければ、大枚を叩いて買ったわけでもなく、縁あって手元に来ているだけです。簡単に言えばこのレコードを聴きたいなと思って廃盤屋さんで買ったらそういうレコードだったってことです。もっともそっちの知識はないので、たまたま遊びに来た「コレクター氏」が裁定して帰っていったのを受け売りで言っているだけなんですが。原題は Hawkins! Alive" at the Village Gate 。「ホーキンスは生きている」なんて失礼なタイトルですが、彼は生前から伝説の人だったんです。邦題『ジェリコの戦い』のほうが日本のジャズファンにとっては馴染み深いタイトルです。
コールマン・ホーキンス、あだ名はビーン。「ジャズ・テナーの父」と呼べる人です。彼がフレッチャー・ヘンダーソン楽団に在籍していた1924年、ルイ・アームストロングがこの楽団に入りその天才的なプレイを披露しました。これを聴いたホーキンスは、天啓を受けがた如く悟るところがあり、それまでのリズム的にカクカクした感じのプレイだったものが、アームストロングとの共演を経て徐々にジャズ・テナーらしいスタイルに変貌していく様は、フレッチャー・ヘンダーソンの『挫折の研究』第1集に耳を傾けると明らかになります。1934年に渡欧し、スター・ソロイストとしてジャンゴ・ラインハルトやベニー・カーターらと演奏をし、戦雲が暗くなった1939年、再びアメリカに戻って吹き込んだ "Body and Soul"(身も心も)は歴史的名演となり、広範な影響をジャズ界に及ぼしました。特にベン・ウェブスターやレオン・チュー・ベリーはホーキンス派といってよく、レスター・ヤングを除くほとんどのテナー奏者の元となったのがコールマン・ホーキンスであるわけです。ビ・バップの時代になると、このトレンドに背を向けたベテランやバップを超えて次代に影響を与えたレスター・ヤングとは逆に、このバップイディオムを積極的に吸収し、ロリンズやコルトレーンにも深い影響を与えました。
1962年8月13日と15日、ニューヨークの名門クラブ『ヴィレッジ・ゲイト』で吹き込んだライブアルバムがこれです。メンツはビーンのほか、トミフラのピアノ、メジャー・ホリーのベース(この人はアルコで弾きながらスキャットを歌う奏法で有名です)、ドラムはエド・ロックです。A面冒頭は "All the Things You Are"。この曲は頻繁に転調する曲でコード感がもともと強いためにバップで好んで取り上げられます。パーカーが全編即興演奏で挑んだ「バード・オブ・パラダイス」はこの曲です。ビーンの場合はそんなことに囚われず、とにかくブフォーン、ブフォーンとテナーの音色を全開して吹いているところが魅力です。トミフラのソロはピシッと決まって心地よい。2曲目 "Joshua Fit the Battle of Jericho" は「ジェリコの戦い」という邦題のほうが有名な黒人霊歌です。この曲、無伴奏でビーンが一発目を吹いた後、左のスピーカーから飛び出してくるメジャー・ホリーのベースがとにかく太くて力があって凄い。ホーキンスのテナーも、「何で金属製のサックスが木管楽器なんだ?」という疑問を一発で解消してくれるように、リードの「木の音」がはっきり分かる音色でサックス好きにはたまりません。トミフラのピアノはちょっとオフった感じの録音ですが、エモーショナルなソロで思わず耳を傾けてしまいます。またホーキンスに合わせたのでしょうか、アール・ハインズのようなソロです。メジャー・ホリーの典型的なソロと続き、ビーンが自由なソロを取りつつテーマになだれ込んでいきます。
B面は1曲目が "Mack the Knife"。トミフラの可憐なイントロに続いて、ぶっきらぼうなテナーが出て来ます。ところでこの曲は、つまり『サキコロ』の「モリタート(マック・ザ・ナイフ)」。どちらにも参加しているトミフラはどうしているでしょう?さすが!「モリタート」でのロリンズのフレーズを後半で引用しまくっています。ベースのソロを受けて後テーマに入ったビーンまで「ホーキンス風ロリンズ」で吹いたりしています。この辺の「ソースは隠さないどころか、積極的にパロディーにする」というジャズ的精神は、普段ジタジタと論文なんぞに取り組んで「影響とオリジナルの境」で精神を湿らせている人間にとっては、もう完全な癒し系音楽です。私のことなんですけれどね。
最後はホーキンスの典型的なバラード吹奏で演じられる、"Talk of the Town"。邦題は「町の噂」。縦方向のコードトーンを並べて吹くホーキンス・バラードは上でも触れた「身も心も」で顕著ですが、ここでも、老いたりとはいえその特色は健在です。
近代ホーキンスを聴くならこのレコードがいいかと思います。しかし伝説的「身も心も」はやはり多くの人に聴いて欲しいなと思います。
Tags: Flanagan, Tommy · Hawkins, Coleman · tenor sax

クリフォード・ブラウンの吹く「アイ・リメンバー・クリフォード」が聴きたいという笑い話が、ジャズ界にはあります。似たような話に、バディー・ボールデンの吹く「バディー・ボールデンの思い出」が聴きたいというのがありますが、どちらも故人を偲んで作られた曲なので、当人の演奏は聴ける筈もないところがポイントなわけです。おまけに、バディー・ボールデンにいたっては伝説だけで録音が残っていないので二重におかしい話となります。これをヒントにして「Youの歌う "I Remember You" を聴きたい」といったら、「だったらYouに頼めばいいじゃないか」と言い返されたことがあります。違いない。ちゃんとものを考えてから発言しないといけませんやね。
アリソン・フェリックス嬢の活躍を祝して、リー・モーガンを続けて紹介します。名曲 "I Remember Clifford" は、クリフォード・ブラウンの急逝の後、ベニー・ゴルソン(ts)が彼を偲んで作曲し、このアルバムでリー・モーガンが吹き込みました。あまりにも哀切極まりない曲想で大ヒットし、その後様々なミュージシャンが吹き込みました。ピアノ、テナー、ギターと様々な楽器で演奏されますが、やはりクリフォードをイメージした曲のせいか、トランペットでの演奏にその華があると思います。
このアルバムは全曲ベニー・ゴルソンによる作曲で占められています。ベニー・ゴルソンの作曲の腕は素晴らしく、魅力的な楽想の曲を数多く生み出しているのですが、不思議なことにテナーの演奏となるとさっぱりです。決してヘタではなく、楽器のコントロールもできているのですが、全然爆発しない、旋律性が感じられないジタジタした感じのソロになるのが不思議でなりません。メンバーはリー・モーガン(tp)、ジジ・グライス(as)、ベニー・ゴルソン(ts)、ウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、チャーリー・パーシップ(ds)のセクステット(6重奏団)編成。57年3月のセッションです。クリフォードが亡くなったのは前年の6月です。
1曲目 "Hasaan's Dream" はイントロこそ中近東の雰囲気を出していますが、テーマに入るとマイナーブルースで、やがて来る「ファンキー時代」すら予感させます。それもそのはずで、ファンキー時代の重要な要素の一つが「ゴルソン・ハーモニー」つまり、ベニー・ゴルソンの作り出す和声進行なのです。ソロの先発はリー・モーガン。はつらつとしています。続いてジジ・グライスのアルト。最初は突拍子もない大胆な入りをしますが、後はなんとなくジャッキー・マクリーンのよう。ゴルソン先生は、まあ吹いています。
2曲目 "Domingo" はベニー・ゴルソンの先発。コールマン・ホーキンスのようなソロを取っています。続くリー・モーガンはやはりいいのですが「パーララ、パーララ」とクロマティックで上がっていく、初心者風の手癖がちょっと目に付きます。ジジのアルトは相変わらず軽い音色でちょっと不思議なフレーズを吹いています。ウィントン・ケリーのソロもいまいち爆発していません。
3曲目にして永遠の名曲 "I Remember Clifford"。テーマ演奏もさることながら、アドリブに入っても、元の曲想と馴染んで突飛な感じがせず、それでいて頻繁に裏に入ってもいる。実に上手いアドリブで、これが19歳の少年の演奏とは思えません。続くウィントンのピアノ・ソロも倍テンで軽快に弾き、元曲に変化をつけています。後テーマも哀愁が深く実によくできた演奏です。
4曲目 "Mesabi Chant" は34小節の構成で13-8-13という変わった構成です。そのせいかサビの入りでジジなど躓いているところもご愛嬌。これでゴルソンまで躓いたら洒落になりませんが。しかし8-12-16-32と聴き慣れている耳には、一瞬「え?」と感じさせる曲ですね。5曲目 "Tip Toeing" はいわゆるファンキーナンバーで16小節。ポール・チェンバースの地面にめりこむようなソロから、ゴルソンの吹き荒ぶテナー、またも入りが奇妙なジジのアルト、おどけたようなリーのペット、ブルースフィーリング溢れるウィントンのピアノを経て、ベース・ドラムのブレークを挟んでテーマに戻ります。
他の曲も悪くはないのですが、やはり "I Remember Clifford" 一発の魅力でこのアルバムは持っています。しかし、この1曲だけでもアルバム全体の価値に匹敵する、そんな名曲です。今月再発盤が出る予定です。
Tags: Kelly, Wynton · Morgan, Lee · trumpet

大阪で行われている世界陸上で活躍したアメリカ短距離のスーパー女子大生、アリソン・フェリックスという可愛らしい選手がいますが、彼女がどことなくリー・モーガンに似ているように見えて仕方ありません。笑うと可愛らしくてそれほど似ていないのですが、緊張しているとそのままトランペットを吹き出しそうな感じです。まあ、大げさに言っていますけれどね 8)
このアルバムはリー・モーガンのワンホーンものとして有名で、彼独自の甘くてちょっとワルなフレーズを堪能できる名盤です。吹き込み当時、弱冠20歳だったことも驚異的です。その後に続くジャズ天才少年のはしりといえるでしょう。メンバーはリーのほか、ソニー・クラーク(p)、ダグ・ワトキンス(b)、アート・テイラー(ds)、吹き込みは57年11月と28年2月の2つのセッションです。
1曲目はタイトル・チューンの "Candy"。リーの演奏を聴いていると「キュッキュッ」というようなすぼまった感じの音がよく聴こえるので、トランペッターに訳を訊くと、これは「ハーフ・バルブ奏法」といい、バルブを半分ぐらいまでしか下げずに息の詰まったような音を出す技法とのことでした。サックスにも「ハーフ・タンギング」といって、音を弱めるような軽いタンギングの奏法がありますが、これはアクセントのメリハリを息ではなくて舌でつけるための技法。一方のハーフ・バルブは音色に変化をつける技法でベンドやギターでいうチョーキングに近いそうです。
"Candy" はスタンダードですが、曲想とリー・モーガンの特質が見事にマッチしていて、彼のために書かれた曲だと思えるほど。ドラムのイントロのあと、リーのテーマに続いて、まずはソニー・クラークが先発ソロ。3連多用の球を転がすようなソロです。続いてリーのソロ。彼の持ち味が全開になったソロですが、最初中音域で渋く抑えておいて徐々に盛り上げていく構成で20歳とは思えない巧みなソロです。この曲では、アート・テイラーのブラッシュが大活躍しています。
2曲目の "Since I Fell for You" はR&Bのヒット曲。スタンリー・タレンタインが『ブルーアワー』でも取り上げていますが、ダウン・トゥー・アースな演奏。ピアノソロを経て聴こえてくるリーのソロはあちらこちらで引用されている有名なものです。
3曲目 "C.T.A." はジミー・ヒースの作曲の循環。マイルスがブルー・ノートに吹き込んだ演奏でも有名です。循環らしく、みな元気なソロを取っています。
4曲目はジェローム・カーンのスタンダード "All the Way"。スローな曲ですが2曲目のダウン・トゥー・アースな曲と違って哀愁のあるメロディーを持った曲を、リーはその哀愁を損なうことなく吹き上げていきます。先発はソニー・クラーク。コードの広げ方がレッド・ガーランドを意識したような感じもしますが、右手はやはり3連多用の彼独自のものです。リーのソロは "I Remember Clifford" のソロを髣髴とさせるような心のこもった綺麗なフレーズの連発で、味わい深い。酒場の隅で呑んでいて、こういうのが聴こえてくると、参ったという気持ちになりますね。
軽快で世俗的な曲の "Who Do You Love I Hope" が5曲目。これもスタンダード。リーのソロは冒頭からハーフ・バルブを多用してます。盛り上げつつリフを駆使し華麗なソロを取ります。6曲目 "Personality" もスタンダード。これも世俗的で小唄調の曲ながら、ソロに入ると世界が広がった感じがします。曲想に引っ張られずに楽想を展開していくリー・モーガン。見事としか言いようがありません。
おそらく、この若さと実力、そして「キャンディー」の可愛らしさから、アリソン・フェリックス嬢を連想してしまったのかもしれませんね。名盤でコンスタントに手に入りますが、来年ぐらいに日本では再発されるようです。下のCDは輸入盤です。
Tags: Clark, Sonny · Morgan, Lee · trumpet

パーカーを聴くならなにから聴いたらいいかという質問はよく出るものですが、自分の場合を振り返ってみると次のような順番で求めていきました。最初に買ったのはこのブログでも散々触れていますが With Strings。これを買った頃は、途中で出てくるオーボエやハープなんかにも耳を傾けていましたが、それでも徐々にパーカーのラインを聴き取ることができるようになり、"April in Paris", "Summertime", "Just Friends" などを好んで聴いていました。気をよくして次に買ったのが On Dial Vol. 1 です。たぶん帯のフレーズを読んで買ったのでしょう、驚きました。16曲入っていると思って買ったら同じ曲が出てくるわ出てくるわ、そう「別テイク」です。CD時代ならスキップで飛ばしたりプログラム再生できますが、LPだとそうも行きません。ジャズを聴き始めた頃なので訳も分からず、ライナーノーツを読むと「テイクごとにアドリブ・フレーズの全く違うところが驚きだ!」などと書いてあるわけですが、こっちとしては「3曲も同じ曲が続くところが驚きだ!」なわけです。「途中で切られた曲が出てくるのはもっと驚きだ!」なわけです。
おまけに連続攻撃が終わって、1曲ずつ違う曲が入っていると思い安心したら、これが「ラバーマン・セッション」。聴いていて「え゛ーっ!」となります。なんか陰鬱で辛そうな演奏が4曲も続いているのですから。今の耳で聴けば、パーカーが何をやっているのか、テイクごとにどう違ってどう優れているのか、「ラバーマン・セッション」がどれほど天才の不思議さを伝えているのか、などなど理解できるわけですが、当時としてはさっぱり、「意味わかんねぇ」とはこのことでした。「変なレコード掴んじゃったなぁ」というのが正直な感想です。
次に買ったのが今日紹介する Swedish Schnapps でした。油井先生が「ヴァーヴのバードはダメだと言うが、『スウェディッシュ・シュナップス』や『ナウズ・ザ・タイム』を聴いてみたまえ。素晴らしいから」と何かで書いていたので買い求めたわけです。本当は「ヴァーヴのバードはダメだ」と言われていることすら知らなかったのですけれどね。
このアルバムはブルースが多く吹き込まれている点と、マイルス入りのセッションが聞ける点が特色です。
1曲目 "Si Si" はFのブルース。ソロ1コーラス目のGm7-C7のところで、典型的なパーカーの節回しが炸裂します。2,3曲目の "Swedish Schnapps" はB♭循環。3曲目(別テイク)のサビの部分で優れたアドリブが聴けます。ジョン・ルイス(p)も味のあるソロを取っています。4,5曲目 "Back Home Blues" はCのブルース。ここでも1コーラス目のトゥーファイブで入念な節が聴けます。パーカーのソロは5曲目(別テイク)のほうがよいような気もしますが、ちょこっととちっているのでお蔵入りされたのでしょう。6曲目の "Lover Man" は、あの「ラバーマン・セッション」から5年。今回は見違えるようによくなったかというと、不思議なものでなんとなくぎこちない。エンディングはパーカーがたまにやるクラシック音楽のパロディーです。
7曲目はCDだと "Blues for Alice" ですが、LPではB面1曲目の "Au Privave" でした。CDで7曲目に来たのは、この曲が上の6曲と同じ51年8月8日のセッションだからで、正しい順番に戻したといえるでしょう。 "Blues for Alice" はFのブルースで、パーカーの中では比較的遅めの160です。これは "Billie's Bounce" と同じぐらいなので、B♭7のところで上のルートから下のルートまでダラララと落ちていく、典型的な手癖フレーズが出ています。
8,9曲目が "Au Privave" でFのブルースです。ここから51年1月17日のマイルス入りのセッション。これも名作でマイルスもなかなか張り切ったソロをとっています。10,11曲目の "She Rote" は「アウト・オブ・ノーウェア」のコードを使ったオリジナル。ミュートのマイルスが優れています。若きマイルスの代表的なミュートソロといえます。
12曲目の "K.C. Blues" はかなりゆっくりとレイドバックした感じのCのブルース。K.C.とは「カンザスシティー」のこと。マイルスのぎこちないソロを挟んで、パーカーが自由自在にソロを繰り広げます。13曲目 "Star Eyes" はスタンダード。こういうスタンダード曲のテーマ解釈は、まさに「ウィズ・ストリングス」を彷彿とさせます。自由に崩しながらテーマを吹いたあと、マイルス、ウォルター・ビショップのソロが続き、再び自由に崩したパーカーによるテーマ演奏が聴けます。
CDだとここに "Segment", "Diverse", "Passport (1 & 2)" が追加されますが、この4曲が共に2ホーン(アルトとペット)のクインテット編成で、これが加わることで「ヴァーヴのクインテットが網羅される」という事情から追加されたわけです。 "Segment" と "Diverse" は同じ曲のテイク違い。逆に "Passport" は1と2になっていますがまったく別の曲で、1がブルース、2は循環です。「別テイク」などと書いているサイトがありましたが、間違いです。
セッションデータはパーカーに加えて、1-7がレッド・ロドニー(tp)、ジョン・ルイス(p)、レイ・ブラウン(b)、ケニー・クラーク(ds)で1951年8月8日、8-13がマイルス(tp)、ウォルター・ビショップ(p)、テディー・コティック(b)、マックス・ローチ(ds)で51年1月17日です。追加曲(14-17)はケニー・ドーハム(tp)、アル・ヘイグ(p)、トミー・ポッター(b)、マックス・ローチ(ds)で、49年5月5日の吹き込みです。
Tags: alto sax · Davis, Miles · Dorham, Kenny · Lewis, John · Parker, Charlie · Roach, Max

ベニー・グッドマンからジャズに入ったことは以前にも書きましたが、ラジオ番組を通してパーカーやマイルス、コルトレーン、バドらに出会ううちに、「一体ベニー・グッドマンはジャズや否や」という本質論というか唯名論的命題にぶつかるわけです。まじめだったんです 8) グレン・ミラーまで行ってしまうと、「アドリブ」の部分まで全部同じ(書き譜)なので、「これはジャズではないな」と言えるのですが、ベニーの場合は微妙。そこで昭和の高校生として一大決心をして、近く来日するベニー・グッドマンを聴きに行き、同時にRCA全集を購入して聴き倒すと決めたわけです。そうなると軍資金が必要になり、近所の中学生に英語を教えて小遣いを稼ぐかたわら、中華料理屋でアルバイトをはじめました。ところがこの中華料理屋の職場環境が劣悪なことこの上ない。仕事で一番つらいのは業務のハードさではなく、人間関係が悪い時ということは今になれば常識ですが、この人間関係がよくなかった。とにかくみんな仲が悪く、コック同士がいがみ合うことしばしば。一人のコックが帽子を床に叩きつけて出て行ってしまい、仕方なしに私が餃子を焼いたり、青椒肉絲を炒めて出したこともありました。免状を持っていない私が料理を作るなんて違反だと思うんですが、料理は楽しいものの、人間関係がこの調子ではインボルブされたあとのことが思いやられ辞めたくなりました。そこでレコード買いは英語バイトの給料を貯めることにして、とにかくベニーのコンサート費用が溜まった頃合を見計らって「辞める」と告げました。因業なオーナーは言を左右にして安く使い叩ける高校生バイトを引き止めましたが、「辞めます、お給料は働いた分だけ貰います」と言い張って辞めました。
そんな苦労をして日本武道館で開催されたオーレックス・ジャズ・フェスティバルにベニーを聴きに出かけましたが、これがよくない。変なコーラス娘を連れてきたりしてシャリコマだし、コンボ演奏でテディー・ウィルソンとミルトン・ヒントンが張り切るものの、ベニーと意思疎通が出来てなくて別のセッションを同時にやっているよう。むしろおまけのように考えていた、ベニー・カーターやハリー・スイーツ・エディソン達のセッションのほうがずっとよかった。いや、かなりよくてこちらはライブ盤も買い求めました。
ということでベニーはやっぱりジャズではないんじゃないかと思い、RCAの全集も買わずにおこうと思いましたが、「まあ、今はジャズでないにしても、全盛時代はジャズだったのかもしれない」と思い直し、働いたお金で買ったのが写真のボックス・セット(9,000円)です。オーケストラの代表的名演とスモール・コンボの全演奏を収録した6枚組みです。いやぁ、聴き倒しましたよ。親から「耳につく」と苦情が来るまで聴きました。その結果出した結論は、1)バンドが素晴らしいのはスター・ソロイストと、2)フレッチャー・ヘンダーソン楽団のアレンジと、3)ジーン・クルーパー(ds)のおかげであり、4)コンボ演奏はベニー含めてみんな凄いということでした。というわけで子供G坂ジャズ検定に合格したわけです。
特にスモール・コンボはモダン・ジャズ的な耳でかなり批判的に聴き込みましたが、それでも凄さに変わりはない。ライオネル・ハンプトンが加わった吹込みから「ジャズ度」がグンとアップするところも面白いです。このレコードには入っていませんがチャーリー・クリスチャンが入るとさらに「ジャズ度」が高まるのですが、その頃には残念なことにジーン・クルーパが抜けています。
さてジーン・クルーパがとびきり優れているのは1937年2月3日のセッションです。この日のジーンは神がかっています。スイング史上最高のスモール・コンボのドラマーに神が舞い降りたのですから、このセッションがスイング時代最高のセッションといっても過言ではありませんが、まあレスターの「レディー・ビ・グッド」セッションのほうが上ですね。しかし、この日のセッション、曲としては "Ida, Sweet as Apple Cider", "Tea for Two", "Running Wild"の3曲が凄い。ジーンが凄いので当然全員凄くなるわけです。モダン・ドラムとは趣向が違いますが、アート・ブレーキーにも匹敵する繊細さと潔さで歌うリズムを叩き出しています。必聴曲です。
ベニーRCA時代の選集はCD時代になっても数多く編まれていますが、上の3曲が入ったものを下に挙げておきます。現在は入手不可ですがサンプルが聴けます。
Tags: big band · Goodman, Benny