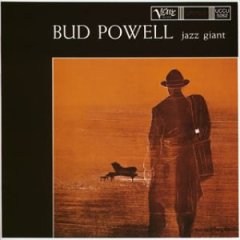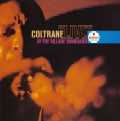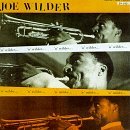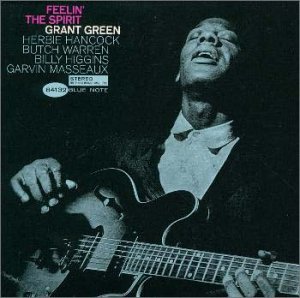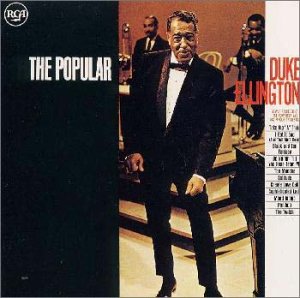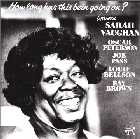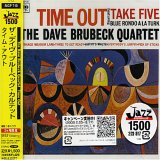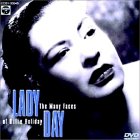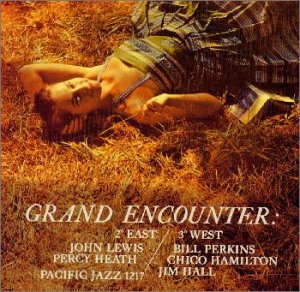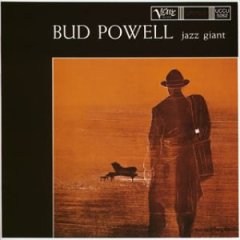
私がちょうどジャズにはまりはじめた頃、ポリドールは "Verve不滅のシリーズ"と銘打ってVerveのアルバムを固め打ちで再発してきました。それもとくに推薦する有名どころは1800円レベル、もう少しマニア度が高いアルバムでも2300円だったように記憶しています。しかし、この500円という差が大きかった。ベイシーで言えばBasie in Londonは1800円なのにApril in Parisは2300円。『パリ』が欲しいと思っても、やはり『ロンドン』を優先することになるわけです。
バド・パウエルの場合Genius of Bud Powellが1800円、今回紹介するJazz Giantは2300円してました。当然のように『ジニアス』の方を買ったわけですが、ピアノソロが多かったりなんとなく理解しがたい演奏もあってピンと来ないんですね。『ジャイアンツ』の方を聴いてみたいと思っていたところ高3の時新任で赴任してきた高校教師が所持していたので、彼のアパートに押し掛けて聴かせてもらいました。その場で「くれ!」と頼み込んだものの当然ダメで、仕方なしに借りてきてテープにダビングしてずっと聴いていたものです。そしてCD時代になってCDラジカセを買ってはじめて購入したのも『ジャイアンツ』でした。いや、『ジャイアンツ』がCD化されたのを見かけてCD移行を決意したというのが正確な言い方です。それほど私にとっては印象深かった一枚です。
まず、冒頭の"Tempus Fugit"。正直に言ってこれが理解できるのには時間がかかりました。ずっと聴き続けてきたある日、突如天啓のように理解できたというのであればかっこいいのですが、それ以前に「なんとなく勘で分かっていたもの」がパーカーの"Ko-ko"を聴いて理解できた後、これを聴いてみたら「やっぱりなー」という感じで分かってきたので、ずいぶんゆるい感じで理解したわけです。最初に聴いて印象深かったのはむしろ2曲目の"Celia"。クラシックのように典雅で、それでもジャズの活力に満ちあふれたピアノを聴いたとき「やられたー」と思いました。3曲目の "Cherokee"は以前も取り上げましたが、パーカーの"Ko ko"と違って原曲のメロディーも出てくるしずっと分かりやすいものです。もちろんバド特有の異常なハイテンションとメランコリックな気分もよく出ています。メランコリックといえば、続く4曲目の"I'll Keep Loving You"でしょう。ソロピアノで演奏されるこのバラッドは「キレイな音」だけではないバドのバラッド解釈の典型です。6曲目の「神の子」は名盤Stitt, Powell & JJでも有名で、まぁエンジン全開ですね。
特筆すべきは7曲目の"So Sorry Please"で、このアルバムの中でも"Celia"とならんで一番好きな演奏。どちらもミディアム・テンポなので、私はそれぐらいのテンポが一番好きなんじゃないかと思います。それにしてもアドリブに入ってからのピアノのすばらしさ。フレーズがピシリピシリと決まり、後のフレーズが前のフレーズを凌駕して興奮が増進してゆきます。バリー・ハリスやトミー・フラナガンを始めとした「パウエル派」のピアニスト達は、こう云うアドリブを目指していたのではないだろうか?
B面(CDでいうと後半)は有名なスタンダードで構成されていて、録音時期やベーシスト(A面はレイ・ブラウン、B面はカーリー・ラッセル)が違いますが、どちらもドラムはマックス・ローチだし、素晴らしさに変わりはありません。とりわけバラッド好きにはたまらないでしょう。ここでも見せるメランコリックなバラッド解釈はアル・ヘイグに引き継がれています。
バド・パウエルファンやピアノファン、ジャズファンのみならず、音楽ファンなら必携の一枚だと思います。
この記事で取り上げたCD
Tags: piano · Powell, Bud · Roach, Max
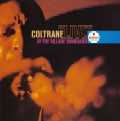
八王子のジャズ喫茶『はり猫』にたまに置いてあるジャズのミニコミ誌を読んだら「コルトレーンは受験勉強と合う」と書いてありました。あんなうるさいものを聴きながら勉強できるのかいな、それとも『バラード』のことかなと思って読み進めると「受験生のようにイライラして、どっちつかずで、下手をすると壊れて暴れてしまいそうな時には、ヒーリングや癒しと称する静かな音楽よりも、同じようにはげしく暴れ回る音楽がいいのである」と書いてあって納得しました。
私自身、受験というよりも高校時代を通してイライラし、時に壊れかけたり暴れそうになるとコルトレーンを聴いていたからです。とくに夏、暑さを背景になんとなく社会的な出来事も、学校でのことも、親との関係もおもしろくなくなってくると今日取り上げるLive at the Village VanguardのB面"Chasin' the Trane"やImpresstionsを聴きながら憂さを晴らしていました。暑い中この暑苦しくて、しつこくてうねるような音楽を聴くと全身から汗がどっと出てくるのですが、聴き終わるとさーっと汗が引いて爽快感が残るんですよね。サウナみたいなもんです(笑)。パーカーのように軽々と吹きこなしているわけでもない、マイルスのようにスタイリッシュなわけでもない、もっと鈍くさくて、でも延々と一心不乱に吹きまくっているサックスの音を聴くと、なんかジタジタと考えていることなどどーでもよくなってしまうんです。コルトレーンというと、どちらかといえば不器用な音楽家です。表現したいことが10あるとすると、18ぐらい(何を根拠に?)のことを言って伝えようとするタイプで、それが時にうるさく、時に押しつけがましく感じることがあるんです。しかし同時に、下の記事にも書きましたがコルトレーンがソロで登場すると、一挙に雰囲気や景色が変化していつも見晴らしがよくなるんですよね。少なくとも『クレッセント』や『ラブ・シュプリーム』の頃まではそうでした。その後彼が登場するとよけいに訳の分からない景色が広がったりする時期もありましたが、それでもやはり「コルトレーン登場!」という存在感は最期までなくなりませんでした。ここがコルトレーンのすごさだと思います。
ところでヒーリングミュージックというと静かで聴きやすい曲想のものが多く、こういう音楽を聴くことでいらついた精神を平穏に鎮めようということなのでしょうが、これは逆効果のような気もします。静かな音楽だと、自分のイライラをよけい対象化して見てしまうからです。音楽の本質は共鳴にあるのだから、現在の精神状態と共鳴するような音楽を聴くことでカタルシスを得る方がずっと有効だと思います。極言してしまえば、生ぬるい癒し系の音楽で癒されるようなストレスはもともと大したことないのじゃないですかね。
この記事で取り上げたCD
Tags: Coltrane, John · tenor sax

マイルスのように息が長く、多面的で絶えず変化し続けたミュージシャンを紹介するのがもっとも難しく、いったいどれを取り上るべきか、どうやって紹介すべきか考えるだけで一日つぶれたりします。私自身も、マイルスのそれぞれのスタイルに、それぞれの思い入れがあり、どれを取り上げるかで言いたいことの半分は決まってしまうわけです。たとえば"Relaxin'"を取り上げておいて、「前進し続けるマイルス」を語るのは非常に難しい。なぜなら "Relaxin'"は前進、変化ではなく「完成」というキーワードで語るべきものだからです。一日中考えあぐねて、それでも埒があかないので思い切ってマイルスを通して私的なことを語ることにしました。
この一枚ははじめて買ったマイルスのLPです。ラジオでおそらく『ブラックホークのマイルス・デイビス』と思われる演奏を聴いて感激したからでした(もちろん『ブラックホーク』だと知ったのは後のことです)。ちょうどその頃TDKカセットテープのCMにマイルスが起用されていて、いわゆる70年代スタイルで演奏しているのを耳にして「なんだかジャズと言うより、怒って掻き鳴らしている感じのするいやな音楽だな」と悪印象をもっていたのですが、ブラックホークでの詩的なミュート・トランペットを聴いて認識を改め、レコード屋に買いに行きました。しかしアルバム・タイトルをまったく覚えていなかったので、店の人に「マイルスだけれど、うるさく掻き鳴らしていない古い時代のレコードないですか?」と尋ねたら紹介してくれたのがこれでした。
一曲目、"On Green Dolphin Street"。印象的なビル・エバンス(このLPではじめて耳にしたのです)のイントロからマイルスのテーマへ。なんという緊張感のある演奏!明るいわけでもなく、暗いわけでもなく、ブルースでもない、もっと浮遊したような雰囲気。そして同じ曲を演奏しながらも、ソロで登場するミュージシャンごとに変化するカラー。とりわけ、コルトレーン(彼をはじめて聴いたのもこのLPでした)が登場するや、それまでの景色が一変して新しい風景が広がる、そのスリル。この曲を聴き終わるや、買うことに決めました(ラジオで聴いたものとは違うことは分かっていたのですが、この一曲に打ちのめされました)。
え?どういうことだって?
今の若い人は知らないかもしれないけれど、昔はLP一枚買うとき、ちゃんと店の人に検盤(傷がないか確かめる)してもらって、店が混みあっていないときは冒頭の一曲ぐらい試聴(それも店中に流れるスタイル)させてもらってから買うかどうか決めたのです。もちろん気にくわなければ買わなくてよかったし、とくにこの時のように店の紹介で買う場合は向こうとしても客に確認してもらった方が後々のトラブルもさけられるのでよかったのです。
そういうわけで、この一枚を買ってきて早速聴いたのですが、さらに私を打ちのめしたのがB面1曲目の"Love for Sale"でした。ここでもソロが代わるたびに演奏のテクスチュアリティー(肌触り)が刻々と変化します。テンションの高いマイルスのミュート・ソロから、キャノンボールに替わるやはっちゃけて少しせわしない演奏になります。そしてコルトレーン登場。この雰囲気の変化はどうでしょう?ドラムのジミー・コブもあわせて奏法を変え、リムショット中心の叩き方に変化します。
私はこの一枚で、本格的にジャズにのめり込みました。ビートルズ小僧を経て、スイングジャズやサッチモをちらほら聴いていたジャズ小僧が、ついに引き返せないところにまで来てしまいました。マイルスに、エバンスに、コルトレーンに捕まってしまったのですから(笑)。そして、その奥にはパーカーが、バド・パウエルが待ちかまえていたのですから。
Tags: Adderley, Cannonball · Coltrane, John · Davis, Miles · Evans, Bill · trumpet
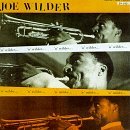
"Cherokee"という曲はスイング時代に作られたもので、「インデアン組曲」の一曲としてレイ・ノーブルが作曲したものをチャーリー・バネットが得意の粘っこいソロで演奏して大ヒットしたものです。ベイシーもレスターをフィーチャーした録音(憎らしいことにレスターのソロがA面B面にまたがって分割されている・・・)を残しています。しかし、私たちジャズファンにとってチェロキーが特別な意味を持つのはやはり、パーカーがその名も「ココセッション」において前人未踏の演奏を繰り広げたからでしょう。「ココセッション」とは「ココ」という曲が演奏されたセッションということで、その「ココ」こそチェロキーのコードに基づいた曲(というよりインプロビゼーション一発)なのです。この間の事情についてはブログ「二つのチェロキー橋」に書いていますが、パーカーの「ココセッション」を受けて偉大なジャズメン達が次々とチェロキーのブリッジを渡っています。代表的なのはブログで取り上げたパーカーとコニッツですが、そのほかバド・パウエルの『ジャズ・ジャイアンツ』、クリフォードの『スタディー・イン・ブラウン』も欠かせないと思います。いちいちのアルバムについては近く取り上げます。私はロープではないのでこの曲のいったいどこがそれほどジャズメンを惹きつけるのかいまいち分かりませんが、少なくともパーカーの「ココ」がなければそれほど触発されて演奏されることもなかったように思います。なにせ皆、パーカー追いつけ、追い越せとばかり「チェロキー橋」を猛スピードで渡っているんですから。
そんな中でパーカーのココもどこ吹く風とばかり、チェロキー橋で優雅に踊っているような演奏が今日取り上げるジョー・ワイルダーのWilder 'n' Wilderです。まず、ココセッションを知っている人は冒頭の"Cherokee"を聴いてみて下さい。ココを含む偉大なチェロキーがみな「必死」であるのに対して、ワイルダーのチェロキーはなんとのんきで典雅なことでしょう。大橋巨泉氏の分類からいえば「中間派」ということになるんでしょうが、その割に結構新しい音使いをしています。そしてジャズをあまり聴いたことない人も聴いてみて下さい。こんなに流ちょうで歌っているトランペットを聴いたことがありますか?ワイルダーのペットは「トランペット、トランペットしていない」、つまりハイノート(高音)ヒットばかり狙うトランペット職人とは反対の方向にあるんですね。基本的に中音域、声と同じ音域で歌いかけるように吹いています。一見地味なようですが、滋味に通じる優れた演奏だけで構成されているアルバムです。
サイトメンはハンク・ジョーンズのピアノ、ウェンデル・マーシャルのベース、そしてドラムはケニー・クラークです。ケニーはいつもみたくオカズだらけで、最初は美味しいけれどだんだんお腹いっぱいになる叩き方ではなくて、ぐっと押さえて叩いています。その分名手だけにツボを押さえた演奏になっているので聞き逃せません。こういうのを隠れた名盤というのだと思いますが、最近はCDで手に入れやすくなっています。
Tags: trumpet · Wilder, Joe
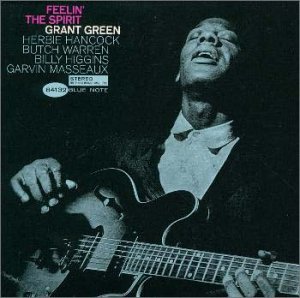
今ではたまに自分でも弾いたりしていますが、ジャズギターには長い間アレルギーがありました。たぶん、最初に聴いたジョン・マクラフリンがやけに小うるさく感じられたのと、渡辺香津美の狙ったような外し方に理屈っぽさを感じたからだと思います。そこでジャズギター=マージナルのルサンチマン(なんのこっちゃ?)という図式が自分の中で出来上がりずっと敬遠していました。結局チャーリー・クリスチャンを歴史的に聴く以外ほとんどギターを聴くことはなかったのです。
この印象が一変したのはここで取り上げるグラント・グリーンの『フィーリン・ザ・スピリット』を「メグ」で聴いたときのことでした。それまで抱いていたような理屈臭さ、小うるささがない、それどころか反対にきわめて感覚的で単刀直入な演奏に目から鱗が落ちる思いでした。こういうところにもジャズ喫茶の良さがあるのです。自分の好みだけで聴いているとどうしても偏ってしまい、私のようにジャズギターに偏見があったりするとそれだけで聴く機会を失ってしまうものも多い。しかしジャズ喫茶で500円分の元だけは取ろうと長く居座っていると、自然にいろいろなタイプの演奏を耳にすることになり、聴かず嫌いを治すこともできるわけです。『フィーリン・ザ・スピリット』は全曲「黒人霊歌(ニグロスピリチュアル)」で構成されていて、曲自体も単純な構造のものばかりです。そこへもってきてグラント・グリーンのわかりやすいギター。頭よりも、ハートやおなかにくるタイプのジャズです。
一曲目の"Just a Closer Walk with Thee"はニューオリンズ・リバイバルの頃ジョージ・ルイスがよく取り上げていた曲です。ミディアムテンポで軽快にソロを取っていきます。ピアノはハービー・ハンコック。難しいハンコックではなく、カンタロープやウォーターメロンハンコックで弾いています。二曲目はコールマン・ホーキンスの演奏でも有名な"Joshua Fit de Battle of Jericho"。「ジェリコの戦い」という邦題の方がわかりやすいでしょう。ここのイントロはハービーですがそのまま「カンタロープ」突入しそうな感じがしておもしろい。三曲目の"Nobody Knows the Trouble I've Seen"(誰も知らない私の悩み)はサッチモがむかし歌った曲です。ここでの演奏はそのサッチモ版を越えていると思います。イントロからテーマ、アドリブまでずっとギターとピアノの絡み合いで進み、二人のブルース・フィーリングが堪能できます。「メグ」で聴いた折りも、この演奏を聴いて「ユニオンで買って帰ろう」と決意しました。 音使いもシンプルで単純な演奏ですが、ソロを順番に取るのではなくグラントとハービーが同時にソロを取っていて、二人のコラボレーションが際だった名演です。
ギターフリークからは「大したテクニックもない」などと馬鹿にされることも多いグラント・グリーンですが私のお気に入りギタリストです。
この記事で取り上げたCD
Tags: Green, Grant · guitar
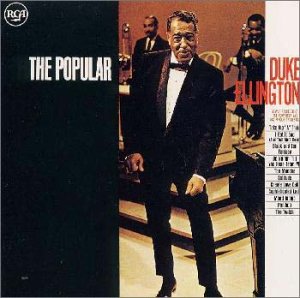
エリントンを聴くときにははずせない一枚です。ちょっと見ると「ヒットパレードのコンピレーション」じゃないかと思ってしまいますが、実はある決意をもって入念に仕上げられた作品なのです。詳しいことは油井先生の『ジャズ歴史物語』(絶版)で述べられていますが、この吹き込みの前にフランスの批評家アンドレ・オデールとエリントンの間でちょっとした論争がありました。簡単にいうと、その頃のエリントンの姿勢を「過去の安直な焼き直し」「焼き直しどころか改悪すらしている」とするオデールによる批判でした。エリントンは一度雑誌で反論しますが、その後沈黙します。そして、音楽家らしく演奏をもってオデールに再反論したのがこの「ポピュラー・エリントン」です。そのため、一曲として昔のままの再演という録音はありません。
まず、冒頭の"Take the 'A' Train"。エリントンが延々ピアノソロでイントロを取ります。このピアノソロの斬新なこと。ちょっと前衛的な雰囲気すら漂い、難しい音を駆使しています。かつてうちに遊びに来た某ピアニストは、この演奏を10回も聴いて大絶賛していました。3曲目の"Perdio"や4曲目の"Mood Indigo"ではジミー・ハミルトン、ラッセル・プロコープのクラリネットが清澄でいながらワイルドでエスニックなサウンドを出しています。
そして問題の"Black and Tan Fantasy"。これは古い曲で題名「黒と茶の幻想曲」からも分かるとおり、アメリカにおける黒人とネイティブアメリカンの衰退を描いたもので、悲痛なトーンで演奏が進み最後は葬送行進曲で締めくくられるものでした。ところが、ここでの演奏は本来終わるはずのパートから徐々に力強さを増して、クーティー・ウィリアムスの圧倒的なトランペットで堂々たるクライマックスに達します。これは黒人達を巡る当時の状況の変化を示していておもしろいと思います。この演奏が吹き込まれたのが'66年、公民権運動のまっただ中であったわけで、時代思潮も影響してこのように力強い演奏になったのでしょう。
7曲目"Solitude"は私の大好きな曲で、ビリー・ホリデイの歌とロリンズの演奏の二つが最高峰だと思いますが、この演奏はそれに次ぐ名演です。8曲目の"Do Nothing till You Hear from Me"と10曲目---ミュージカルのタイトルにもなった代表曲---"Sophisticated Lady"も普段とは違う構成で臨んでいるところにエリントンの意気込みが聞こえてくるようです。そしてラストの"Creole Love Call"。オリジナル演奏ではアドレーデ・ホールがスキャットを歌いエキゾチシズムを強調した演奏であったのに対して、ここではクーティー・ウィリアムスのトランペットとラッセル・プロコープのパワフルなクラリネットを使い「黒人の愛」を堂々と歌い上げています。
このアルバムは、最初に聴くエリントンとしてもバランスのよい構成ですが、上で述べたように新しいものに挑戦しようとするエリントンの意気込み、そして60年代のアメリカ社会の息づかいまでもうかがえるような本当の名盤だと思います。
この記事で取り上げたCD
Tags: big band · Ellington, Duke
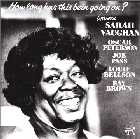
ぐぅ~む・・・・・このジャケット、パーマ当て損なった男ですよね?レーベルはパブロといってノーマン・グランツという、ジャズ史上二番目ぐらいにエライプロデューサーが設立したレーベルなのですが、ここのジャケットはあまりに散文的すぎて、しばしば糾弾の的となっています。
私がこのアルバムを知ったのは中学2年生。こどもの頃です。当時買っていた(買ってもらっていた)ジャズ雑誌があって、そこに新譜として載っていました。アルバムを買うお金なんてない中学生のこと、いろいろなジャズ番組をFMで狙い聴いているうちに出会いました。うーーむ、いい男性ボーカル・・・・・・・サラ・ボーンが女性だと知ったのはそれからかなり後のことです。やはりFMラジオでサラを紹介しながら「彼女」と言っているのを聞き咎めて、やっと女性だと気づきました。それまではジャケットとヴォイスの印象でずっと男だと思っていたわけです。
おそらく印象的に言って「ジャズボーカルの典型」といえばサラ・ボーンだと思います。このアルバムはサラとしては後期の「パブロシリーズ」の一枚です。このほか、「枯葉」「ウィズ・カウントベイシーバンド」「デューク・ソングブック」「コパカパーナ」などがありますが、このシリーズの最高傑作はこの一枚です。
一曲目"I've Got the World on a String"。もうこの一曲で十分です。サラの歌は自由自在にリズムを伸縮していきます。声は私に男だと思わせた低音も豊かに高音まで少しもひっかかることなく続いてゆきます。さらに驚くべきはバック。オスカー・ピーターソン、ジョー・パス、レイ・ブラウン、ルイ・ベルソンが綺羅星のごとく並びすごいソロを取っていくところも聞き逃せません。
3曲目の表題曲"How Long Has This Been Going on?"はラテン調にアレンジされていますがサラは軽快に歌っています。5曲目の"Easy Living"は私のもっとも好きな曲の一つですが、そのイメージはビリー・ホリデーの歌にあるわけです。一方、サラはビリーとは全く違うアプローチでこの歌に挑んで成功しています。7曲目の"My Old Flame"もビリーの歌で有名ですが、ここでのサラはもてるテクニックを全てつぎ込んで歌っています。テノール歌手並といわれる自慢の低音からファルセットまで駆使して捏ねに捏ねていますが、ちょっと押しつけがましいというか、後期サラボーンのよくないところ、すなわちテクニックが全面に出過ぎてちょっとやりすぎてしまう欠点が出ています。最初は驚くんですけれどね。
サラ・ボーンはどこからはじめてもいいジャズ・シンガーですが、もし最初に聴く一枚ということであれば、これをお勧めします。彼女の歌い方こそ「ろいく」のイデアであり、なかなか出せないフィーリングなのです。
この記事で取り上げたCD
Tags: Peterson, Oscar · Vaughan, Sarah · vocal
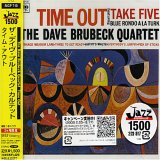
当初サラ・ヴォーンを取り上げようと思っていたのですが、第5回(take5)ということでこのアルバムにしました。そう、名曲、そして名演の"Take Five"が入っているアルバムがこれです。アルバム全体が変拍子の曲だけで構成されていて、ともすると「キワモノ」になりかねない状況を救っているのは、やはりポール・デスモンドの歌心ですかね。
このアルバムは「名盤百選」風のアルバム紹介には必ず顔を出すおなじみさんです。高校の音楽の授業でも「ジャズ」ということでこのアルバムと、ジャック・ルーシェの「プレイ・バッハ・シリーズ」を聴かされましたが、当時すでにパーカーやバド、マイルスにコルトレーンを聴いていた私としては「どうしてそうやってピントをはずすかなぁ?」という釈然としない思いを抱いてました(笑)。
いま聴いてみると、"Take Five"のみならず、一曲目の「トルコ風ブルーロンド(Blue Rondo a la Turk)」なんかも実に巧みに計算されていますね。クラシック風のパートでテンションを高め、それに対してポール・デスモンドのブルージーなソロがリラックスさせるという構成の妙があります。二曲目の"Strange Meadow Lark"は優しい気持ちになれる演奏です。そして"Take Five"。ダダッダダドゥダの5拍子の曲は、一般的な4ビートの曲以上に「ジャズ」のイデアとなっているところがあります。以前もアリナミンのCMで使われていましたし、「ジャズらしさ」を出したいときにこの曲はよく用いられます。なにせかっこいいですからね。作曲はアルトのポール・デスモンド自身。アルバム全体のハイライトとなっています。
この記事で取り上げたCD
Tags: Brubeck, Dave · group · piano
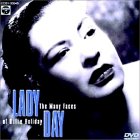
ビリー・ホリデイはいろいろと面倒です。時代によってかなりスタイルが違っているだけでなく声質も相当変化していて、あるアルバムを薦めたからといって、それが薦められた当人のツボとマッチしていないと、後で「どうだった?」と訊いても曖昧な返事しかもらえないわけです。とりわけ、リズムと声質というのは生理的な好き嫌いに支配される傾向が強く、好きになればとことん好きになるのですが、一度嫌悪感をもってしまうとそれを払拭することはなかなか難しいものです。
ビリー・ホリデイは大きく分けて三期あり、声もバックのスタイル(特にリズム関係)も大きく異なります。第一期は「ブランスウィック・セッション時代」で、彼女はセッションの一員として歌っています。個人的にはこの時期が一番好きなのですが、声は若々しいもののリズム周りがちょっと古めかしい。第二期は名盤「コモドア・セッション」とラバーマンを含む「デッカ時代」が来ます。この時期は「トーチソング」といって身も焦がすような恋愛の歌がメインで、バックもビッグバンドやストリングスなど分厚く、個人的には「ちょっとドロドロして重たいサウンドだな」という印象の録音が多いと思います。つづいて第三期はノーマン・グランツのもとで新境地を拓いた「ヴァーヴ時代」。バックの編成が第一期と同じようにスモール・コンボに戻り、リズムも新しく聞き易い録音が多い時代です。そしてそのラストに真のビリーファンしか聴かない方がいい「レディー・イン・サテン」と「ラスト・レコーディング」が来ます。
という面倒な歌手なのですが、このDVDを観れば一発でスタイルの変遷と合わせて彼女の人生がたどれます。カーメン・マクレエやアニー・ロスといった歌手仲間、ハリー・スイーツ・エディソン、バック・クレイトンらベイシーバンド時代の同僚のインタビューを中心に構成されています。映像も垂涎ものが多く、彼女の映像は当然のことサッチモとの共演映画、「動く」伝説のベッシー・スミス、レスター・ヤングなど多数収録されています。とりわけうれしいのは「"ファイン・アンド・メロー"セッション」がフルに収録されている点で、彼女の歌の合間を縫ってベン・ウェブスターが、レスターが、ロイ・エルドリッジがソロを取っていきます。ソロは取らないもののコールマン・ホーキンスや若き日のジェリー・マリガンも写っています。仲間がソロを取っているときのビリーの表情、カメラが彼女の背中をかすめたらしく「キャッ」という感じで笑う表情、そして歌う表情。これらが余すところなく舐めるように映像化されている貴重なフィルムです。
ビリー・ホリデイを最初に聴く(観る)ならこれ。音と文字情報(悲惨な人生の伝記)だけでイメージを作りあげてしまった人も、この映像を見れば印象がひっくり返るはずです。
この記事で取り上げたDVD
Tags: Holiday, Billie · vocal
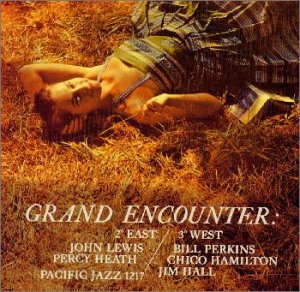
西海岸のパシフィックというレーベルには美麗ジャケットが多い反面、内容はほんわかし過ぎて食い足りないものが多いという印象があります。ブルーノートはともかくプレスティッジや同じ西海岸のコンテンポラリーに比べてもガツンとくる作品の比率が低いことはたしかで、こうした印象が積分的には正しいのは事実です。
しかし微分的にはジャケット・内容ともに優れた作品があり、今日挙げたこの『グランド・エンカウンター』もその一枚です。一曲目の"Love Me or Leave Me"。ピアノがジョン・ルイス、ベースがパーシー・ヒースということもあり、MJQ的なイントロとテーマの直後に入ってくるビル・パーキンスの渋くて丸いテナーサックス。理想的なテナーではないですか?この一曲だけでもアルバム全体の価値があるでしょう。
つづく"I Can't Get Started"はピアノトリオですが、ジョン・ルイスらしい典雅な演奏の中に時折見せるMJQ的サウンドが特徴。さて次の"Easy Living"はビリー・ホリデイとレスター・ヤングの演奏が有名ですが、レスターを師匠・アイドルとするビル・パーキンスがサブトーンも豊かに名演を聴かせます。そのあとのブルース"2°East /3°west"でタネ明かしがされます。つまり、このメンツは東海岸の二人の人間(ジョン・ルイスとパーシー・ヒース)と西海岸の三人の人間(ビル・パーキンス、チコ・ハミルトン、ジム・ホール)の「大いなる邂逅(grand encounter)」であったと。この一曲がアルバム全体のハイライトではないですか?たんに私がブルース好きという話もありますが(笑)
ジャケットは中西部の美人娘が干し草か牧草の上で、ペーパーバックを脇に置いて微笑みかけている写真です。もちろん写真家はウィリアム・クラックストン。ジャケットといい演奏といい一枚のアルバム作品として完璧に近い出来です。ただ一点問題があるとすれば、このアルバムを聴いて「テナーのビル・パーキンス」に惚れてはいけないということです。この一枚に惚れて、それでなくとも見つけづらい彼のアルバムを見つけ、片っ端から買い込んだとしても、この一枚に匹敵するような満足感は得られません。ここでのビルはいつもと違うんです。いや、畢生(ひっせい)の名演をしちゃったんです。アート・ペッパーのように、ある日憑き物が落ちたように全然フレーズがでなくなるミュージシャンに対して、彼はある日突然憑き物がついて名演をしてしまったんですね。秋吉敏子が自分のバンドの「テナー」ではなく「バリトン」として彼を迎えたことが理解できます。
最初の100枚に入っていていい一枚です。
この記事で取り上げたCD
Tags: Lewis, John · piano