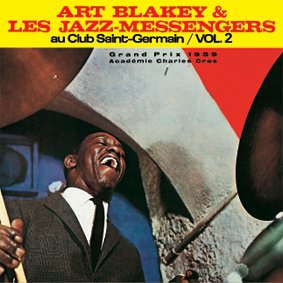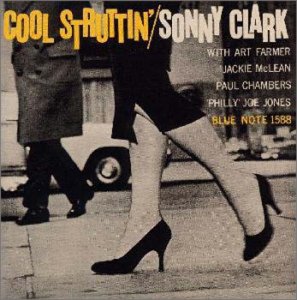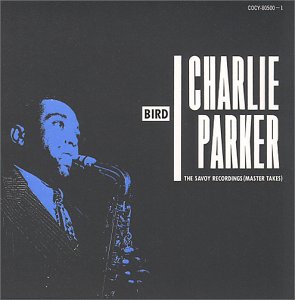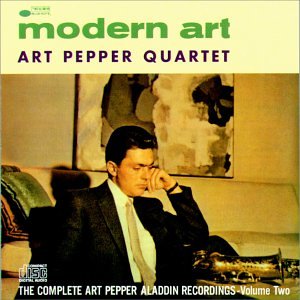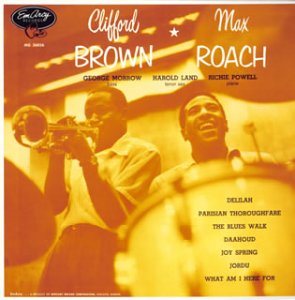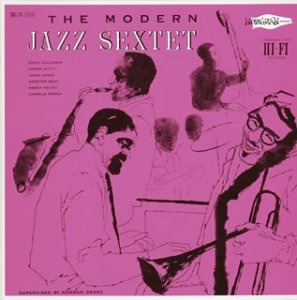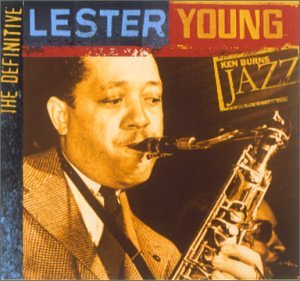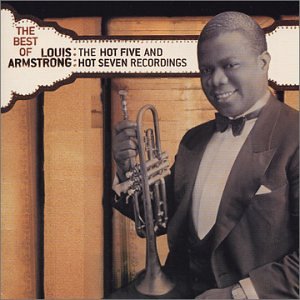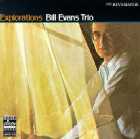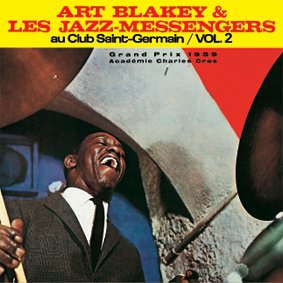
もう一つ60年代の気分を表すのが"Moanin'"という曲です。作曲はボビー・ティモンズ。ジャズ・メッセンジャーズのピアニストです。ブルーノートのアルバム『モーニン』が火付け役となり、62年の正月にジャズ・メッセンジャーズが来日するや日本中が「ファンキーブーム」になったといわれ、油井先生の表現を借りれば「そば屋の出前持ちまでも、モーニンを口ずさんだ」という話です。まぁしかし、たまたま油井先生が行き違ったそば屋の出前持ちが熱狂的なジャズファンだったという可能性は依然として残りますね。
「ファンキー」という言葉はもともと「たばこ臭さ」を意味するフランス語から来ているといわれていますが、簡単にいうと「臭い」という意味です。この場合は黒人的な体臭の強い音楽、リズムに粘りがあって音もブルーノートを多用して黒っぽいジャズを指すのですが、その傾向の原点とも言えるアルバムがブルーノート盤『モーニン』なのです。本当はこれを紹介してもよかったのですが、それ以上に盛り上がっていて当時の空気を伝えているのアルバムがあるのでそちらを紹介したいと思います。私自身、BN盤「モーニン」はラジオで散々かかるので、テープにとってそれを聴いていました。最初に買ったジャズ・メッセンジャーズのレコードは今日紹介する方のアルバムです。本アルバムはジャズ・メッセンジャーズが渡仏した際、パリの「クラブ・サンジェルマン」で行った演奏のライブ録音。メンバーはBN『モーニン』と同じく、リー・モーガンのトランペットとベニー・ゴルソンのテナーという構成です。唯一違うのは、ここにもう一人新しい参加者がいることで、それはヘーゼル・スコットというピアニストですが、ここではピアノを弾いていません。客として来ていて一人おお盛り上がりで騒いでいる女性です。録音でもばっちり捕らえられていて、彼女の大騒ぎぶりがはっきり聞こえるので、この「モーニン」の正式なタイトルは "Moanin' with Hazel" となっています。
しかし、この騒ぎ。曲テーマなんか一緒に歌っちゃっています。アドリブに入っても延々騒ぎ倒して、最近話題の「引っ越しさん」顔負けのうるささです(笑)。同じピアニストということで、ボビー・ティモンズのソロになるとさらにヴォリュームアップして、挙げ句の果てに "Oh Lord, have mercy"(主よ哀れみを賜え)なんつうお祈りの言葉まで叫んで、それがきっちり録音されてしまっています。ティモンズも煽るようなソロを取ってます、わざと。もっとも、"Moanin'"という曲名自体、黒人教会で現世の辛さを嘆くことを意味していますから、あながち間違った叫びでもないのですね。いずれにせよ、日本のライブハウスで同じ調子だったら、周りから「シーッ」ととがめられそうな勢いで乗っています。
「クール・ストラッティン」に「ブルー・マイナー」があるように「モーニン」と対になるのがB面の "Blues March (for European No. 1)" です。これもまたオリジナル以上に乗りに乗った演奏で興奮します。その他の2曲 "Evidence" と "Like Someone in Love" ですが、どちらも演奏の繊細さと複雑さという観点に立っていえば、「モーニン」や「ブルース・マーチ」以上の出来を示していると思います。とくに、やはりというべきかリー・モーガンのペットはここでも冴えていますね。どちらもクリフォード直系の旋回するアルペジオに、彼の個性である「クイクイ上がる語尾」を付け加えていますが、「モーニン」の場合のように下品になりすぎず非常に好みのソロです。ベニー・ゴルソンはどうかというと、あんな繊細な作曲・アレンジ能力があるのになぜかソロは常にラフ・プレーであまり好みではありません。
『モーニン』もいいですが、ライブということで時代の空気が缶詰されているのはむしろ、この『クラブ・サンジェルマン』だと思います。推薦!
Tags: Blakey, Art · drums
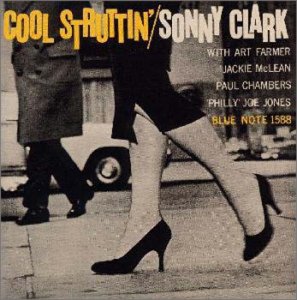
このアルバムと、次に紹介するアルバムは「時代の気分」を濃厚に現した伝説的な名曲が収められているものです。本アルバムではタイトル通り "Cool Struttin'"、もう一枚のアルバムの選択は少し変化球ですが "Moanin'" がその名曲にあたります。
東芝EMIでは現在「ブルーノート決定盤1500シリーズ」と銘打って、名門レーベル・ブルーノートの必聴盤を1500円で売り出しています。2300円とか、2500円払わされてきた身としては若干納得がいきませんが、よく考えれば私が高校生で少ない小遣いやバイト代でこつこつ買っていた20年以上昔でも、やはり2000円前後であったことを考えると、レコード業界も努力しているなと思います(一方で流行歌の方は値上げがはげしくて、去年買ったサザンの「夢に消えたジュリア」など1200円も取られました。ドーナツ盤は700円ぐらいが相場だったように記憶しています)。さて、その決定版シリーズの中でも常時トップに来る一枚が「クール・ストラッティン」です。日本独自の文化であるジャズ喫茶を中心として60年代に大ヒットした一枚だといわれています。私自身はまだ生まれてない頃なのでその空気を体感することは出来なかったものの、聴いてみれば「なるほど、これはヒットするだろうな」と実感できるような演奏です。
タイトル曲である「クール・ストラッティン」。ブルースです。一度聴けば決して忘れないあのテーマがウォーキング・テンポで演奏されると、「ああ、あの時代だなぁ」とまだ生まれてもいない時代に思いをはせます(笑)。メンバーのうちジャッキー・マクリーン(as)とソニー・クラーク(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)は普段も仲がよく年がら年中遊び歩いている仲間だったそうで、そのメンツがこれまた手慣れた「Fのブルース」をあのテンポでやれば名演が生まれないわけない。案の定、ソロが始まると彼らの間にある共通の気分が流れ出し、循環し、ソリストとリズム隊の間を巡っていきます。この共有された気分こそグルーヴ感と言うべきものなのです。そこでは、各人がくつろいで自分のいいたいことを言っていると同時に、相手の出す音にも敏感で互いに反応しあっていくわけです。グルーヴ感というものは、音楽はもとより、詩や小説、演劇美術、あるいはスポーツ、そしてスピーチや講義、恋愛やセックスにも発生するものです。これが発生しないとちっとも気持ちよくないんですよね。独りよがりな芸術、つまらない講義、自己中心的な恋愛というのはすべてグルーヴしていないのです。「クール・ストラッティン」にはそのグルーヴがふんだんに溢れていてそれが快感をもたらします。
ソロのトップはリーダーのソニー・クラーク。出だしということでずいぶん押さえめのシンプルなソロになっています。次がアート・ファーマーのペット。彼のもつある種の上品さ、抑制感がこの演奏のポイントとなっているように思います。というのも、もしこれがリー・モーガンで語尾をクイクイ上げまくっていたら、次に来るのがマクリーンですから、ねちっこさ、下品さが倍増して10分間(演奏時間)耐えられなくなっていたかも知れません(笑)
さて、マクリーンのアルトソロ。しょっぱい音色でピッチも怪しい感じがしますが、それをコミで聴くのがマクリーンの正しい鑑賞法です。語尾にクルリと小節を効かせるマクリーン節全開で、乗りのよいソロを取ります。再びソニー・クラークがソロに入ります。前回のソロとは違って3連符を多用し、タメにタメた粘っこくて黒人的なソロ。そのあとがポール・チェンバース。前半をアルコ(弓)弾きで、後半をピチカート(指弾き)のウォーキングで演奏します。これらのソロ、よく聴けば一人一人がすごいソロを取っているわけではなく、その一人一人の間を循環する気分がすごいということが分かります。2曲目の "Blue Minor" も実に名演。こういうマイナーキーの曲になるとマクリーンの「泣き」がよくフィットして感動的なソロになります。LPではこの二曲がA面を構成していて私も繰り返し繰り返し聴いたものです。このA面全部が「クール・ストラッティン」という一つの曲だと考えても差し支えないでしょう。
そのせいかB面をほとんど聴いたことがなく(笑)、ある時J-Waveをつけっぱなしにして勉強をしていたらどっかで聴いたような曲が流れてきて、これまたとてもいい演奏なので曲名を確認したところ、本盤のB面にある "Deep Night" でした。曲もいい感じで、最初スタンダードのコードを借りたオリジナルだと思ってライナーを見たら、これ自身がスタンダードでした。
ジャズ全体に多かれ少なかれ流れる気分。この気分をつかむのにこのアルバムは最適です。
Tags: Clark, Sonny · piano
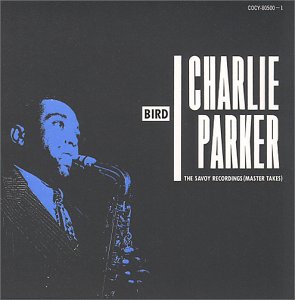
ジャズ史上最も重要なレコードの一枚です。'40年代初頭、ジャズ界ではのちに「ビ・バップ革命」と呼ばれる音楽上の革命が起きていました。その走りはチャーリー・クリスチャン(g)で、彼の弾くギターは斬新なコード感覚にあふれていました。簡単に言えば「え、そこでそんな音使うの?」という音、今まではふさわしくないと思われていた音を盛り込むことでそれまでのジャズ(スイング音楽)にはない感覚を導入したのです。さらに、それを押し広げたのがチャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンク、バド・パウエル達であったといわれていますが、中でもパーカーは新しい感覚の音を、それにふさわしい場所で自在に使いこなし、その上に超絶技巧(パロテクニック)を駆使することでたちまちジャズ界のリーダーになりました。
ここで、「ビ・バップだ新感覚だと言われたって分からないよ」という人は1~4曲目を聴いてみて下さい。これはバンド自体は古い感覚で演奏しているのに対してパーカーのソロだけが新感覚になっている演奏です。バンドの合奏や歌がベッタリして、よく言えば地に足のついた、悪く言えばのそのそした演奏なのに対して、パーカーのソロだけは30センチぐらい空中に浮かんでいないでしょうか?この感覚に新しい物好きは大喜びし、保守派は頑固に抵抗したというのがジャズの史実です。偉大なプロデューサー達でさえバップが登場した頃は「リフを繰り返しているだけ」と批判したとか、その音楽的な成果よりもディジーのベレー帽と山羊髭に注目が集まり、「ベレー帽とあごひげで訳の分からない言葉を話すバップ族」などと評されたとも言われています。
1~4曲目までは伝統的な音の使い方とパーカーのバップを対比するのに格好の材料ですが、バップの理念が具現化したような演奏は5曲目以降の「ココ・セッション」です。 "Warming up a Riff"。チェロキーのコードを使ってウォーミングアップをしています。即興演奏です。途中バックで笑い声が聞こえますが、何かの引用か符丁を吹いてバックミュージシャンが反応したのだと思われます。6曲目の "Billie's Bounce" と7曲目の "Now's the Time" はFのブルースでパーカーのブルース演奏の典型です。私は「ビリーズ・バウンス」を延々練習し、練習しすぎてFのブルースを吹くと必ずこのフレーズが飛び出してしまいます(笑)つづく8曲目の "Thriving on a Riff" は通常 "Anthropology"(人類学)と呼ばれている曲で、いわゆる「B♭循環」という構成の曲です。冒頭からアドリブで始まり曲テーマは最後になって出てきます。9曲目 "Meandering" はスローテンポの曲でバップにおけるバラッド解釈がはっきりと現れた演奏です。
そしてジャズ史上最も重要な演奏の一つ "Koko" が来ます。これはあちこちで書きましたが原曲は「チェロキー」。チェロキーのフレーズは出てきません。これには理由があります。実は「ココ」には(にも)別テイクがあって、最初のテイクでは緊迫したペット(ディジー)とアルトのあと、のんきな「ターララ・ラーラー」っていう「チェロキー」のテーマが演奏されるのですが、曲の使用料支払いを恐れたプロデューサーが「ヤメロ!ヤメロ!ヒュー(口笛を吹く音)」と割り込んでくるところで録音がカットされています。これがテイク1。もちろん30秒程度のNGですからこのCDには収録されていませんが、これは面白い演奏だと思います。なぜならイントロは「ココ」と変わらない緊迫感があるものなのに対してあのチェロキーのテーマはあまりにも間延びしているからです。穿った見方をすれば「ボツになる」のを承知でわざとあの演奏を残しておいたのではないか?そうする事によってテイク2で繰り広げる「ビバップ」との対比を際だたせ、自分たちが今成し遂げようとしていることが一体どういうことであるのかを満天下に示そうとしたのではないかと思えるのです。
それだけの緊迫感が「ココ」のテイク2にはあります。最初聴いたときには、こんなのせわしないだけで一体何吹いているのか分からない、という印象を抱きました。その後1年ぐらいこの演奏は気にも掛けずにいたのですが、大学一年生の時ラジオを聴いていたら「ココを聴かずしてジャズを語るな」みたいな発言がされているのを聞き咎めて、「そういえば家にあったなぁ(寮生でしたがLPは全部実家に置いてありました)」と思いだし、冬に帰省したときにずっと聴き続けました(「ココ」だけじゃないですがね)。そしてある時、ふとそれまで勘で分かっていたようなことがリアリティーをもって理解できたのです。それはバップのコード、リズム、テンポを駆使することで生まれる独特のテクスチュアリティーということでした。このテクスチュアリティーはどれが欠けても生み出すことは出来ないし、それが一瞬のアドリブで行われるからこそリアリティーをもち得るのだということでした。このリアリティーは一般にグルーヴと呼ばれるものです。そして、いったん「ココ」が分かってしまうと先のスローテンポな「ミアンダリング」にさえ、いやスローな曲ほどベースにものすごく細分化した急速なビートが流れていることが感じられるようになったのです。さらには、ポップスや歌謡曲においても、どれが「だるい曲」でどれが「いけてる曲」であるかも分かるようになりましたし、クラシックで聴き比べなどしなくても一回聴けば、どの指揮者や演奏家が「乗って」いて、どの演奏家が「営業的」なのかがなんとなく分かるようになってきました。
さて、これ以降の曲もそれぞれに思い入れがあるのですが、実際に聴いてみるのが一番速いので、これ以上くどくどと曲目解説はしないでおこうと思います。11~13曲はバド・パウエルを含む「ドナリー・セッション」。ディスク2枚目の1~4はマイルス名義の録音でパーカーはテナーを吹いています。12曲目の "Parker's Mood"。Bフラットのブルースで超スローですが、その底流にものすごいスピードが流れていることはこの録音を聴けば理解できると思います。このアルバムもまた、音楽ファン必携の一枚(二枚)です。
この記事で取り上げたCD
Tags: alto sax · Parker, Charlie
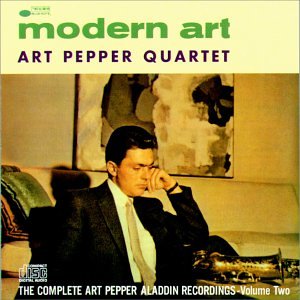
世間の評判はいいのに、自分にはピンと来ない作品というのもいくつかあります。もっと若くて血気盛んな頃は「あんなの誉めるなんて、気が知れない」と言わずもがなを言い歩いてトラブルを引き起こしていましたが、最近は少し大人になったせいか「これは私には縁がないようです」ぐらいで済ましていられるようになりました。アート・ペッパーで言うと最高傑作との誉れも高い Art Pepper Meets the Rhythm Section の良さが私にはちっとも分からずに困っています。吹き方もアート独特のきめ細やかな吹き方ではなくて、無理してハードに吹いているという感じです。リズムもマイルスのところでやっているほどの高い緊張感を維持しているとはとても思えず、いいのはデュナンの録音だけじゃないかと思えるほどです。しかし、きっとこれは私と縁がないアルバムだからでしょう。コルトレーンの『バラード』と同じです。
一方、この時期のアート・ペッパーで私が自信を持って推薦できるのが、今日取り上げる『モダン・アート』です。イントロ原盤で、LP時代には幻盤扱いされていました。私もなかなか手に入らずに千葉市内をうろついていたところ、街角の寂れたレコード屋のジャズコーナーにひっそりと置いてあって、ふるえる手つきでこれを買った思い出があります。まず、ジャケットがかっこいい。ボタン・ダウンのシャツの上にサキソニー地のスーツというブルックス・スタイルのアートがうつむき加減でポーズを取っていて、その脇にはアルト・サックス、背後にはアルバム・タイトルを暗示する「現代芸術(モダンアート)」の絵画が掛かっているわけです。この時点で既にヘロヘロジャンキーだったとは信じられないぐらいのかっこよさです。
一曲目の"Blues In"。ベン・タッカーのウォーキング・ベースのみを従えてアートがブルースを吹きますが、この構想力はどうでしょう!アウトラインぐらいは描いてあったのかも知れませんが、実にすぐれたインプロビゼーションです。この汲めども尽きぬフレーズの泉とニュアンスこそアートの特色です。二曲目の"Bewitched, Bothered and Bewildered"(魅せられて)というアリタレーション(頭韻)を踏んだタイトルのバラードでも、アートはニュアンスに富んだソロを取ります。ここではまた、ウェスト・コーストの雄、ラス・フリーマンのピアノもすばらしい。三曲目は"Stompin' at the Savoy" (サボイでストンプ)。アートのソロは、まるで歌詞を歌っているようにはっきりしたラインを持ったフレーズの連続です。つづく"What Is This Thing Called Love"はLP時代A面のハイライトとなっていました。ちょっと早めのテンポでマイナーキーと来ればアートの得意とするところです。後半には4バースが入ったりして盛り上がる演奏です。5曲目はLPの時にはB面のラストとなっていた"Blues Out"。 "Blues In"と同様にウォーキング・ベースだけを従えたインプロビゼーションですが、「イン」とは対照的に、グロールトーンやフラジオも使った力強いブルース演奏です。LPでは「イン」から始まって「アウト」で終わるという構成がはっきりとしていたわけです。
6曲目の"When You're Smiling"はレスターの名演で知られた曲です。リー・コニッツなどは自分のアルバムで、レスターのソロをまるまるコピーしてギターとユニゾンで吹いているほどですが、アートの演奏はそこまで丸分かりではないもののレスターの影響が顕著に現れたソロを取っています。7曲目の"Cool Bunny"は"Love Me or Leave Me"か何かのコードを使ったオリジナル曲です。"Diane's Dilemma"は"All of Me"でしょうか?コード進行に沿ってメリハリのついた演奏が繰り広げられます。
レコードではこの後「ブルース・アウト」が来て終わっていたのですが、CDではさらに問題の"Summertime"が来ます。この「サマータイム」は賛否両論で、絶賛する人は「アートの心情が直接的に吐露された稀代の名演」であると主張し、否定的な人は「ちょっと臭すぎる」といいます。啜り上げるような泣きでムード満点のアルト・サックスですが私はどちらかというと否定的です。ソニー・クリスの「サマータイム」のようにしつこい小節(こぶし)回しで聴いていて疲れるような演奏ではないですが、演奏と距離がとれず入れあげ過ぎているという印象です。それがいいと思う人には縁があるのでしょうが、ここまで入れ込まれるとちょっと引きます。いずれにせよ、この一曲はアルバムの中での異色作であることは間違いないでしょう。オリジナルでは外されていたことも理解できます。
Tags: alto sax · Pepper, Art
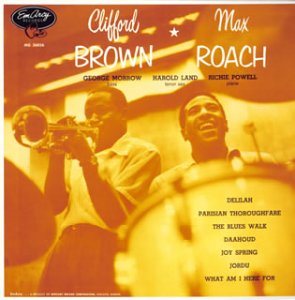
このアルバムもまた、タイトルの付け方がよくないのでアンダー・レイティッド気味だと思える一枚です。グループ名がClifford Brown & Max Roach Quintetで、アルバム・タイトルが Clifford Brown & Max Roach ですからね。そのままじゃないですか(笑)。これに比べると、同じエマーシーの Study in Brown やブルーノートの Memorial Album、 あるいはコロンビアの Beginning and the End などは、タイトルからしてキャッチーでそそられます。
しかしクリフォード・ファンの間では、彼の最高傑作はこのアルバムの5曲目 "Joy Spring"だと言われています。そして私もそうだと思っています。クリフォードの特長は、ディジー・ガレスピーと同じように旋回しながら上昇・下降を急速に繰り返すフレーズを繰り出し、なおかつそこに音の分厚さと輝きを加えたところなのです。ハイノートをヒットしても決して音が痩せたり荒れたりせず、独特の力強さと丸みを帯びた音色で歌い上げていきます。本アルバムの"Joy Spring"でも、その特色が全面に出ているとともに、まるで新しい曲を吹いているのではと思わせるほど構築的で美しいアドリブを繰り広げています。偉大なミュージシャン達でも、ここまで旋律的なアドリブを取るのは容易なことではありませんが、クリフォードはここでそれを成し遂げてしまっているのです。チェット・ベイカーが伝記的映画『レッツ・ゲット・ロスト』の中で楽しそうにこの曲を歌っていますが、様々なミュージシャンに影響を与えた演奏なのだと思います。
さらにCDでは"Joy Spring"の別テイクも収録されていて、クリフォードのアドリブが全くの即興でなされたことが分かります。この別テイク、これだけを聴かされれば「ああ、立派な演奏だな」と思えるのでしょうが、本テイクを知っているだけに物足りなさを感じます。しかし、それだけ本テイクが完璧なソロであるという証拠でもあり、聴き比べることでクリフォードがいかに一瞬でメロディーを構築し、いささかの逡巡もなく繰り出してくるのかがはっきりと理解できるのです。テイクごとの聴き比べは、私自身パーカーで痛い思いをしているのでやみくもに薦めることは出来ませんが、この "Joy Spring"に限ってはぜひ聴き比べて下さい。"Joy Spring"の話ばかりになりましたが、その他の曲も聴き応えがあります。しかし、このアルバムはやはり"Joy Spring"を聴くアルバムであるのも事実だと思います。この驚異的なアドリブラインを用いて、後年マンハッタン・トランスファーがヴォーカリーズ(歌化)しました。その際にシェークスピアの引用を行っていて、アドリブ最後のフレーズは "Signifying nothing" (意味などない)で結ばれる『マクベス』の中でも、いや歴史上もっとも有名な一節が登場します。このマクベスの独白について以前に記事を書きましたので、興味があったら読んでみて下さい。
Tags: Brown, Clifford · Roach, Max · trumpet
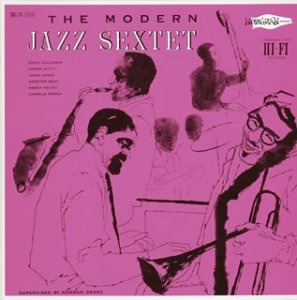
ルイ・アームストロング?ロイ・エルドリッジというジャズトランペットの王道を引き継いで、チャーリー・パーカーと一緒にバップを主導したのがディジー・ガレスピーですが、日本においてはパーカーと比べるとずいぶん人気が低く、トランペッターという枠組みでもマイルスやクリフォード・ブラウンに大きく水をあけられているのが実状です。「アメリカではマイルスより人気がある」という話を聞いたことはありますが、実際に確かめたわけではないので何とも言えません。ただ、10年ぐらい前にインテルのCMで"Dizzy's Atomosphere"が使われていたのが印象的です。日本であまり人気が出ない原因は、彼がビッグバンドやラテンリズムにおいて活躍していたこと(日本ではスモール・グループで4ビートがもっとも評価されます)、アルバム作りが粗雑で印象的なタイトルがあまりないこと、そしてパーカーやマイルスの演奏には陰があるのに対して、ディズは陽の印象が強いことなどだと思います。
ビッグバンド主体、ラテンリズム多用というのは趣味の問題なので何とも言えませんし、アルバム作りが粗雑というのはたしかにそうで、実際には多作なのですが印象に強く残るアルバムというと数えるほどしかありません。しかし「ディズは陽気一点張り」というのはかなりの誤解だと思います。たしかにトランペット職人としてハイノートヒットばかりを狙っているときは陰影を感じさせず単調な感じがしますが、一転して中音域主体のちょっとダークなトーンでの演奏になるときわめてニュアンスに富んだ、味のある演奏を繰り出します。その点も実にルイ?エルドリッジ・ラインの衣鉢を継いでいるといっていいでしょう。
今日紹介するアルバム、実は名義人なしのアルバムで、モダンジャズ・セクステット(というワンナイト・グループ)による、『モダンジャズ・セクステット』というタイトルのアルバムなのです。こういう形態のアルバムもあまり人気が出ず、実際の演奏内容と比べると、ずいぶんアンダー・レイティッドな感じです。もしこれがディジー・ガレスピー:『パーカーに捧げる』なんてタイトルだったら絶対に上位に来るはずです。もちろん、これはガレスピーの責任ではなく、プロデューサーのノーマン・グランツにその責任があると思いますが。
1曲目の"Tour de Force"(離れ技)が名演です。最初、ディズのハイノートで派手に始まるので「あちゃー、またか」と思いますが、ソニー・スティットのパーカー風ダブルタイム主体のアルトソロの後に出てくるディズは中音域を主体にして渋く歌い始め、コーラスごとにパワーをましてハイノートに到達しますが、終始リラックスして歌うソロを取ります。つづくジョン・ルイスのピアノがこのディズと対照的に力の抜けたソロ。冒頭で「ナウ・ザ・タイム」をパロったようなフレーズを弾いたり、「オーバー・ザ・レインボー」の一節を引用したりとユーモアあふれる演奏ですが、この人もまた決して破綻しない構成的なソロを取る人ですね。次に出てくるスキーター・ベストはこのアルバムでしか聴いたことがないと思いますが、地味だけれどジャズ・ギターらしいソロを取ってます。
2曲目の"Dizzy Meets Sonny"はいわゆる「リズムチェンジ」の曲で、アップ・テンポに乗ってビバップの妙技が競われる演奏です。後半では4バースが繰り広げられます。3曲目の"Ballad Medoley"では"Old Folks"でスティットが、"What's New"でジョン・ルイスが、"How Deep Is the Ocean"でディズがそれぞれフィーチャーされます。"How Deep"はパーカーの「ダイアル・セッション」におけるラストナンバーでもあり、ディズの演奏はパーカーに対するオマージュにもなっているようです。4曲目 "Mean to Me"も快演です。ラストの"Blues for Bird"はタイトル通り、パーカー(バード)に捧げたブルースですが、スティットのソロはおそらく"Funky Blues"(Norman Granz Jam Session 収録)でのパーカーソロを模したものだと思われます。しかし、パーカーには顕著な陰影が薄くて、どちらかといえば平板な感じなのはスティットの特徴ですかね。
ディズを聴くなら、この他ロリンズやゲッツのと「ミーツ・シリーズ」、『ニューポート』のようなビッグ・バンド作品、『マンディカ』や『ジャンボ・カリベ』のようなラテン作品も楽しいと思います。あるいは、パブロの「モノクロ散文ジャケ」時代(笑)のものも聴き所満載です。でもこの一枚っていうと、実は『バード&ディズ』が一番いいんじゃないかって思っていたりします(笑)。
Tags: Gillespie, Dizzy · trumpet
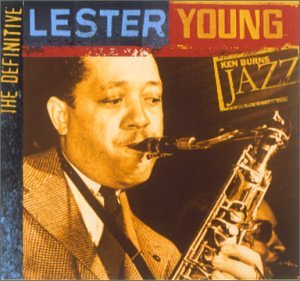
Lester Youngは私がもっとも好きなテナー奏者で、その好きさ加減が高じて高校時代は彼のポートレイトを何枚も描いたりしていました。
この人のテナーは独自の音色で、リズムに急かされるわけでもなければ逆らうわけでもなく、ゆったりと自在の間で乗っていき、止めどなくしなやかな旋律が流れ出てくるところが特徴です。歴史的にはコールマン・ホーキンス流のテナーに対するオルタナティヴを提示したという点や、のちの白人モダンテナー(スタン・ゲッツやズート・シムズら)に影響を与えた、あるいはパーカーがレスターのソロを完コピしたという点が重要になってくるのでしょうが、それ以前にレスターの演奏そのものが果てしなく美しいということを忘れてはいけません。また、すぐれたジャズマンに共通する要素、つまりソロがはじまるやいなや「レスター登場!」という空気が広がるのも、彼のすごさだと思います。
ここに紹介する『ケン・バーンズ・ジャズ・コレクション』シリーズは、従来のコレクション・アルバムと違いレーベルの枠にとらわれず、様々な権利関係をクリアして本当の名演だけを集めているのが特色です。もちろんいろいろ障害もあるようで、なぜかサヴォイ系の名演"Blue Lester"が含まれていないのが惜しまれますが。冒頭の "Lady, Be Good!"は上で述べたパーカーが完コピした演奏です。これはレスターにとっての最高傑作であるばかりでなく、ジャズ史上でもサッチモの「ウェスト・エンド・ブルース」やエリントンの「ジャック・ザ・ベア」、パーカーの「ココ」やマイルスの「ソー・ホワット」と肩を並べる名演中の名演です。斬新でいながら美しい旋律が汲めども尽きぬ泉のようにこんこんと湧き出て、そのワンフレーズワンフレーズが原曲はおろかそれより前のフレーズを凌駕してゆきます。3曲目の"Honeysuckle Rose"はベイシーのデッカ録音からのトラックでしょう。意表をつくような出だしから自在のリズムを繰り出し、最後に得意のクラクション音までぶっぱなす乗りっぷりです。冒頭に聴けるベイシーのピアノソロも「ゴキゲン」ですね(笑)。5?6曲目はビリー・ホリデイとのコラボで有名な録音です。いわゆる「ブランスウィック・セッション」。"Sailboat in the Moonlight"での自由なソロはレスターの真骨頂です。
レスター本人が「もっとも気に入っているソロ」といったのは9曲目"Taxi War Dance" です。これはベイシーバンドのコロンビア系録音で、当時としては珍しく曲が出る前にアドリブを始めているのですが、そのアドリブのすごいこと。いきなりメジャーに対してマイナーキーで挑んでゆきます。それもオールマンリヴァーをマイナーで吹いたフレーズです。レスターの特徴の一つはこのようにメジャーのコードに対してマイナーフレーズを吹くところだと言われています。レスター作曲で、その後も長くジャズマンに取り上げられることとなった曲が"Lester Leaps In"(12曲目)で、パーカーがJATPやロックランドパレスで信じられないような名演を繰り広げています。つづく"Tickle Toe" でもバンド、レスター本人とも乗りに乗った名演です。
"Sometimes I'm Happy"は「キーノートセッション」として知られるもので、曲想とレスターのイメージがぴったりと符合してしなやかなソロを繰り広げています。15?17曲目は「アラジン・セッション」でしょうか。とくに17曲目"Jumpin' with Symphony Sid" はレスターのオリジナルでレスターらしさのでた名曲ですが、「レスター・リープス・イン」とは対照的に取り上げられる機会の少ない曲で、スタン・ゲッツとデイブ・ペルが演奏しているのしか知りません。
実は私、このアルバムは持っていません(笑)。これらの録音はすべてそれぞれのオリジナル音源で持っているのですが・・・どの音源からのものであるかは、アマゾンのサンプルを聴いて見当をつけて書いています。もし間違っていたら平にご容赦を。それにしても、オリジナルでそろえれば何枚にも渡ってしまうものを、こうしてよいところだけを抽出した一枚で聴けるというのは実にありがたいことだと思います。
この記事で取り上げたCD
Tags: tenor sax · Young, Lester
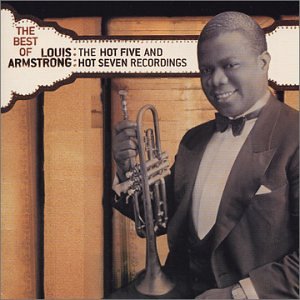
たとえば陽気で心地よいディキシーランド・ジャズをテレビなどで耳にし、「さて、ディキシーランドジャズの元祖といえばルイ・アームストロング(サッチモ)だ」(これは大きな間違いですが、いまだに流布しています)と何かの本で読み、このアルバムを買ったとしたら「全然違う!」と叫びたくなるでしょう。あるいは、名曲「このすばらしき世界("What a Wonderful World")」を愛知万博で耳にしてサッチモに興味を持ち、彼のベストだと教えられてこのCDを聴いたら失望する人も多いかもしれません。
何でそんなにキケンなCDを薦めるのかというと、これがジャズの原点だからです。ジャズが初期の「コレクティブ・インプロビゼーション(集団即興演奏)」から、徐々に個人のソロを中心とする音楽に変貌を遂げつつあったとき、その手本となったのがここで紹介する、サッチモのホット・ファイブ、ホット・セブンの吹き込みでした。これらの演奏は一作一作が新たな試みであり、言い方を変えれば当時の「モダンジャズ」あるいは「前衛ジャズ」であったわけです。したがって上で述べたような「心地よいディキシー」のような安定感は全くありません。むしろ、スリリングな新しい芸術創造の過程を聴くことができるのです。
一曲目の"Heebie Jeebies"。スキャットがはじめて吹き込まれた瞬間です。「録音中に歌詞の紙を落としたから仕方なしにスキャットを歌った」というのはどうやら伝説で、当時からニューオリンズでは行われていた歌い方だったようですが、それが全世界へ伝播したのはこの吹き込みによるものです。5曲目の"Wild Man Blues"はその少し前に、ジョニー・ドッズ名義で同じ曲が吹き込まれていますが全く対照的です。ジョニー・ドッズ名義の録音がシンプルなブルース演奏であるのに対して、こちらの演奏はストップタイムを利用して複雑を極めます。同じくストップタイムを用いたすばらしいソロは8曲目"Potato Head Blues"でも聴くことができます。ここのソロのリズム構成、これぞジャズのリズムであり、耳を澄ませばモダン・ミュージシャン達の演奏の中からも彼のフレーズやイントネーションが聞こえてくるのに驚かされます。そして、ジャズ史上最大の傑作といわれるのが12曲目の"West End Blues"。冒頭のカデンツァ、中間部のスキャット、最後の方で一音を4小節のばし、その後複雑を極めたフレーズに突入するスリル。そして最後に「キャポッ」という正体不明のノイズ。最初から最後まで全部ジャズの姿を決定づける作品で、この演奏を聴いてミュージシャンを志した人はビリー・ホリデイをはじめとして数知れないといわれています。そして、最後の曲"Tight Like This"。「こんなにコチコチになって」という意味深なタイトルと歌詞からふざけた曲だと思われそうです(そして実際、ドン・レッドマンが女性の声色を使っていたりしてふざけているのです)が、後半に出てくるサッチモのソロは低音、中音、そして高音と積み重ねていくことでその構成美を遺憾なく発揮しています。もちろん、ここで紹介した以外の曲も聞き所満載です。
最後にこの時期のサッチモを推薦する油井先生の名文を紹介したいと思います。
冒頭に述べたように戦後のサッチモのレコードを聴いていたのでは真の偉大さが分からない。『タウン・ホール・コンサート』(ビクター)、『シンフォニー・ホール』(デッカ)、『プレイズ・W. C. ハンディ』(CBS)は戦後としてはいい出来だが、ジャズ史をゆるがすような作品ではない。音の悪さを忍んで、CBS盤またはオデオン盤に収められた1920年代の傑作を聴いてほしい。その一作、一作に全ジャズ界がどよめいたのである。
ファンのみならずプレイヤーも時代を超え、スタイルを越え、史上最大の巨人を時折りきいてみることだ。」(『ジャズ歴史物語』)
この記事で取り上げたCD
Tags: Armstrong, Louis · trumpet

名曲"Blue Monk"に対する思いの丈については、以前ブログに「理性が雲散霧消する曲」という記事を書きましたが、今日紹介するMonk's Musicもそれらに劣らない名作です。
モンクというピアニストは、綺麗めのジャズピアノを聴いて「ジャズピアノっていいなぁ、おしゃれだな」と思っているような人が最初につまずくピアニストです。事実、数年前に「キースを聴いてジャズピアノに入門しました。同じような感じのジャズピアノないですか?」と質問され、からかい半分でモンクを紹介(セシル・テーラーでなかったのはせめてもの情け)したところ、「すぐに買ったけれどなんか違う」と連絡がありました(笑)。事情を話すと怒っていましたが、「モンクを聴かなくちゃ、ジャズは分からない。ジャズの奥深さを知ってもらおうと、わざと紹介した」と詭弁を弄したところ、なんとか納得してもらいました。
もちろん、この場での発言は詭弁なのですが、「モンクを聴かずにジャズを語るなかれ」というのは、厳然たる真理です。なぜでしょう?一般に、ジャズというのはクラシック的な価値観では否定されそうな要素が、堂々とまかり通っている。その一つが「美しさ」の概念です。ジャズではサッチモのだみ声から、ピーウィー・ラッセルのグロール・クラリネット、エリントンの濁ったようなコード、コールマン・ホーキンスのテナーサウンドのように、それ以前の古典音楽では「汚い」とされていた音使いを用いることで、新たな美を創造しています。モンクのピアノもパーカッシブな奏法と、独自の和声感覚で一聴すると「なんかずれている」「濁っている」と感じられるのですが、慣れてくるとこの感覚がたまらなくなってくるわけです。一曲目の賛美歌"Abide with Me"は、とても賛美歌とは思えない、あるいは「中学校の下手なブラバンが演っているんじゃないか」と思わせるような、ずれた音色で演奏されています。そしてそのまま、二曲目"Well You Needn't"に滑り込んでいくところが絶妙だと思います。
この曲では、モンクが不意に叫んだり、ドラムのアート・ブレイキーがつられてとちったりするのですが、全く意に介せず演奏は進行し、そのまま本テイクとして発表されているのです。そしてここにも「ジャズとはなんぞや?」という問いに対する答えが見え隠れします。私がジャズに入門したての頃、一番驚いたのは「チャーリー・パーカーの別テイク」でした。一枚のLPを買って「16曲あるな」と思っても、よく見ると同じ曲の別テイクが何曲も収録されていて、正味8曲ぐらいしか入っていない、ということにビックリし、なんだか詐欺にあったような心持ちがしました。中には失敗した演奏まで入っているんですからね。しかしジャズを聞き込むにつれて、だんだん「こういうのもありかな?」と思えるようになってきました。一つの完全無欠な形を目指して、その途中を切り捨てるのではなく、音として出してしまったものはとりあえず受け入れようという姿勢です。そしてその失敗が全体をダメにするようなものならともかく、ちょっとしたミスならコミで考えようということです。実際、サッチモ不朽の名演"West End Blues"にしても、最後に「キャポッ」っていう正体不明のノイズが入っていますしね。それにしても、この"Well You Needn't"、そんなとちりもどこ吹く風とばかり、演奏全体がドライブして、グルーヴしています。つづく"Ruby, My Dear", "Off Minor"は順調に進みますが、5曲目"Epistrophe"で、またもやブレイキーがとちり、コールマン・ホーキンスが2回ほど飛び出しをやります。しかし、演奏全体の価値は少しも減りません。最後はモンクが「小シンフォニー」と位置づけ、アドリブを許さなかった名曲 "Crepuscule with Nellie" で閉められますが、この曲を「調子っぱずれだ」ではなく「キレイだ」と思えるようになればジャズファンといえるでしょう。
モンクの代表作というとBrilliant Cornersがあり、そちらはロリンズが参加し、演奏ももっと完成されまとまりがありますが、私はこのMonk's Musicのほうが好きです。
この記事で取り上げたCD
Tags: Monk, Thelonious · piano
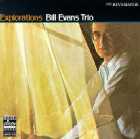
ビル・エバンスの代表作は「リバーサイド4部作」、すなわち『泥の川』『螢川』『道頓堀川』・・・は宮本輝の「川」三部作で(笑)、こちらはPortrait in Jazz, Explorations, Waltz for DebbyそしてSunday at the Village Vanguardの4枚。この4枚はベースの名手スコット・ラファロとの共演が収められているためそう呼ばれるわけです。それまでのピアノトリオは、下で紹介したバド・パウエルのようにピアノが主でベースとドラムが従の位置に立っていたのですが、このエバンス~ラファロ~モチアンによってピアノ~ベース~ドラムスが正三角形を描いて対等に絡み合う独特のピアノトリオのあり方が提示されました。これを「インタープレイ」と呼びます(タイトルが『インタープレイ』というエバンスのアルバムがありますが、これは無関係です)。もちろん、単なる実験作ではなく、完成度の高い永遠のピアノトリオということができます。ラファロはこのトリオでの活動中交通事故にあって亡くなるのですが、そのたしかな腕前、イケ面風のルックス、わがままな性格といった特徴と相まって伝説のベーシストとなっていきます。私個人としては、ラファロのベースを楽しみたいならオーネット・コールマンのFree Jazzを聴いた方がよいと思っていますが、最初からこんなの聴いてもラファロ以前にアルバム全体のコンセプトで挫折してしまうでしょうから、エバンストリオがやはりお勧めです。
その「リバーサイド4部作」の中でも、とくに気に入っているのが今日取り上げるExplorationsです。4部作の中では一番地味だけれど、一曲目の「イスラエル」から「ビューティフル・ラブ」、「エルザ」を経てマイルス作曲の「ナーディス」にいたる部分が非常に優れているのでこれを紹介します。「イスラエル」から「ナーディス」まで。ここにはピアノトリオのかつて到達し得なかった経験が収められています。もっとも、LPではたしか「ナーディス」がB面1曲目だったのでこうした流れが見えづらかったような気もします。
ところでこのラファロ。イケ面風なのですが性格が悪く、エバンスを脅してはギャラを前払いさせていたそうです。天才でルックスもいいのに、その性格に難がある。私は、最近日本を出国してアイスランドに行ったチェスの天才、ボビー・フィッシャーを連想してしまうのですが。
この記事で取り上げたCD
Tags: Evans, Bill · piano