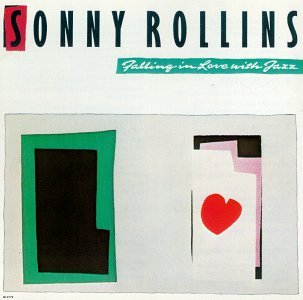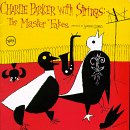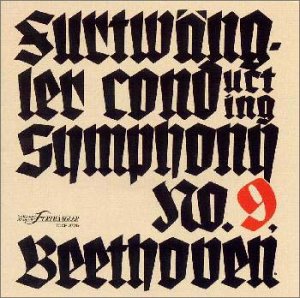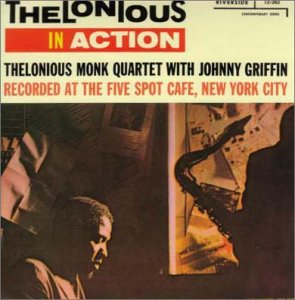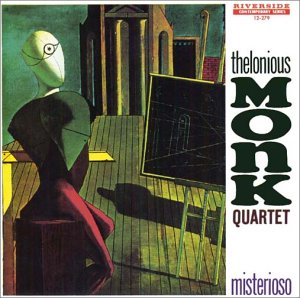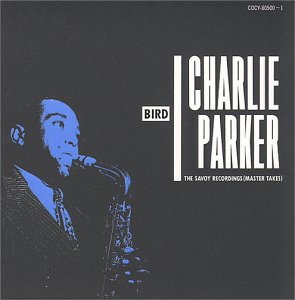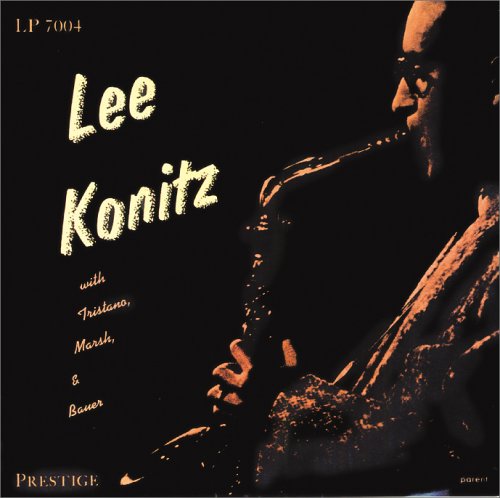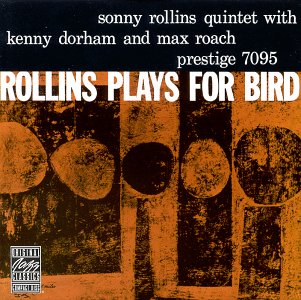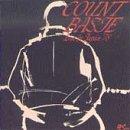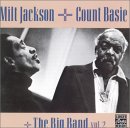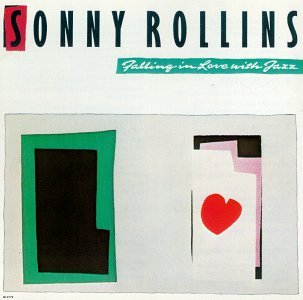
これは、ちょうど"Tennessee Waltz"がはいっているアルバムならなんでも買い漁っていた時期に買ったアルバムです。邦題は『ジャズに恋して』・・・ケニー・ドリュー「北の国からシリーズ(笑)」と同じ頃だったので、"Tennessee"が入っていなければ買わなかったかもしれません。テナーの "Tennessee"というと、下手をすれば「むせびなくムードテナー:愛のポピュラー音楽」なんて感じのタイトルの海賊版CDに入っていそうな演奏を思い浮かべますが、そこはロリンズのこと、きっちりとジャズに仕立てています。この辺のことは、技術よりも倫理の問題であるような気がしますね。
ロリンズのバラード解釈は、ずっと元をたどるとコールマン・ホーキンスの「ボディー・アンド・ソウル」でとにかく音数が多くて説得的なんですよね。演奏が縦方向というか小節毎のコードを全部吹ききってやろうという感じです。まぁ、しかし絶品。 "Tennessee Waltz"の演奏としては最高の一つじゃないですか。ギターはジェローム・ハリスという人で、この人の事はよく知らないんだけれど結構泣かせるソロを取ってます。
この記事で取り上げたCD
Tags: Rollins, Sonny · tenor sax
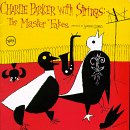
やはり最初はパーカーでしょう。最初に聴いたパーカーがこれです。といってもFMラジオで1曲だけ、"April in Paris"でした。さっそく千葉市内のディスクユニオンに走って行き購入しましたが、当時はこういうジャケじゃなかったんですよね。曲数もこんなに入っていなかったし。買った当初は"April in Paris"や"Summertime"にぞっこんでしたが、聴きこんでいくうちに"Just Friends"が浮上してきました。アマゾンのサンプルでも聴けるけれど、この出だしにやられました。こういうアルバムは、立派なオーディオ装置を使って大音量で聴くよりも、片隅で小さく流れていたほうが様になります。以前に、高円寺の居酒屋でこれがさりげなく流れていたときには、ジーンと来ました。ビリー・ホリデイなんかもそうですね。
この記事で取り上げたCD
Tags: alto sax · Parker, Charlie
アルトのジャッキー・マクリーンが亡くなりましたね。
50?60年代のプレスティッジ、ブルーノートを盛り上げたハード・バップの申し子みたいな人で、ちょっと怪しいピッチとくすんで塩辛い音色(アルトは普通艶やかな音色になる)で、一聴してわかる独自の個性を持っていました。
彼はリーダー作だけでなく、サイドマンとしても活躍していましたから、BNの有名どころを聞けば必ず聞こえてくる人でもあります。特に私が好んで聞くのが下にジャケットを挙げたA Long Drink of the Bluesです。

私はLPで持っているのですが聞くのはもっぱらB面。ワン・ホーン物でスタンダードをやっています。"Embraceable You", "I Cover the Waterfront", "These Foolish Things"とビリー・ホリデイの得意曲を並べアルト一本で陰影豊かに吹いているのが心地よい。Left Aloneと同じで、ビリーのフィーリングをうまく伝えています。しかし、このアルバムが一番好きというあたりに自分の趣味の保守性に改めて気づいたりもします。Damon's DanceやJackie's Bagといった後期の名作もファイバリットには挙がらないし、Let Freedom Ring!なんていう「おっかない」タイトルのものには(笑)端から食指が動かないからです。
LPのA面、タイトル曲でもある"A Long Drink of the Blues"はブルースのスタジオセッション。ミスリードがあって録り直しになり、賑やかに騒いでいる模様などがそのまま録音されています。
2006年3月31日(享年73歳)
合掌
この記事で取り上げたCD
Tags: alto sax · McLean, Jackie · 雑記
第九は年末と決まったものではないのでしょうけれど、テレビやラジオ、そして街角でこの曲を耳にする機会が増えるのはやはり年末ですね。
私はジャズ・ファンなのでクラシックは苦手です。とくにテンポが頻繁に変化するのとドラムが入っていない(ってあたりまえですが)ことが聴いていて落ち着けない原因だと思います。それでも付き合いがあるので第九ぐらいは何度か聴きにいったり、CDを聴かせてもらったことがありますが、やはりこれはホールかなんかで聴く方がいいですね。
冒頭はDとAを長く伸ばす音から始まるのですが、これは三度の音が定まっていないパワーコードなのでまだ調が決まらない感じがする。ところがホールでは倍音の関係で必ずF#が発生しますから、最初Dメジャーだと思うんですね。しかしこの曲、実はDマイナー。引っかけられるわけです(笑)。これは多分ベートーベンの作為や悪戯だと思うのですが、CD演奏だとこの倍音があまり発生せず平たい印象になります。まして、最後の合唱のところはCDがどう逆立ちしてもホールで圧倒的な人数で歌われる迫力には敵わない。やはりこの曲は、演奏の上手い下手はどうあれ、ホールで聴くべき曲だと思います。
そんな中で、「これはCDで聴いてもいい演奏だな」と思ったのが下に挙げたフルトベングラーの第九です。
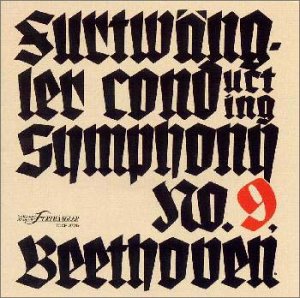
私には細部を逐一検討して批評する能力も時間もありませんが、とくに好きなパッセージを聴いてみて、これは深い!と感じたのです。それは、一回目の合唱が終わって行進曲風の独唱が始まり、そこに合唱が絡んだあと、楽器だけになり激しく上昇下降を繰り返すフレーズが交差して様々なテクスチュアーを織りだしていく、あのきわめてエモーショナルな一節です。ここにやられました。他の演奏も何回か聴いたことがあるのですがこの演奏ほど深い感動は得られませんでした。
ジャズファンなのでトータルよりも部分聴きで判断してしまう傾向がありますが、これはいい演奏だと思いました。
Tags: Rock, Pops, Classical · 雑記
音楽を聴きながら、「あそこはいけないね」「ここはこうしたほうがよいね」とうるさい事おびただしい聴き方はきらいだ。せっかく時間を使って音楽聴いているのにそんなにヒハン的にならなくてもいいんじゃないかと思う。だったらもっと政治を批判せよ!と思わず立ちあがりたくなるが、立ちあがっても次にする事がないので立ちあがらないでおく。同じように、LPコレクターの中には「ああ、ここでノイズが出る」「これはノイズが多くていけないね」などとノイズに集中した聴き方をしている人もいるが、これもどうかと思う。古いLP聴いてんだからノイズぐらい出るでしょ?もっとゆったりした聴き方しなさいよ!と叫びたくなるが、叫ぶとその後よくない事が起こりそうなので静かにしておく。と、よく考えると私のほうがずっと批判的になっているのだ・・・
ヒハン的・懐疑的になったときにそれらの気持ちをふっとばす曲がある。ひとつは以前にも書いた「シャイニー・ストッキング」であるが、もうひとつは「ブルー・モンク」である。このB♭のブルースをやってもらうと、どんな場合でもヒハン的な気持ちは消えうせニヤニヤしてしまう。人前でニヤニヤしてしまうなど理性すら雲散霧消したような格好だ。
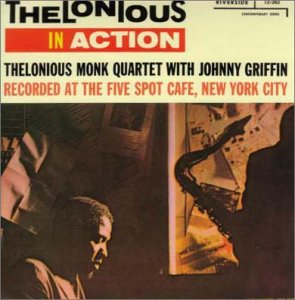
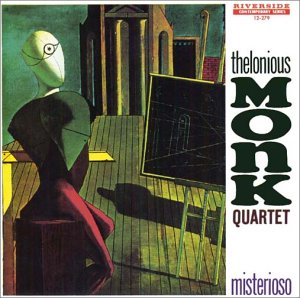
そういう曲だから、どのアルバムがいい、どのジャズマンの演奏がいいなどと挙げることじたい自己矛盾な気もするが、よく聴くのはオリジナルの『トリオ』ではなくて、上のにジャケットを挙げた『セロニアス・イン・アクション』である。これは名盤『ミステリオーソ』(写真右)と同日ライブのものであるが、ミステリオーソはジャケットにキリコの絵をあしらってもらったりしてずいぶん厚遇を受けているのに対して、こちらはポール・ベイコンのデザインとはいえ散文的なジャケットで冷遇されているような感じがし、ちょっとその辺どうなっているのよ!?と問い詰めたい気持ちになるが、いけないいけない・・・
ここでの「ブルーモンク」はもう爆発している。聴衆はざわめいているし、途中で電話が鳴ったりするが、そんなのお構いなしにグリフィンが吠え、モンクが叩く。そういえば以前に吉祥寺「メグ」でこれを聴いたとき、演奏中に鳴る公衆電話の音が店の電話の音と聞き間違うほどリアルだったのを思い出す。またメルドーを教えてくれたピアニストが、このアルバムの録音技師が用いた手法について話してくれたのだが、「ブルーモンク」中だったのでどんな話だったか忘れてしまった(笑)。
この記事で取り上げたCD
Tags: Monk, Thelonious · piano · 雑記
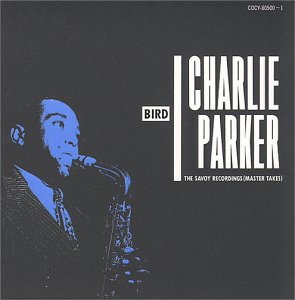
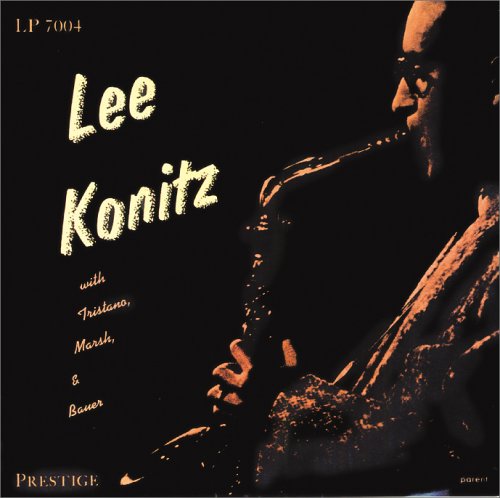
パーカーの伝記映画「バード」はパーカー役の俳優が笑福亭鶴瓶に、妻のチャン役の女優もどことなく久本マチャミに面影が似ていて、別の番組を見ているような気になってしまう(笑)。さらに問題なのはパーカーの音楽観が著しく歪められている点で、パーカーがロックンロールに偏見を持ってアルトサックスを盗み出してしまうシーンなど、見ていていささか白けてしまう。実際のパーカーは芸術の間の障壁を認めていないのだから。一方、バップのアイデアを思いついた瞬間についてはレトリカルで雄弁である。「ある晩、俺が渡ったのはチェロキーの橋(ブリッジ)だった」というのがそれだ。この「橋を渡ってしまったチェロキー」をレコーディングしたものがサヴォイ・セッションの「ココ(ko ko)」。最初聴いたときはめまぐるしいだけで、こんなの一体どこがいいのか分からなかったが、何度も何度も聴くうちにその良さが見えてきた。
パーカーの「ココ」に刺激を受けたせいかどうかは分からないけれど、同じチェロキーで勝負を挑んだミュージシャンの一人がリー・コニッツであった。名盤サブコンシャス・リーB面1曲目の「マシュマロ」という演奏がそれだ。テーマはユニゾンを用いてパーカと一線を画しているけれど、アドリブに入るとどうしても「ココ」が見え隠れしてしまうところが面白い。全体のテクスチャーはしかし大違いで、パーカーが真っ赤な火炎だとすると、コニッツはむしろ青白いガス灯の炎のような感じである。「コニッツ」とコールすると、即座に「クール」とレスポンスが返って来るけれど、コニッツを聴いて「クール」だと感じた事など一度もない。いつも微熱を伴ったような演奏だなぁと感じていた。これは、コニッツがもともと「クール」などではなかったのか、それとも現代のほうがもっとクールな演奏が多くなって、相対的に熱く感じてしまうのかは判断のつかないところである。
この記事で取り上げたCD
Tags: alto sax · Konitz, Lee · Parker, Charlie · 雑記
「ジャズの聴きかたに法則はない」といったのは寺島さんであるが、ジャズであれなんであれ方法を学ぶ事は大事だと思う。とりわけこの感を強くしたのはブラッド・メルドーの「ライブ・アット・ザ・ヴィレッジヴァンガード」の聴き方を某ピアニストに手ほどきしてもらったときのことであった。
これはいつも行くタワレコでかなりお勧め度が高かったので購入したのだが、あまりピンと来なかったので聴かないで仕舞っておいた。あるときそのピアニストが遊びに来て「いいの持っているじゃん」と言いながらこれをかけたから、この演奏に感じる不満をぶつけてみた。「この『オール・ザ・シングス』のテーマ、フシが間違ってない?」、「アドリブパートも、なんだかギクシャクして訳が分からないんだけれど?」等々。
その人の言うには「これはリズムをギリギリまで改変している演奏なんだ」、「右手と左手で違うビートを演奏している」ので、「聴くべきところはそうした複合的なリズム(ポリリズム)なのだ」ということであった。そしてポーズ機能を使いながら、それぞれの演奏と聴き所のポイントについて解説をしてもらった。その後で見違えるほどこの演奏がよく聞こえた、というドラマチックな事はなかったが、彼の解説を念頭に置きながら何度か聴いているうちにおぼろげながらこのアルバムのすごさが見えてくるようになった。
「音楽を学ぶなんておかしい、感じればいいだけなんだ」という意見をたまに耳にするが、それは違うと思う。思想や学問だけではなくて感性もまた学ぶことによって磨かれていくのだから。感性一発勝負の天才に見えるパーカーもこう言っている。
学問はあらゆる形式で絶対的に必要なものだ。どんな才能も、なにもせずに生じる事はない。履き心地のいい靴を、ぴかぴかにするようなものだ。学校教育が、この世のどんな才能にも洗練をもたらす。アインシュタインだって学校教育を受けた。彼自身が天才だったのも確かだけれど。学校教育はこの世で最もすばらしいものの一つだと思うよ。(カール・ウォイデック著『チャーリー・パーカー―モダン・ジャズを創った男』
この記事で取り上げたCDと書籍
Tags: Meldau, Brad · piano · 雑記
ジャズを聴き始めたのはFMラジオ流れていた「シング、シング、シング」を聴いたのがきっかけです。といっても『スイングガールズ』じゃないですよ(笑)。ベニー・グッドマンの演奏、それもカーネギーホール40周年記念コンサートの際のものでした。上の写真はそのアルバムのジャケットです。
1938年の「シング、シング、シング」ではジェス・ステイシーというピアニストが活躍するのですが、そのパートをバイブのライオネル・ハンプトンが受け持って、一夜のハイライトを作り上げています。この40周年コンサートはまったくの「回顧調」というわけでもなく、「ロックロモンド」でマーサ・ティルトンと掛け合うところ以外はほとんど新しい構成で臨んでいます。
なんてことは全部、後に知ったことなんですけれど・・・もし最初の「シング、、、」がこのバージョンじゃなくてオリジナルバージョンだったら私はジャズを聴くようになったでしょうか。そんな事は誰にもわかりません。しかし、ドラムはジーン・クルーパーです。
この記事で取り上げたCD
Tags: big band · Goodman, Benny · 雑記
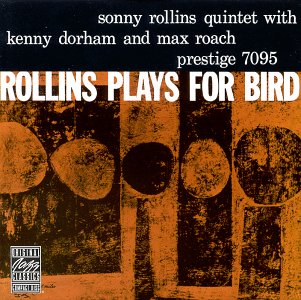
このアルバムは『プレイズ・フォー・バード』というタイトル通りA面はパーカーメドレーとなっていますが、何度聴いても一番心に訴えてくるのはB面の"i've grown accustomed to her face"です。『ウェイ・アウト・ウェスト』の"solitude"もかなしいし、『ジャズに恋して』の"tennessee waltz"なんか同曲の最高傑作だと思うけれど、この曲が一番切々としている。そこでちょっと調べてみたら、この録音はクリフォードが事故死した三ヶ月後の録音なんですね。ご存知のように、ロリンズとクリフォードは同じバンドで演奏していました。だからクリフォードの死はロリンズにとって相当のショックだった。そこで実はこの曲、クリフォードへの哀悼を示す演奏なのではないだろうかと推察できるわけです。
問題はこの曲のタイトル・・・邦題は『あの子の顔に慣れてきた』・・・これはいくらなんでも無茶です(笑)「ブスは三日で慣れる」って歌詞じゃありません。知っている人も多いと思いますが、これはヒギンズ教授がイライザに去られた後の歌で「君の顔に馴染んだのに今は見れなくて寂しい」という思いの歌なんですよ。むしろ「君の顔が忘れられなくて」とか、「君の影を慕いて」(って古賀政男か!?)といった邦題のほうがふさわしい気がします。そうすると、やはりこの曲の演奏は亡きクリフォードに捧げたものだという推察もあながち間違っていないんではないかと思え、ますますこの演奏が好きになるのです。
ちなみに、これも有名な話ですが"you'd be so nice to come home to"の表題「帰ってくれると嬉しいわ」も間違いですよね。理屈はこうなります。
This car is easy to drive.→It is easy to drive this car.
You'd be so nice to come home to.→It would be so nice to come home to you.
英語では漠然といってから、具体的にいう事が多いからまず「帰宅する(come home)」といって「あなたの元へ(to you)」と具体的に述べるわけですね。したがって、この曲は「あなたの待つ家に帰れたらどんなに素敵だろう」という感じのタイトルなわけです。
この記事で取り上げたCD
Tags: Rollins, Sonny · tenor sax · 雑記
ビッグバンドはCDで聴くより出かけて聴く事の方が多い。特に学バンや市民バンドのコンサートなどは積極的に出かけるようにしています(安いから)。でも、そうしたコンサートに出かけても「シャイニー・ストッキング」を演ってくれないとなんとなく釈然としない気持ちになる。ビッグバンドを聴くという事は、すなわち「シャイニー・ストッキング」を聴くことだと乱暴に考えているからです。いったんこの曲が始まれば「あのテナーは云々」「ドラムは人変えたほうが良くない?」といったヒハン的な気持ちは消え去ってあのタイムに身を任せるわけです。
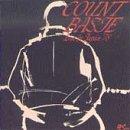
こうした偏った気持ちを知ってか、その学バンのOBで私のテナーの師匠でもある人が「シャイニー・ストッキングの決定盤はベイシーのLive in Japan(1978)だ」と教えてくれました。早速購入して聴いてみたけれど、「ちょっと速くないですか?」という雰囲気もあったが、確かにいい感じであった。
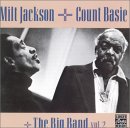
最近出会ったベスト「シャイニーストッキング」はベイシーとミルト・ジャクソンが共演したBig Band, Vol. 2ですが、 これはいい! ゆったりとしながらも精密なベイシーバンドをバックにミルトが自在の間で演奏する。たまたまスタジオに遊びに来ていたサラ・ヴォーンがスキャットで参加する曲もあったりと、ジャズらしさを味わえる1枚でした。
この記事で取り上げたCD
Tags: Basie, Count · big band · piano · 雑記